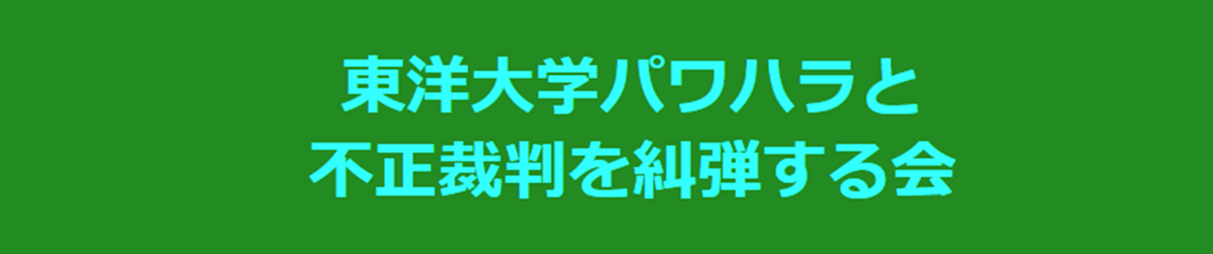東洋大学パワハラ裁判・上告理由書
令和6年(ネオ)第724号 上告提起事件
上告人 福田 拓也
被上告人 学校法人東洋大学
上告理由書
2024(令和6)年10月29日
最高裁判所 御中
上告人 福 田 拓 也
上告人は、頭書事件について、以下の通り上告理由を述べる
目次
第1 本件訴訟の事案の概要と上告人の主張の骨子…………………………………4
1 本件訴訟の事案の概要………………………………………………………………4
2 第一審判決と原判決(控訴審判決)………………………………………………4
(1)第一審判決…………………………………………………………………………4
(2)原判決(控訴審判決)……………………………………………………………5
3 上告人の主張の骨子…………………………………………………………………5
(1)憲法違反(上告理由1~3)……………………………………………………5
(2)理由不備及び理由齟齬(上告理由4~6)……………………………………6
第2 憲法32条違反、憲法14条1項違反及び憲法76条3項違反(上告理由1、上告理由2及び上告理由3)……………………………………………………………8
1 原判決による第一審判決の不当な書き換え………………………………………8
2 原判決の犯した憲法違反……………………………………………………………34
(1)憲法32条違反(上告理由1)…………………………………………………34
(2)憲法14条1項違反(上告理由2)……………………………………………36
(3)憲法76条3項違反(上告理由3)……………………………………………37
第3 原判決の理由不備(上告理由4、5、6)及び理由齟齬(上告理由7)……40
1 原判決が第一審判決の「引用」に際して犯した夥しい判断遺脱の法令違反…41
(1)第一審判決における前提事実の遺脱に関する上告人の主張についての判断遺脱……………………………………………………………………………………………41
(2)第一審判決における争点変更の法令違反に関する上告人の主張についての判断遺脱………………………………………………………………………………………41
(3)第一審判決における本件行為1~9及びパワハラの長期にわたる継続性と大規模な組織性及び安全配慮義務違反に関する認定事実の誤りと遺脱に関する上告人の主張についての判断遺脱………………………………………………………………42
(4)第一審判決における本件行為1~9及びパワハラの長期にわたる継続性と大規模な組織性及び安全配慮義務違反に関する夥しい法令違反に関する上告人の主張についての判断遺脱………………………………………………………………………42
2 原判決「引用」部分以外における判決に影響を及ぼす重要な具体的事実についての判断遺脱の法令違反…………………………………………………………………44
(1)上告人の主張追加部分における具体的事実の遺脱……………………………44
(2)原審における上告人の主張部分の認定判断における具体的事実の遺脱……60
(3)パワハラ・不法行為の有無等に関する原判決の判断における具体的事実の遺脱……………………………………………………………………………………………74
3 小括……………………………………………………………………………………78
4 パワハラ行為の発生した状況や文脈及びパワハラ行為の程度、継続期間、頻度、反復性等の様態に関わる具体的事実についての判断遺脱と理由不備………………79
(1)本件行為1~9……………………………………………………………………79
(2)原判決の判断枠組みと理由不備…………………………………………………110
(3)小括…………………………………………………………………………………115
5 上告人の被った精神的苦痛についての判断遺脱と理由不備(上告理由6)…115
6 原判決の理由齟齬(上告理由7)……………………………………………………117
第4 結語………………………………………………………………………………117
第1 本件訴訟の事案の概要と上告人の主張の骨子
1 本件訴訟の事案の概要
本件は、2002年から、長きにわたって、大学の社会の中で、上告人が他の教員と比べて劣位な状況に置かれ、その状況下でパワーハラスメント(以下パワハラとする)を受け続けた上告人が、ハラスメント通報によっても事態が改善しないため、法廷の場でパワハラの違法性とその被害の救済を訴える事案である。
とくに、上告人の場合、パワハラが持病との関係で、命と健康に関わる問題に発展しかねない状況であるだけに、問題として重大性をはらんでいる。
上告人は、本件を通じ、被告の労働環境、安全衛生環境に関する規範意識の低さを告発するとともに、その是正を求め、本件を提起する次第である。
本事案にあって特筆すべきは、被上告人東洋大学による控訴人へのパワハラが本件行為1~9に限定されるものではなく、時期的には、平成14年に始まり、平成20年に激化したものであり、規模の観点からすると、法学部のみならず東洋大学全学の関わる大規模な組織性を有するものであることである。永年の間、大学組織全体で仲間外しされ続け、数多くのパワハラ行為の被害を被った上告人の精神的苦痛は甚大なものであると言わざるを得ない。本事案は、その長期の継続性と大規模な組織性において、未曾有の大学パワハラと言えるものであり、その社会的影響には計り知れないものがあるというほかはない。
2 第一審判決と原判決(控訴審判決)
(1)第一審判決
上告人の請求を棄却した第一審には、尋問個所につき控訴人を欺いた行為、違法な控訴人本人尋問主尋問を組織した行為、判決作成時点に至って一方的に争点を変更した行為など審訴訟手続上の法令違反が確認される上、第一審判決は、本件行為1~9各行為につき、またパワハラの長期にわたる継続性と大規模な組織性及び安全配慮義務違反に関して、判断遺脱、経験則違反、論理則違反、採証法則違反、弁論主義違反、自由心証主義違反、法令解釈適用を誤った違法等、夥しい法令違反を犯している。
(2)原判決(控訴審判決)
「補正」部分を除いて第一審判決を「引用」するとして上告人の控訴を棄却するとした原判決は、「補正」の名のもとに第一審判決を大幅に書き換えながら、夥しい判断遺脱他の法令違反を犯す第一審判決を変更あるいは破棄することなく上告人の控訴を棄却することにより、第一審判決の誤謬を是正することを拒否するとともに、上告人の利益を救済することをも拒否し、これにより上訴制度の根幹を危機に瀕せしめる憲法違反を犯すのみならず、夥しい数の判断遺脱の法令違反を犯し、とりわけ本件各行為の発生状況や文脈及び諸様態に関わる具体的事実及びそれらに関する上告人の主張につき全く検討していないことから、理由不備や理由齟齬を犯すものである。
3 上告人の主張の骨子
(1)憲法違反(上告理由1~3)
上告人によって指摘された第一審判決における夥しい判断遺脱及びその他の法令違反につき審理判断し当該判決を変更・破棄することなく、判断遺脱部分をことごとく補うと同時に法令違反部分を書き換えることにより別の判決を捏造し第一審判決に違法なしとし、上告人の控訴を棄却した原判決は、上訴制度の目的である誤謬の是正と当事者の利益救済を拒否した点で、上訴制度の根幹を危機に瀕せしめた点において、そして公正手続請求権を侵害した点においても、憲法32条に違反する憲法違反を犯している(上告理由1)。上訴制度が正常に機能する範囲内では、第一審判決に判断遺脱他の違法があれば控訴審はそれにつき審理判断し、違法である場合には判決を変更して当時者の利益を救済するのが通常であるところ、原判決にあっては、第一審判決の夥しい判断遺脱部分を補い、他の法令違反部分を全面的に書き換え、それにより第一審判決を修正し別の判決に仕立て上げ、上告人の控訴を棄却し、上告人の利益救済を拒否したのであるから、これにより上告人は自身の利益が救済される機会を失ったことになり、控訴人が通常享受する権利を侵害されるという不平等を被ったことになる。上告人の利益救済を拒否した原判決は、法の下の平等を定め平等権を保障する憲法14条1項に違反する憲法違反を犯している(上告理由2)。第一審判決の夥しい判断遺脱部分及びその他の法令違反部分につき審理判断することなく、これらを補うことにより、あるいは経験則違反等の法令違反を指摘された判示を全面的に書き換えることにより、当該判決を全く別の判決に書き換え、これを法令違反なきものとみなし、上告人の控訴を棄却する原判決の行為は、上訴制度を根本的に破壊する前代未聞の不祥事というべきであり、原判決が「裁判が法に基づき公正中立に行われることを保障」した憲法76条3項に違反する憲法違反を犯していることは明らかである(上告理由3)。
(2)理由不備及び理由齟齬(上告理由4~7)
原判決は、上告人の具体的な主張や具体的事実につき全く検討していないため、原判決には具体的な理由が完全に欠如している。確かに、原判決が不当にも「引用」するとしている第一審判決には具体的な理由が欠如していないが、後述の通り、上告人は第一審判決のすべての判示につき、判断遺脱、経験則違反、論理則違反、採証法則違反、弁論主義違反、自由心証主義違反、法令解釈適用を誤った違法等、判決結果に影響を及ぼす夥しい法令違反があることを原審において主張しているにもかかわらず(控訴理由書第2章参照)、原判決は、第一審判決のこれらすべての法令違反に関する上告人の主張につき、一切審理判断していない。原判決における「引用」部分以外の事実や上告人の主張に関する認定判断及びパワハラや不法行為の有無に関する審理判断においても、原判決は、上告人の具体的主張や具体的事実につき一切検討せず、それらについての判断を全く示していないのであるから、原判決は、「引用」部分においても、それ以外の部分においても、具体的な理由を全く欠いたものであると言え、原判決に、民訴法312条2項6号に掲げる絶対的上告理由としての理由の不備があることは疑い得ない(上告理由4)。
以上に加え、とりわけパワハラや不法行為の有無に関する原判決の審理判断の著しい特徴として、パワハラや不法行為の有無に関する判断において、原判決は、パワハラ行為の発生した状況や文脈及びパワハラ行為の程度、継続期間、頻度、反復性等の様態に関わる重要な具体的事実につき、一切審理判断していない。つまり、原判決の判断枠組みは、パワハラ行為の不法行為性を検討するにあたって考慮することが必要不可欠である、社会通念や業務上の常識をも包含するパワハラ行為発生の状況や文脈及びパワハラ行為の程度、継続期間、頻度、反復性等の様態に関わる重要な具体的事実の検討を全く欠いたまま、業務上の合理性及び必要性があるかどうか、社会通念に照らして許容されるかどうか等について結論を出すというものであり、かような誤った判断枠組みを用いてパワハラの有無が問題になる本件各行為について判決結果を導く原判決には、理由の本質的部分が欠けていると考えざるを得ない。したがって、原判決には、判決主文を導き出すための理由の一部が欠けていると言わざるを得ず、民訴法312条2項6号に掲げる絶対的上告理由としての理由の不備があると言わざるを得ない(上告理由5)。
さらに、原判決が上告人の精神的苦痛及び精神的損害等につき一切審理判断していないことを鑑みれば、本件行為1~9の不法行為性につき判断するにあたって上告人の精神的苦痛を全く考慮しないことから、原判決が論理的に完結しているとは言えず、判決主文を導き出すための理由の一部が欠けていると言わざるを得ず、原判決に、民訴法312条2項6号に掲げる絶対的上告理由としての理由の不備があることは明白である(上告理由6)
また、第一審判決を「引用」するとしながら「補正」の名のもとに第一審判決を大幅に書き換えた上で、上告人の請求を排斥した原判決の理由づけには論理的矛盾があり、したがって、原判決には理由の食違いがあると言え、民訴法312条2項6号に掲げる絶対的上告理由としての理由齟齬がある(上告理由7)。
第2 憲法32条違反、憲法14条1項違反及び憲法76条3項違反(上告理由1、上告理由2及び上告理由3)
1 原判決による第一審判決の不当な書き換え
第一審判決「(別紙)「パワーハラスメント行為一覧表」本件行為1~9(原告の主張)」欄に、第一審弁論の全過程ならびに陳述書において上告人によってなされた主張の遺脱が確認された。上告人は、控訴理由書第2章第2・2(控訴理由書50頁)において、当該主張につき全く審理判断せずなされた第一審判決に判決の結論に影響を及ぼすおそれのある判断遺脱、審理不尽、理由不備の違法があることを主張した。
原判決は、「補正」と称して、上告人によって数多くの判断遺脱等を指摘された第一審判決(別紙)「パワーハラスメント行為一覧表」本件行為1~9(原告の主張)欄に、上告人が遺脱された主張として控訴審で指摘した諸事項(控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」37~50頁)を、書き加えた上(原判決第2・2、2~6頁)、第一審「事実及び理由」「第3当裁判所の判断」欄の本件行為1に関する判示(第一審判決第3、1(1)イ、10頁)を全面的に書き換えた(原判決第3、1(1)、10頁)。原判決による第一審判決への当該追加部分は、原審において上告人が第一審判決によって遺脱されているとした上告人の第一審弁論における主張に相当し、また第一審判決の全面的書き換え部分は、原審において上告人によって判断遺脱、経験則違反、論理則違反、自由心証主義違反等の法令違反を指摘された判示である。上告人はこの遺脱を根拠に第一審判決による判断遺脱等の法令違反を指摘している。そうすると、当該追加部分は、判決に影響を及ぼす重要事項に相当し、「補正」が通常、誤字や数字の間違い等小さな間違い等に関わるものであることを鑑みれば、このような重要事項を「補正」と称して第一審に書き加えることは、本来あってはならないことである。また、上告人が原審において法令違反を指摘した第一審の判示を原判決が書き換え、指摘された法令違反をなくすことも言うまでもなく決してあってはならないことである。原判決のやるべきは、上告人が第一審判決において遺脱されたと主張する上告人の第一審弁論における主張につき、また上告人が原審において法令違反を指摘した第一審の判示につき、それらが法令違反を生じさせるものであるかを審理判断することであった。しかるに、原判決は、第一審による判断遺脱等の違法の有無について全く審理判断することなく、上告人が第一審判決において遺脱されたと主張する上告人の第一審弁論における主張を第一審判決(別紙)「パワーハラスメント行為一覧表」本件行為1~9(原告の主張)欄に書き加え、また第一審「事実及び理由」「第3当裁判所の判断」欄の本件行為1に関する判示を全面的に書き換え、それにより第一審判決を上告人が控訴審で指摘した第一審判決における上告人の主張の遺脱部分または法令違反部分をほとんどなくした別の判決へと大きく改変し、第一審に違法なしとして上告人の控訴を棄却したのであるから、原判決によるこの書き換え操作は極めて不正なものであり、重篤な法令違反及び憲法違反たるを免れ得ない。
以下に、原判決による第一審判決「(別紙)「パワーハラスメント行為一覧表」本件行為1~9(原告の主張)」欄への追加部分、及び原判決によって全面的に書き換えられた第一審「第3当裁判所の判断」欄の本件行為1に関する判示を指摘し、それらが極めて悪質な法令違反及び憲法違反を構成するものであることを主張する。
(1)本件行為1について
ア 原判決による第一審「(原告の主張)」欄への追加部分1
「履修者数の多寡は、中国語及びドイツ語の契約制講師採用の正当な理由にはなり得ないものであるし、大学全体の収容定員に応じ定める教員数の配分を事実上変更することは法令違反であり、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであることは明らかである。
また、被控訴人においては、フランス語の教員枠に対する対応が一貫していないのであって、控訴人を仲間外しにし、控訴人をおとしめる悪意があるのみであった。フランス語教員枠の政治学教員枠への転用は、控訴人に精神的苦痛を与えるとともに、控訴人を孤立させることを目的とするものであった。」(原判決3頁)
イ 上告人が控訴審で指摘した第一審判決における上告人の主張の遺脱部分1
(ア)上記アの追加部分のうち、「履修者数の多寡は、中国語及びドイツ語の契約制講師採用の正当な理由にはなり得ないものである」という部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(1)「遺脱された主張1」の下線部分の引用である(下線は引用者による)。
「控訴人は、「平成27年度第1回語学委員会書面会議について」に「語学委員会の答申(案)」として、「現況に鑑み、選択者数の多い中国語とドイツ語でそれぞれ契約制講師を採用する」とある事実から、語学委員会で検討する以前に、原告に全く無断で中国語・ドイツ語の契約制講師採用が事実上決定されていることを確認した上で、フランス語履修者数増が全くない時にフランス語教員を採用した事実があることから、履修者数の多寡は中国語及びドイツ語契約制講師採用の正当な理由とはなり得ず、この決定が原告へのハラスメント目的のものであることを主張した。(準備書面5、7頁)」(控訴理由書37~38頁)
(イ)上記アの追加部分のうち、「大学全体の収容定員に応じ定める教員数の配分を事実上変更することは法令違反であり、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであることは明らかである」という部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(1)「遺脱された主張2」の下線部分の若干の変更を加えた引用である(下線は引用者による)。
「控訴人は、大学全体の収容定員に応じ定める教員数の配分を事実上変更することが大学設置基準第13条に違反する法令違反である事実をまず確認し、法令違反である決定あるいは「裁量」がいかなる合理性をも欠いた「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」であることが明白であることから、フランス語教員枠の政治学教員枠への転用が「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」であることを主張した。(準備書面5、4頁~5頁)」(控訴理由書38頁)
(ウ)上記アの追加部分のうち、「被控訴人においては、フランス語の教員枠に対する対応が一貫していないのであって、控訴人を仲間外しにし、控訴人をおとしめる悪意があるのみであった。」という部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(1)「遺脱された主張3」の下線部分の若干の変更を加えた引用である(下線は引用者による)。
「まず被控訴人東洋大学が、2008~9年に一人であったフランス語専任教員を*****を雇うことによって二人にし、***を重んずることによって控訴人を法学部フランス語運営から排除し、次いで2015~6年に二人いたフランス語専任教員を控訴人一人にすることによってフランス語劣遇措置がそのまま控訴人へのハラスメントになるような状況を作り、最後に2022~3年に法学部フランス語非常勤講師を3人増員することによって控訴人から授業を奪ったという事実がある。この過程を通して、法学部フランス語教員の増減はフランス語履修者数の増減と一切相関関係はない。つまり、被控訴人は、ある時は法学部フランス語教員枠二人を尊重しフランス語教員を雇い、ある時はフランス語教員枠を事実上減らしフランス語教員を採用しないようにしており、フランス語教員枠の被控訴人による扱いは全く首尾一貫していない。首尾一貫しているのは、フランス語教員を増やす時も増やさない時も控訴人を貶める悪意(故意あるいは過失)のみである。同様に被控訴人は、フランス語教員枠の政治学教員枠への転用に際してフランス語履修者減を理由とするが、他方でフランス語履修者の増減に関係なくフランス語教員を増やしている。そして、いずれの場合にも控訴人を無視し仲間外しし控訴人の尊厳を傷つける故意過失のみが一貫して確認される。(準備書面5、6頁~7頁、陳述書、6頁~7頁)」(控訴理由書38~39頁)
(エ)上記アの追加部分のうち、「フランス語教員枠の政治学教員枠への転用は、控訴人に精神的苦痛を与えるとともに、控訴人を孤立させることを目的とするものであった。」という部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(1)「遺脱された主張4」の下線部分の若干の変更を加えた引用である(下線は引用者による)。
「フランス語教員枠の政治学教員枠への転用は、控訴人の意見を全く聞くことなく転用を決めた無視と仲間外しによって控訴人に精神的苦痛を与えると同時に、法学部フランス語専任教員だけを控訴人一人にすることによって、既に法学部内で仲間外しに遭っていた控訴人をさらに孤立させ、控訴人の発言力を奪いその立場を弱く不利なものとすると同時に、フランス語劣遇措置を容易にすることによってフランス語劣遇が法学部唯一のフランス語専任教員である控訴人へのハラスメントになることを目的とした悪意によるハラスメントである。(準備書面5、3頁、5頁、陳述書、6頁)」(控訴理由書39頁)
ウ 原判決による第一審「(原告の主張)」欄への追加部分2
「同頁1 2行目の、「本件行為1は」の次に「、パワハラの定義に照らし」を、同1 3行目の「原告に対する」の次に「悪意による」を、それぞれ加える。」(原判決3頁)
エ 上告人が控訴審で指摘した第一審判決における上告人の主張の遺脱部分2
上記(ウ)の追加部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(1)「遺脱された主張5」を参照し踏まえたものである。
「控訴人は、準備書面5において、パワハラ6類型、パワハラ3要件、「学校法人東洋大学ハラスメントの防止等に関する規程」に定める「パワー・ハラスメント」定義を援用しながら、本件行為1がパワハラであることを主張し(5頁~6頁)、また本件行為1が悪意による不法行為であることを主張している。(7頁)」(控訴理由書39頁)
オ 原判決による第一審「当裁判所の判断」欄の修正部分
「原判決9頁10行目の「本件訴訟」の次に「に係る訴え」を、同頁23行目の「この点」の次に「について」を、それぞれ加え、同10頁5行目冒頭から12行目末尾までを次のとおり改める。
また、控訴人は、本件行為1が大学設置基準に違反するものであって、職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、業務上の合理性及び必要性が全くなく、社会通念に照らして許容される範囲を超える等との主張をするが、上記アにおいて認定をした諸事情に照らし、本件行為1が職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、業務上の合理性及び必要性を欠くとも、社会通念に照らして許容される範囲を超えるとも認めることはできない。」(原判決「第3当裁判所の判断」1(1)、10頁)
カ 上記判示は、次に引用する第一審判決の判示を「補正」の名のもとに全面的に書き換えたものである。
「なお、原告は、教授会の決定が仮にあったとしても、大学設置基準13条に違反するものであり、許されない旨主張するが、大学設置基準は、大学に置く教員数の基準を定めたにすぎず、ある教員が退任した後にその教員分の枠についてどのように配分するかは、基準に反しない限り大学の合理的裁量により定められるものであると解されるから、原告の上記主張はそもそも失当であるし、大学設置基準に違反する教員の採用がされたからといって原告の権利、利益が害されるともいえないのであるから、結局のところ原告の上記主張は主張自体失当といわざるを得ない。」(第一審判決10頁)
上記第一審判決の判示につき、上告人は、控訴理由書第2章第4、1(3)イ及び(4)イにおいて、判断遺脱、経験則違反、論理則違反、自由心証主義違反等の法令違反があることを主張している。以下に控訴理由書の当該部分を引用する。
「イ 判示の違法性
(ア)上記判示は、控訴人が弁論の過程において既に論駁した被控訴人の主張を(準備書面5,5頁)、弁論における当該議論につき何ら審理判断せず採用し、控訴人の主張を排斥したものであり、審理不備、理由不尽、判断遺脱の違法及び自由心証主義違反の違法を犯していると言うほかはない。
(イ)「大学設置基準は、大学に置く教員数の基準を定めたにすぎず」という表現が極めて不正確である上に、「ある教員が退任した後にその教員分の枠についてどのように配分するかは、基準に反しない限り大学の合理的裁量により定められるものである」という判示は、「ある教員が退任した後にその教員分の枠について」の配分の仕方が本件行為1にあって基準に反することは、第3,2,(1)エ(ア)、(イ)に前述した通り、大学設置基準第13条に定める別表第二枠と別表第一枠それぞれに属する教員数の配分を変えることが法令違反であることから、明白であるから、不合理であると言うほかはなく、審理不備、理由不尽、判断遺脱の違法を犯している。
(ウ)原審は「ある教員が退任した後にその教員分の枠についてどのように配分するかは、基準に反しない限り大学の合理的裁量により定められる」と判示するが、本件行為1が大学設置基準第13条に反する法令違反を犯している以上、本件行為に関して「合理的裁量」が存在しないことは疑い得ない。」(控訴理由書71頁)
「 イ 判示の違法性
(ア)控訴人は、法令違反である決定が明白に業務上のいかなる必要性をももたない「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」であることを主張している。本件行為1が大学設置基準第13条違反である事実がそれ自体直接に控訴人の権利や利益を害するものであるとは主張していない。
(イ)本件行為1が大学設置基準第13条違反である事実がそれ自体直接に控訴人の権利や利益を害するものではないという前提から、「被告が、フランス語教員枠を政治学教員枠に転用したことが、原告のフランス語教員としての人格権を侵害するものとは認められない」という結論は全く帰結し得ず、このように推認する判断が、誤った経験則を採用している上に、控訴人の人格権侵害の他のあらゆる可能な原因を無視し排除している点において論理的に失当であることから、控訴人の主張を排斥する当該判示の審理判断には、経験則違反及び論理則違反の違法がある。」(控訴理由書72頁)
原判決が本来なすべきは、控訴理由書において上告人が主張する判断遺脱、経験則違反、論理則違反、自由心証主義違反等の法令違反の第一審判決における有無について審理判断することである。しかるに、原判決はこれを一切しなかったのであるから、原判決に判断遺脱の法令違反があることは明白である。のみならず、原判決は、法令違犯の有無につき検討し、法令違反があった場合には第一審判決を棄却するという本来なされるべきことをすることなく、その代わりに、第一審判決の当該判示を全面的に書き直し、違法部分を消去してしまったのであるから、原判決がこの極めて不正な操作により重篤な法令違反及び憲法違反を犯していることは明白である。
上記に加え、原判決上記判示の「職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、業務上の合理性及び必要性が全くなく、社会通念に照らして許容される範囲を超える等との主張をする」という部分は、原判決が摘示した原審における上告人の主張である(原判決第2、3「当審における控訴人の主張(補足の主張)」(2)ア、6頁))。つまり、原判決は、第一審判決時点では存在しなかった原審における上告人の主張を用いて第一審判決を書き換えたのであり、原判決はその意味でも極めて悪質な法令違反及び憲法違反を犯していると言えるのである。
(2)本件行為2について
ア 原判決による第一審「(原告の主張)」欄への追加部分1
「原稿に問題があるのであれば、それを無視するのではなく、作成者に連絡をするのが常識であるから、これを無視することは、業務上必要かつ相当な範囲を超えているのであるが、**らは、控訴人を苦しめるため、悪意をもって、このような控訴人を無視するとの手段を選択した。また、控訴人に何らの相談もせずに控訴人の原稿を採用しなかったことは、控訴人の授業を妨害し、その就労に不利益を与えて就労環境に悪影響を及ぼすものである。控訴人は、被控訴人において徹底的に誹謗中傷されていたから、控訴人の原稿を無視するという常識に反する対応も許されてしまっていた。」(原判決3頁)
イ 上告人が控訴審で指摘した第一審判決における上告人の主張の遺脱部分1
(ア)上記アの追加部分のうち、「原稿に問題があるのであれば、それを無視するのではなく、作成者に連絡をするのが常識であるから、これを無視することは、業務上必要かつ相当な範囲を超えているのである」という部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(2)「遺脱された主張1」の下線部分の変更を加えた引用である(下線は引用者による)。
「原稿に問題があれば、その原稿を無視するのでなく作成者に連絡するのが常識であるところ、これを無視する行為は、それが人に原稿を頼む際の常識に反し、合理性を欠いた判断に基づく業務上の必要性がなく業務遂行上の手段として不適当な行為であることから業務上必要かつ相当な範囲を超えたものである。(準備書面5、10頁~11頁)」(控訴理由書39頁)
(イ)上記アの追加部分のうち、「**らは、控訴人を苦しめるため、悪意をもって、このような控訴人を無視するとの手段を選択した」という部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(2)「遺脱された主張2」の下線部分の変更を加えた引用である(下線は引用者による)。
「**学部長らは、原稿作成者の原稿を無視するという他の教職員に対しては絶対にしない通常の業務を逸脱した対応を、人間関係から切り離され孤立した状態にある控訴人に対して、控訴人に連絡する、字数を増やす等、可能ないくつかの選択肢のなかから控訴人を苦しめようという悪意をもって選択した。(準備書面5、10頁、陳述書、7頁)」(控訴理由書40頁)
(ウ)上記アの追加部分のうち、「また、控訴人に何らの相談もせずに控訴人の原稿を採用しなかったことは、控訴人の授業を妨害し、その就労に不利益を与えて就労環境に悪影響を及ぼすものである。」という部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(2)「遺脱された主張3」の下線部分の変更を加えた引用である(下線は引用者による)。
「控訴人に何らの相談もせず控訴人の原稿を採用しなかったことにより控訴人の授業計画が学生に正確に伝達されないと同時に、控訴人は伝達されたと勘違いして授業することになるため、控訴人の授業についての双方の理解の間に齟齬が生じ、原告の授業運営がスムーズに行かなくなる。したがって、被控訴人の行為は控訴人の授業を妨害することであり、控訴人の就労における不利益を与え、就労環境に悪影響を及ぼすものである。(準備書面5、10頁~11頁)」(控訴理由書40頁)
(エ)上記アの追加部分のうち、「控訴人は、被控訴人において徹底的に誹謗中傷されていたから、控訴人の原稿を無視するという常識に反する対応も許されてしまっていた」という部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(2)「遺脱された主張4」の下線部分の変更を加えた引用である(下線は引用者による)。
「控訴人の場合は、**教授の画策により徹底的に誹謗中傷され、法学部の中でほぼ人間関係から切り離された、味方のいない状態でいるので、原稿を無視するというような常識に反した失礼な対応も許される存在になっていた。(陳述書、7頁)」(控訴理由書40頁)
ウ 原判決による第一審「(原告の主張)」欄への追加部分2
「同頁22行目の「本件行為2は」の次に「、パワハラの定義に照らし」を、同24行目の「原告に対する」の次に「悪意による」を、それぞれ加える。」(原判決3頁)
エ 上告人が控訴審で指摘した第一審判決における上告人の主張の遺脱部分2
上記(ウ)の追加部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(2)、「遺脱された主張5」を参照し踏まえたものである。
「控訴人は、準備書面5において、パワハラ6類型、パワハラ3要件、「学校法人東洋大学ハラスメントの防止等に関する規程」に定める「パワー・ハラスメント」定義を援用しながら、本件行為2がパワハラであることを主張し(11頁)、また本件行為2が悪意による不法行為であることを主張している。(10頁)」(控訴理由書40頁)
(3)本件行為3について
ア 原判決による第一審「(原告の主張)」欄への追加部分
「同36頁1 6行目末尾に「これは、控訴人が孤立し味方のいない弱い立場にあるからであって、業務上の必要性はないし、業務遂行上の手段として不適当なものでもあった。」を、同1 8行目の「である。」の次に「これは、複数の悪意あるフランス語劣後措置の一つであり、他のものと同様に、控訴人に対する悪意あるハラスメントであった。」を、同18行目の「本件行為3は」の次に「、パワハラの定義に照らし」を、同20行目の「原告に対する」の次に「悪意による」を、それぞれ加える。」(原判決3~4頁)
イ 上告人が控訴審で指摘した第一審判決における上告人の主張の遺脱部分
(ア)上記アの追加部分のうち、「これは、控訴人が孤立し味方のいない弱い立場にあるからであって、業務上の必要性はないし、業務遂行上の手段として不適当なものでもあった」という部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(3)「遺脱された主張1」の下線部分の若干の変更を加えた引用である(下線は引用者による)。
「履修者数の点でフランス語と競合するドイツ語の宣伝だけを法学部HPに載せたことについて、そのような語学宣伝の場があることを法学部が私に教えなかったこと、フランス語とドイツ語間のこの不平等状態が2016年からほぼ5年間続いていた期間法学部の誰も私にそのような場があることを私に教えなかったことは、孤立し味方のいない弱い立場に立たされた私だけになされたことであり、業務上の必要性がなく、それが業務遂行上の手段として不適当な行為であり、しかも不平等状態の続いた期間が社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであることから業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであり、私に対する悪意なくしては考えられない。(準備書面5、12頁、陳述書、7頁)」(控訴理由書40~41頁)
(イ)上記アの追加部分のうち、「これは、複数の悪意あるフランス語劣後措置の一つであり、他のものと同様に、控訴人に対する悪意あるハラスメントであった」という部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(3)「遺脱された主張2」の下線部分の変更を加えた引用である(下線は引用者による)。
「**教授が法学部を始め学内に控訴人について誹謗中傷をし、控訴人が孤立し法学部内で徹底した仲間外しに遭っている状況で、しかも**教授の悪意のもと他に複数の悪意あるフランス語劣遇措置がとられている中、このハラスメントだけが悪意ない偶然のものであったとは考えられない。」(控訴理由書41頁)
(ウ)上記アの追加部分のうち、「同18行目の「本件行為3は」の次に「、パワハラの定義に照らし」を、同20行目の「原告に対する」の次に「悪意による」を、それぞれ加える」という部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(3)、「遺脱された主張3」を参照し踏まえたものである。
「控訴人は、準備書面5において、パワハラ6類型、パワハラ3要件、「学校法人東洋大学ハラスメントの防止等に関する規程」に定める「パワー・ハラスメント」定義を援用しながら、本件行為3がパワハラであることを主張し(12頁)、また準備書面2において本件行為3が悪意による不法行為であることを主張している。(6頁)」(控訴理由書41頁)
(4)本件行為4について
ア 原判決による第一審「(原告の主張)」欄への追加部分1
「このようなことは、控訴人以外の教員では起こり得ないのであって、被控訴人において、控訴人以外の語学教員には、平成23年の「教養演習開講方針」に従わなくていいことを伝え、控訴人のみがこれに従うようにしたからこそ生じたものにほかならない。被控訴人は、「教養演習開講について」との学部長文書をもって、過去のハラスメントを明文化して正当化するとともに、控訴人が過去に担当した教養演習より厳しい条件を課すことで、控訴人が教養演習を再開講することをあきらめさせようとしたものである。
これに対し、被控訴人は、控訴人に不利益を与えるため、ある時は6コマの授業が必要とし、ある時は5コマの授業でもよいとの恣意的な主張をするにすぎない。」(原判決4頁)
イ 上告人が控訴審で指摘した第一審判決における上告人の主張の遺脱部分1
(ア)上記アの追加部分のうち、「このようなことは、控訴人以外の教員では起こり得ない」という部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(4)「遺脱された主張1」の下線部分の変更を加えた引用である(下線は引用者による)。
「法学部の大半の語学教員が教養演習を開講している中で控訴人だけが開講していないという異常な事態が10年間以上も誰にも批判もされずに放置され維持されているという状況自体が孤立し味方のいない私以外の教員には起こり得ない、通常の大学業務の範囲を超えるものである。このような状況は、偶然には維持され得ず、完全に排除され一人前の教員扱いしなくてもよいとされた私を通常の業務範囲を逸脱してでも苦しめようとする法学部教職員らの悪意によるものである。(準備書面5、15頁、陳述書、3頁)(控訴理由書41頁)
(イ)上記アの追加部分のうち、「被控訴人において、控訴人以外の語学教員には、平成23年の「教養演習開講方針」に従わなくていいことを伝え、控訴人のみがこれに従うようにしたからこそ生じたものにほかならない。」という部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(4)「遺脱された主張2」の下線部分の変更を加えた引用である(下線は引用者による)。
「2011年の「教養演習開講方針」には、教養演習開講の必要条件として履修者10名以上語学科目6コマ+教養演習1コマ計7コマが定められているが、2011年以後10年以上にもわたって控訴人以外のほぼすべての語学教員らによる数多くの教養演習やセミナーがこの条件を満たさないまま開講されている。このような状況は、**法学部長らが、控訴人以外の語学教員には「教養演習開講方針」に従わなくていいことを伝え、それによって控訴人だけがこれに従うようにし向けたということがなければ起こり得ない。したがって、「教養演習開講方針」が控訴人の教養演習開講を妨げようという悪意によって作成されたものであり、上述の状況は、控訴人を差別し、控訴人だけを不利益に陥れようという悪意によって実現されたものである。(準備書面4、9頁~10頁、陳述書、3頁~4頁)」(控訴理由書42頁)
(ウ)上記アの追加部分のうち、「被控訴人は、「教養演習開講について」との学部長文書をもって、過去のハラスメントを明文化して正当化するとともに、控訴人が過去に担当した教養演習より厳しい条件を課すことで、控訴人が教養演習を再開講することをあきらめさせようとしたものである」という部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(4)「遺脱された主張4」の下線部分の変更を加えた引用である(下線は引用者による)。
「「教養演習開講方針」を記載した「教養演習開講について」という学部長文書は、語学科目5コマ+教養演習1コマ計6コマで控訴人が担当していた教養演習をつぶすという2007年のハラスメントをそのための口実を明文化して正当化すると同時に、控訴人が二年間担当した教養演習より厳しい条件を原告に課すことによって、2007年以来開講されていなかった教養演習を復活させるにあたって、原告に教養演習を再開講することをあきらめさせ、これを妨げることを目的としたものである。(準備書面4、10頁、控訴人本人調書、18頁)」(控訴理由書42頁)
(エ)上記アの追加部分のうち、「これに対し、被控訴人は、控訴人に不利益を与えるため、ある時は6コマの授業が必要とし、ある時は5コマの授業でもよいとの恣意的な主張をするにすぎない」という部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(4)「遺脱された主張3」の下線部分の変更を加えた引用である(下線は引用者による)。
「被控訴人が第3準備書面で2023年度の控訴人の担当コマ数を4コマにしたことを不当に正当化するために5コマでよいと主張している事実から、被控訴人が控訴人に対して悪意をもってハラスメントを犯すために、控訴人を不利益に貶めたり苦しめたりする限りにおいて、ある時は6コマ必要と主張し、ある時は5コマでよいと主張しているだけであることが帰結する。(準備書面4、8頁、陳述書、4頁)」(控訴理由書42頁)
ウ 原判決による第一審「(原告の主張)」欄への追加部分2
「同頁24行目の「本件行為4は」の次に「、パワハラの定義に照らし」を加え、同3 9頁3行目の「、不法行為」を「及び悪意による不法行為」に改める。」(原判決4頁)
エ 上告人が控訴審で指摘した第一審判決における上告人の主張の遺脱部分2
上記ウの追加部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(4)、「遺脱された主張5」を参照し踏まえたものである。
「控訴人は、準備書面5において、パワハラ6類型、パワハラ3要件、「学校法人東洋大学ハラスメントの防止等に関する規程」に定める「パワー・ハラスメント」定義を援用しながら、本件行為4がパワハラであることを主張し(15頁)、また本件行為4が悪意による不法行為であることを主張している。(16頁)」(控訴理由書43頁)
(5)本件行為5について
ア 原判決による第一審「(原告の主張)」欄への追加部分
「同頁14行目の「なかった。」の次に「このようなことは、通常の大学業務の範囲内では起こり得ないものであり、偶然とは考え難い上、業務上の必要性はなく、業務遂行上の手段として不適当でもある。また、法学部が悪意をもって、控訴人の評価を不当におとしめるものでもある。」を加え、同14行目の「これは」を「以上のとおり」に改め、同1 6行目から1 7行目までにかけての「本件行為5は」の次に「、パワハラの定義に照らし」を、同1 9行目の「及び」の次に「悪意による」を、それぞれ加える。」(原判決4頁)
イ 上告人が控訴審で指摘した第一審判決における上告人の主張の遺脱部分
(ア)上記アの追加部分のうち、「このようなことは、通常の大学業務の範囲内では起こり得ないものであり、偶然とは考え難い上、業務上の必要性はなく、業務遂行上の手段として不適当でもある。」という部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(5)「遺脱された主張1」の下線部分の変更を加えた引用である(下線は引用者による)。
「法学部のほとんどすべての専任教員が「長」のつく何らかの役職を経験している中、控訴人にだけ20年以上も何らの役職にもつかせないということは、通常の大学業務の範囲内では起こり得ないものであり、控訴人のみに対するそのような劣遇に何ら業務上の必要性がなく、それが業務遂行上の手段として不適当な行為であり、しかも当該行為の継続期間が社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであることから業務上必要かつ相当な範囲を超えたものである。(準備書面5、17頁、陳述書、9頁)」(控訴理由書43頁)
(イ)上記アの追加部分のうち、「また、法学部が悪意をもって、控訴人の評価を不当におとしめるものでもある」という部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(5)「遺脱された主張2」の下線部分の変更を加えた引用である(下線は引用者による)。
「ほとんどの法学部教員が何らかの役職を与えられるなか原告にのみ20年以上の間何らの役職をも与えなかった行為は、これを偶然のものであると考えることはできず、被控訴人の悪意によるものと考えるほかはない。(準備書面5、17頁~18頁、陳述書、9頁)」(控訴理由書43頁)
(ウ)上記アの追加部分のうち、「同1 6行目から17行目までにかけての「本件行為5は」の次に「、パワハラの定義に照らし」を、同1 9行目の「及び」の次に「悪意による」を、それぞれ加える」という部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(5)、「遺脱された主張5」を参照し踏まえたものである。
「控訴人は、準備書面5において、パワハラ6類型、パワハラ3要件、「学校法人東洋大学ハラスメントの防止等に関する規程」に定める「パワー・ハラスメント」定義を援用しながら、本件行為5がパワハラであることを主張し(16頁)、また本件行為5が悪意による不法行為であることを主張している。(17頁~18頁)」(控訴理由書44頁)
(6)本件行為6について
ア 原判決による第一審「(原告の主張)」欄への追加部分
「同42頁24行目の末尾に「主査である控訴人の所見を副査の所見よりも下位に置き、審査結果報告書にも控訴人の所見を全く掲載せず、反映もさせないことは、業務上の必要性を欠き、業務遂行上不適当な行為であって、控訴人には何をしてもよいという法学部内の共通の了解の下、明白な悪意によりされたものである。」を加え、同頁2 5行目の「本件行為6は」の次に「、パワハラの定義に照らし」を、同43頁2行目の「及び」の次に「悪意による」を、それぞれ加える。」(原判決5頁)
イ 上告人が控訴審で指摘した第一審判決における上告人の主張の遺脱部分
(ア)上記アの追加部分のうち、「主査である控訴人の所見を副査の所見よりも下位に置き、審査結果報告書にも控訴人の所見を全く掲載せず、反映もさせないことは、業務上の必要性を欠き、」という部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(6)「遺脱された主張1」の下線部分の変更を加えた引用である(下線は引用者による)。
「常勤講師採用審査にあたって、控訴人を主査にしたのであれば、主査に主要役割を副査に副次的役割を負わせ、副査の見解を審査結果報告書に反映させ掲載したのであれば、主査についてはより多く反映・掲載するのが通常の大学業務で行われることである。したがって、主査である控訴人の所見を副査のそれより下位に置いたり、審査結果報告書に全く掲載もせず反映もさせないことには、何ら業務上の必要性はなく、それが業務遂行上の手段として不適当な行為であることから、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものである。(準備書面5、24頁、陳述書、8頁)」(控訴理由書44頁)
(イ)上記アの追加部分のうち、「業務遂行上不適当な行為であって、控訴人には何をしてもよいという法学部内の共通の了解の下、明白な悪意によりされたものである」という部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(6)「遺脱された主張2」の下線部分の変更を加えた引用である(下線は引用者による)。
「****学部長らは、副査の見解は踏まえながら主査である控訴人の見解は審査結果報告書に全く反映させないという控訴人以外の他の教員には決してなされない通常の業務を逸脱したことをした。これは、徹底した仲間外しによって法学部内にあるいは大学全体に孤立し味方のいない控訴人にだけは何をやっても大丈夫という共通の了解が出来上がっており、その共通の了解を前提として通常の業務範囲を超えてでも私の精神を傷つけるようとしてなされたことであり、明白に悪意によるものである。(準備書面5、23頁、陳述書、8頁)」(控訴理由書44頁)
(ウ)上記アの追加部分のうち、「同頁2 5行目の「本件行為6は」の次に「、パワハラの定義に照らし」を、同43頁2行目の「及び」の次に「悪意による」を、それぞれ加える」という部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(6)、「遺脱された主張3」を参照し踏まえたものである。
「同頁2 5行目の「本件行為6は」の次に「、パワハラの定義に照らし」を、同43頁2行目の「及び」の次に「悪意による」を、それぞれ加える。」(控訴理由書45頁)
(7)本件行為7について
ア 原判決による第一審「(原告の主張)」欄への追加部分1
「同44頁1 6行目末尾に改行して、次のとおり加える。「 また、法学部では、教授会資料に掲載される推薦入試出向教員一覧の一番上にほかと切り離した形でほかの教員の氏名より大きな活字で控訴人の氏名を印刷した。これは、控訴人が法学部内の人間関係から隔離されていることを法学部教員らに象徴的に示すとともに、控訴人にもそれをはっきりと示して精神的苦痛を与えるためにされたものである。」」(原判決5頁)
イ 上告人が控訴審で指摘した第一審判決における上告人の主張の遺脱部分1
上記アの追加部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(7)「遺脱された主張3」の下線部分の変更を加えた引用である(下線は引用者による)。
「2007年から少なくとも2014年まで(あるいは2015年まで)の8年間(あるいは9年間)にわたって、被控訴人東洋大学法学部は、教授会資料に載る10月・11月推薦入試出向教員一覧の一番上に他から切り離した形でしかも他の教員の氏名より大きな活字で控訴人の氏名を印刷した。ちなみに控訴人の氏名は一覧表などに載る時はいつも一番下や最後に書かれるので、一番上に書かれたのはこの時だけである。
留学生日本語試験採点の日は法学部での試験監督出向は控訴人だけであり、被控訴人東洋大学法学部がこれを10年間にわたってさせたのは明らかに法学部内での控訴人の人間関係からの切り離しを狙ったものである。そして、控訴人が法学部内で人間関係から隔離され仲間外しされていることを新任教員も含めた法学部教員たちに象徴的に示すために、そして控訴人に対しても自身が仲間外しされていることをはっきり示し、これによって控訴人に精神的苦痛を与え原告の精神をさいなむために、教授会資料に挿入される、出向日ごとに入試業務担当教員を分類・区分した10月・11月推薦入試出向教員一覧表において、例えば10月19日であれば、一番上に置かれた10月19日の欄に一人だけ書かれた控訴人の氏名をことさら大きな活字で印刷し、その下の別の日にち欄に印刷された多数の法学部教員の氏名との対照を際立たせることによって、一覧表の上でも控訴人が隔離され差別されているということを示したのである。」(控訴理由書45~46頁)
ウ 原判決による第一審「(原告の主張)」欄への追加部分2
「同頁1 8行目の「ことは」の次に「、偶然とは考え難い上、業務上の必要性はなく、業務遂行上の手段として不適当なものでもあって」を、同1 9行目の
「であり」の次に「、パワハラの定義に照らし」を、それぞれ加え、同22行目の「、不法行為」を「及び悪意による不法行為」に改める。」(原判決5頁)
エ 上告人が控訴審で指摘した第一審判決における上告人の主張の遺脱部分2
(ア)上記ウの追加部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(7)「遺脱された主張1・2」の下線部分の変更を加えた引用である(下線は引用者による)。
「ほぼ10年連続で留学生日本語試験採点の仕事を東洋大学で控訴人のみに強要することに何ら業務上の必要性がなく、それが業務遂行上の手段として不適当な行為であり、10年連続という期間が社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであることから、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものである。」
「東洋大学でただ一人控訴人のみに、ほぼ10年連続で他の入試業務をほとんどさせず日本人であれば誰でもできる留学生日本語試験採点を強要する行為は、偶然にはなされ得ず、控訴人への悪意によるものであると考えるほかはない。」(控訴理由書45頁)
(イ)上記ウの追加部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(4)、「遺脱された主張4」を参照し踏まえたものである。
「控訴人は、準備書面5において、パワハラ6類型、パワハラ3要件、「学校法人東洋大学ハラスメントの防止等に関する規程」に定める「パワー・ハラスメント」定義を援用しながら、本件行為7がパワハラであることを主張し(25頁~26頁)、また本件行為7が悪意による不法行為であることを主張している。(27頁)」(控訴理由書46頁)
オ 原判決による第一審「当裁判所の判断」欄への追加部分
「また、控訴人は、控訴人が法学部内の人間関係から隔離されていることを法学部教員らに象徴的に示すとともに、控訴人にもそれをはっきりと示して精神的苦痛を与えるために、法学部では、教授会資料に掲載される推薦入試出向教員一覧の一番上にほかと切り離した形でほかの教員の氏名より大きな活字で控訴人の氏名を印刷したとの主張をする。
しかし、仮に控訴人指摘の事情を考慮したとしても、控訴人が主張をする意図を推認することはできず、控訴人の人格権等の権利を侵害するものと認めることもできないから、この点に関する控訴人の主張も採用することができない。」(原判決11頁)
カ 上記オの追加部分は、次に引用する控訴理由書第2章第3・2「本件行為1~9及びパワハラの長期にわたる継続性と大規模な組織性に関する認定事実の誤りと遺脱」(7)ウに明記された第一審判決において遺脱された事実を、第一審判決による判断遺脱等の法令違反につき全く審理判断することなく、第一審判決に挿入したものである。
(8)本件行為8について
ア 原判決による第一審「(原告の主張)」欄への追加部分1
「**及び**の行為は、極めて異常であって、業務上の必要性を欠き、業務遂行上の手段として不適当でもあった。また、控訴人を仲間外しとする悪意を認めることができるとともに、それが常態化しており、末端の教務課職員までもが自らの職分を超えて控訴人の人格を傷付けようとしたものである。さらに、**の控訴人に対する態度は、極めて敵対的で傲慢であることも、悪意をもって原稿の改ざんがされたことの証左である。」(原判決5頁)
イ 上告人が控訴審で指摘した第一審判決における上告人の主張の遺脱部分1
(ア)上記アの追加部分のうち、「**及び**の行為は、極めて異常であって、業務上の必要性を欠き、業務遂行上の手段として不適当でもあった。」という部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(8)「遺脱された主張1」の下線部分の変更を加えた引用である(下線は引用者による)。
「被控訴人法学部教務課職員が、控訴人に何ら相談もなく控訴人の原稿を修正した行為、及び、目の前にいる控訴人にわざわざ朱の入った原稿を見えるようにしておきながら、控訴人に全く相談することなく控訴人の原稿の修正点についての検討を続行しようとした行為は、いずれも控訴人も交えて検討するのが常識であり、大学業務において通常のことであることから、社会通念からして極めて異常であり、原告を無視して原告の研究計画書に手を入れ、それについての検討を原告を交えずにすることに何ら業務上の必要性がなく、それが業務遂行上の手段として不適当な行為であることから業務上必要かつ相当な範囲を超えたものである。(準備書面5、27頁~28頁、陳述書、8頁)」(控訴理由書46頁)
(イ)上記アの追加部分のうち、「また、控訴人を仲間外しとする悪意を認めることができるとともに、それが常態化しており、」という部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(8)「遺脱された主張2」の下線部分の変更を加えた引用である(下線は引用者による)。
「被控訴人法学部教務課職員が、控訴人に何ら相談もなく控訴人の原稿を修正した行為及び目の前にいる控訴人に全く相談することなく控訴人の原稿の修正点についての検討を続行しようとした行為のいずれにおいても、控訴人に相談するというごく自然な選択肢を被控訴人法学部教務課職員が敢えて採らなかったという事実に控訴人を仲間外ししようという悪意が認められる。同時に、控訴人を仲間外しすることが法学部内で常態化していたことも確認される。(準備書面5、27頁、陳述書、8頁)」(控訴理由書46~47頁)
(ウ)上記アの追加部分のうち、「末端の教務課職員までもが自らの職分を超えて控訴人の人格を傷付けようとしたものである。」という部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(8)「遺脱された主張3」の下線部分の変更を加えた引用である(下線は引用者による)。
「教員の専門的学問につき何らの見識をも有さない大学職員が教員の研究計画書に教員に無断で朱を入れた上、それにつき当該教員の意見を聞くことなしに検討を続けるなどということが起こったということは、控訴人に対する徹底した組織的な誹謗中傷と仲間外しの結果、大学職員の職分を超えしたがって通常の大学業務の範囲を逸脱したそのような非常識な行為が味方のいない控訴人に対してだけは許されるという共通認識が醸成されており、末端の教務課職員までがその共通認識を前提として自らの職分を超え通常の業務範囲を逸脱してでも控訴人の人格を傷つけようという悪意をもってハラスメント行為に及んだことを意味する。(陳述書、8頁、控訴人本人調書、23頁)」(控訴理由書47頁)
(エ)上記アの追加部分のうち、「**の控訴人に対する態度は、極めて敵対的で傲慢であることも、悪意をもって原稿の改ざんがされたことの証左である」という部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(8)「遺脱された主張4」の下線部分の変更を加えた引用である(下線は引用者による)。
「法学部教務課では、**と****が対応した。****の態度は控訴人に対し極めて敵対的かつ傲慢なもので、通常であれば「~して頂けますか?」というところを「~してもらえますか?」と言い放つという、若い職員の年配の教授に対する態度としては普通は考えられぬものである。このような態度は、被控訴人及び東洋大学法学部が常日頃から控訴人を一方的に自分らより下位に位置づけ、控訴人をさげすんでいることの証左である。打ち合わせの最後に当時の法学部教務課長である****が挨拶に来た。その際、**は変ににやにやしながら、控訴人をまじまじと見つめるという控訴人を小馬鹿にした態度を取った。法学部教務課の控訴人に敵対的な雰囲気は、当の改竄が悪意あるハラスメントであることを証すものである。(準備書面4,12頁)」(控訴理由書47頁)
ウ 原判決による第一審「(原告の主張)」欄への追加部分2
「同1 5行目の「本件行為8は」の次に「、パワハラの定義に照らし」を加え、同1 9行目の「、不法行為」を「及び悪意による不法行為」に改める。」(原判決5頁)
エ 上告人が控訴審で指摘した第一審判決における上告人の主張の遺脱部分2
上記ウの追加部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(8)、「遺脱された主張5」を参照し踏まえたものである。」(原判決5頁)
「控訴人は、準備書面5において、パワハラ6類型、パワハラ3要件、「学校法人東洋大学ハラスメントの防止等に関する規程」に定める「パワー・ハラスメント」定義を援用しながら、本件行為8がパワハラであることを主張し(28頁)、また本件行為8が悪意による不法行為であることを主張している。(27頁)」(控訴理由書48頁)
(9)本件行為9について
ア 原判決による第一審「(原告の主張)」欄への追加部分1
「同48頁21行目末尾に改行して、次のとおり加える。
「 フランス語とほかの言語との間で予算の格差を設け、悪意をもってこれを維持し、更に拡大することに業務上の必要性はなく、業務遂行上の手段として不適当でもあって、明白なハラスメントである。法学部において、控訴人には何をしてもよいという共通の了解の下、控訴人に不利益を与えるものでもある。また、被控訴人が控訴人に対して海外研修予算をつけることが可能であることを教示せず、立案や予算要求書提出を勧めることもしなかったことは、極めて異常であり、悪意のあるハラスメントであるというほかない。」」(原判決6頁)
イ 上告人が控訴審で指摘した第一審判決における上告人の主張の遺脱部分1
(ア)上記アの追加部分のうち、「フランス語とほかの言語との間で予算の格差を設け、悪意をもってこれを維持し、更に拡大することに業務上の必要性はなく、業務遂行上の手段として不適当でもあって、明白なハラスメントである」という部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(9)「遺脱された主張1」の下線部分の変更を加えた引用である(下線は引用者による)。
「フランス語予算と他言語予算との間に数10万から100万、200万に至る莫大な格差が10年間も維持されている場合、通常の大学業務の範囲内であれば、10年間の間にこの極端な不平等状態を是正しようという試みが法学部の方からなされているはずである。そのような試みが全くなされないままこれだけ大きな予算格差が10年間も維持された事実は、通常の大学業務の範囲を超えたものであり、
10年以上もの間フランス語のみに予算をつけず、フランス語と他言語との間の予算格差を維持することに何ら業務上の必要性がなく、それが業務遂行上の手段として不適当な行為であり、10年以上という期間が社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであることから、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものである。(準備書面5、29頁~30頁、陳述書、5頁)」(控訴理由書48頁)
(イ)上記アの追加部分のうち、「法学部において、控訴人には何をしてもよいという共通の了解の下、控訴人に不利益を与えるものでもある」という部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(9)「遺脱された主張4」の下線部分の変更を加えた引用である(下線は引用者による)。
「これだけ大きな予算格差が10年間も維持された事実は、**教授らによる徹底した誹謗中傷と仲間外しにより、人間関係から切り離され味方がいないために何をしてもよい存在であるという共通の了解が形作られた控訴人をこの了解に基づいて通常の業務範囲を逸脱してでも貶め、不利益に陥らせようとする悪意なくしては考えられない。(陳述書、5頁)」(控訴理由書49頁)
(ウ)上記アの追加部分のうち、「被控訴人が控訴人に対して海外研修予算をつけることが可能であることを教示せず、立案や予算要求書提出を勧めることもしなかったことは、極めて異常であり、悪意のあるハラスメントであるというほかない」という部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(9)「遺脱された主張3」の下線部分の変更を加えた引用である(下線は引用者による)。
「10年以上も事実上フランス語予算ゼロが続いている時に、被控訴人が控訴人に計画の立案や予算要求書の提出を経て海外研修予算をつけることが可能であることを控訴人に全く教えることもせず、立案や予算要求書提出を勧めることもしなかったのは極めて異常であり、控訴人に対する悪意あるハラスメントがあり、差別待遇、劣後措置があると言うほかはない。(準備書面4、13頁)」(控訴理由書48~49頁)
ウ 原判決による第一審「(原告の主張)」欄への追加部分2
「同頁22行目の「本件行為9は」の次に「、ハラスメントの定義に照らし」を加え、同49頁3行目の「、不法行為」を「及び悪意による不法行為」に改める」(原判決6頁)
エ 上告人が控訴審で指摘した第一審判決における上告人の主張の遺脱部分2
上記(ウ)の追加部分は、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(9)、「遺脱された主張5」を参照し踏まえたものである。
「控訴人は、準備書面5において、パワハラ6類型、パワハラ3要件、「学校法人東洋大学ハラスメントの防止等に関する規程」に定める「パワー・ハラスメント」定義を援用しながら、本件行為9がパワハラであることを主張し(29頁~30頁)、また本件行為9が悪意による不法行為であることを主張している。(29頁)」(控訴理由書49頁)
(10)小括
上記(1)~(9)から明白であるように、原判決は、第一審判決において遺脱され、控訴審弁論において上告人によって判断遺脱の法令違反に該当すると指摘された上告人の主張を、その違法性につき全く審理判断することなく、第一審判決に書き加え、また、原審において上告人によって判断遺脱、経験則違反、論理則違反、自由心証主義違反等の法令違反を指摘された第一審判決の判示を全面的に書き換え、それにより第一審判決の不備を補い、少なくとも当該箇所については判断遺脱等の法令違反のない別の第一審判決を捏造し、これを違法のないものと結論付けている。本来であれば、原判決は、上告人によって判断遺脱を指摘された第一審判決における上告人の主張の遺脱につき、また第一審判決において様々な法令違反を指摘された部分につき、法令違反の有無を審理判断すべきであり、判断遺脱の法令違反があった場合には第一審判決を破棄せねばならないはずである。そして、原判決が、上告人が控訴審において主張の遺脱として指摘した部分をことごとく第一審判決に挿入し、または法令違反を指摘された部分を書き直し、これにより第一審判決の不備をただし第一審判決を補い訂正したのであれば、原判決が当該遺脱部分につき第一審判決を補い訂正する必要を認めたということであり、原判決が、第一審判決による上告人の主張に関する遺脱等につき、あるいは第一審判決のうち上告人によって法令違反を指摘された箇所につき、違法性を認めた蓋然性は極めて大きいと考えざるを得ない。にもかかわらず、原判決は、第一審判決を破棄することなく、また第一審判決による上告人の主張の遺脱その他の違法性につき何ら審理判断することなく、それどころか第一審判決に遺脱された上告人の主張を書き加え、第一審における上告人の主張に関しては判断遺脱のない第一審判決を捏造し、あるいは法令違反を指摘された部分を全面的に書き直し違法部分を削除した第一審判決を捏造し、第一審判決に違法なしとし、上告人の控訴を棄却したのであるから、原判決はこれにより、不利な裁判を受けた上告人から第一審の訴訟上の請求を実現する機会を奪い、上告人の利益が救済される機会を奪ったと言えるのであり、公正な裁判を受ける権利を侵害したと言えるのである。
2 原判決の犯した憲法違反
(1)憲法32条違反(上告理由1)
上記1から明らかであるように、原判決は、第一審判決を不適当であると判断したにもかかわらず、第一審判決を判断遺脱の法令違反によって破棄し、それによって第一審判決の誤謬を是正することなく、「補正」の名のもとに第一審判決の判断遺脱部分を不当に補ない、また法令違反部分を全面的に書き換え、法令違反なしとして上告人の控訴を排斥したのであるから、「裁判の誤謬を是正し、裁判に対する国民の信頼を確保することを目的とする上訴制度とそれに即応して認められた審級制度」と述べつつ上訴制度及び審級制度の目的を明確化した最判昭和28年5月7日民集7巻5号489頁に反する判例違反を犯している。
原判決はまた、第一審判決の誤謬を是正することを拒否するとともに、上告人の利益を救済することをも拒否したのである。裁判を受ける権利を保障した憲法32条が、当事者が「裁判所の判断を求める法律上の利益を有すること」を前提としていることは、最大判昭和35年12月7日民集14巻13号2964頁に述べられる通りである。「憲法三二条は、訴訟の当事者が訴訟の目的たる権利関係につき裁判所の判断を求める法律上の利益を有することを前提として、かかる訴訟につき本案の裁判を受ける権利を保障したものであつて、」。したがって、上告人の有するこのような権利を救済することを放棄することにより、原判決は明らかに判例違反を犯すと同時に憲法32条に違反する憲法違反をも犯しているのである。
学説においては、「憲法三二条に基づく裁判を受ける権利を実質的に保障するもの」として設けられた救済制度の中心をなすものとして上訴制度が考えられている。伊藤眞は次のように書く。「明白な誤謬にせよ、または裁判資料の不足もしくは経験則や法解釈の多様性による判断の偏りにせよ、それによって当事者に不利益が発生する以上、何らの救済制度を設けないのでは、憲法三二条に基づく裁判を受ける権利を実質的に保障するものとはいえない。この救済制度の中心をなすのが上訴制度である」。伊藤はまた、上訴制度の目的につき「上訴の要件として不服、すなわち原裁判による不利益が要求されている以上、上訴制度の主たる目的は当事者の利益救済にあると考えられる」(「上訴制度の目的」、『新民事訴訟法Ⅲ』3頁)と述べている。したがって、第一審判決を不適当であると認めながらこれを変更することなく、「補正」の名のもとに判断遺脱部分を補うと同時に法令違反部分を全面的に書き換え、違法なしとした原判決は、上訴制度の主たる目的である当事者の利益救済を拒否または放棄し、それにより上訴制度の根幹を骨抜きにすると同時に、上訴制度が「憲法三二条に基づく裁判を受ける権利を実質的に保障するもの」であることを鑑みれば、憲法32条が明記した裁判を権利を侵害する憲法違反を犯していることになるのである。
当事者たる上告人の利益救済を不当に放棄し、夥しい判断遺脱他の法令違反を犯す第一審判決を変更あるいは破棄することなく、その代わりに「補正」の名のもとに違法部分を補って、あるいは全面的に書き換えて、これを修正し違法のない別の判決を捏造し、上告人の控訴を棄却し、これにより上訴制度の根幹を危機に瀕せしめ、憲法違反を犯す原判決が公正でないことは言を俟たない。となれば、原判決が「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない」と定めた民事訴訟法2条に違反する法令違反を犯していることは明白である。学術的にも、民事訴訟法2条により裁判所が「公正迅速配慮義務を負うことが明らかにされている」(松本博之『民事上告審ハンドブック』149頁)。
山内敏弘は、「民事裁判について は憲法32条が手続保障(公正手続請求権)の憲法上の根拠とされていると捉えてよいと思われる」(「参加的効力論と公正な裁判を受ける権利」『龍法13号』1123頁)と指摘し、次のように述べる。「憲法学説及び民事訴訟法学説においては、憲法32条の公正な裁判を受ける権利は手続保障(公正手続請求権) をその不可欠の内容として含むものであると理解されている」(「参加的効力論と公正な裁判を受ける権利」1124頁)。したがって、原判決は、公正手続請求権を侵害している点において、公正手続請求権を内実として含む裁判を受ける権利を侵害していることになり、この意味でも憲法違反を犯している。公正手続請求権を含む手続基本権の侵害が憲法違反であることは、学術において指摘されるところである。「控訴審の手続きと判決が当事者の手続基本権を侵害している場合には、訴訟手続に関する憲法違反の上告理由が存在すると解すべきである」(松本博之『民事上告審ハンドブック』119頁)。
したがって、上告人によって指摘された第一審判決における夥しい判断遺脱及びその他の法令違反につき審理判断し当該判決を変更・破棄することなく、判断遺脱部分をことごとく補うと同時に法令違反部分を書き換えることにより別の判決を捏造し第一審判決に違法なしとし、上告人の控訴を棄却した原判決は、上訴制度の目的である誤謬の是正と当事者の利益救済を拒否した点で、「憲法三二条に基づく裁判を受ける権利を実質的に保障するもの」としての上訴制度の根幹を危機に瀕せしめた点において、そして、裁判を受ける権利の内実をなす公正手続請求権を侵害した点においても、そして、最高裁判例から言っても学術的理解から言っても、憲法32条に違反する憲法違反を犯しているのである。
(2)憲法14条1項違反(上告理由2)
上訴制度が正常に機能する範囲内では、第一審判決に判断遺脱他の違法があれば控訴審はそれにつき審理判断し、違法である場合には判決を変更して当時者の利益を救済するのが通常であるところ、原判決にあっては、第一審判決の夥しい判断遺脱部分を補い、他の法令違反部分を全面的に書き換え、それにより第一審判決を修正し別の判決に仕立て上げ、上告人の控訴を棄却し、上告人の利益救済を拒否したのであるから、これにより上告人は自身の利益が救済される機会を失ったことになり、控訴人が通常享受する権利を侵害されるという不平等を被ったことになる。学術において、「同様の訴訟状況にある他の訴訟の当事者との関係での平等をも保障する憲法上の平等原則(憲14状1項)」(松本博之『民事上告審ハンドブック』121頁)が指摘される通り、上告人の利益救済を拒否した原判決は、法の下の平等を定め平等権を保障する憲法14条1項に違反する憲法違反を犯している。
原判決の憲法14条1項違反は最高裁判例によっても確認される。例えば、昭和39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁は、次のように述べる。「右各法条は、国民に対し絶対的な平等を保障したものではなく、差別すべき合理的な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、事柄の性質に即応して合理的と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない」。原判決が第一審判決の判断遺脱他の法令違反につき審理判断することなく上告人の利益救済を拒否した行為は何ら「事柄の性質に即応して合理的と認められる差別的取扱」とは認められぬものであるから、「差別すべき合理的な理由なくして差別することを禁止している」憲法14条1項に違反していることは明白である。また、最大判平成27年12月16日民集69巻8号2586頁には、「憲法14条1項は,法の下の平等を定めており,この規定が,事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り,法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものであると解すべきことは,当裁判所の判例とするところである」とあり、憲法14条1項が、上告人の利益救済を拒否した原判決の行為のごとき不合理な「差別的取扱い」を禁止していることは明白である。
(3)憲法76条3項違反(上告理由3)
第一審判決の夥しい判断遺脱部分及びその他の法令違反部分につき審理判断することなく、これらを補うことにより、あるいは経験則違反等の法令違反を指摘された判示を全面的に書き換えることにより、当該判決を全く別の判決に書き換え、これを法令違反なきものとみなし、上告人の控訴を棄却する原判決の行為は、上訴制度を根本的に破壊する前代未聞の不祥事というべきであり、原判決が「裁判が法に基づき公正中立に行われることを保障」した憲法76条3項に違反する憲法違反を犯していることは明らかである。最大判平成23年11月16日刑集65巻8号1285頁に、「元来,憲法76条3項は,裁判官の職権行使の独立性を保障することにより,他からの干渉や圧力を受けることなく,裁判が法に基づき公正中立に行われることを保障しようとするものである」と述べられた通りである。原判決の上記行為は、まさに裁判官の「職責と相いれないような行為」であると言える。最高裁大法廷判決平13.3.30.裁判集民事201号737頁、判例時報1760号68頁は次のように判示する。「裁判の公正,中立は,裁判ないしは裁判所に対する国民の信頼の基礎を成すものであり,裁判官は,公正,中立な審判者として裁判を行うことを職責とする者である。したがって,裁判官は,職務を遂行するに際してはもとより,職務を離れた私人としての生活においても,その職責と相いれないような行為をしてはならず,また,裁判所や裁判官に対する国民の信頼を傷つけることのないように,慎重に行動すべき義務を負っているものというべきである」。また、原判決の当該行為が、「自己内心の良識と道徳感に従う」ものでないことも明らかである。最高裁大法廷判決昭23.11.17刑集2巻12号1565頁は次のように判示する。「憲法第七六条第三項の裁判官が良心に従うというのは、裁判官が有形無形の外部の圧迫乃至誘惑に屈しないで自己内心の良識と道徳感に従うの意味である」。
(4)小括
上記1及び2(1)~(3)より、原判決には、憲法32条、憲法14条1項及び憲法76条3項に違反する憲法違反の上告理由がある(上告理由1,2,3)。
第3 原判決の理由不備(上告理由4、5、6)及び理由齟齬(上告理由7)
原判決は、上告人の具体的な主張や具体的事実につき全く検討していないため、原判決には具体的な理由が完全に欠如している。
確かに、原判決が不当にも「引用」するとしている第一審判決には具体的な理由が欠如していないが、後述の通り、上告人は第一審判決のすべての判示につき、判断遺脱、経験則違反、論理則違反、採証法則違反、弁論主義違反、自由心証主義違反、法令解釈適用を誤った違法等、判決結果に影響を及ぼす夥しい法令違反があることを原審において主張しているにもかかわらず(控訴理由書第2章参照)、原判決は、第一審判決のこれらすべての法令違反に関する上告人の主張につき、一切審理判断していない。原判決における「引用」部分以外の事実や上告人の主張に関する認定判断及びパワハラや不法行為の有無に関する審理判断においても、原判決は、上告人の具体的主張や具体的事実につき一切検討せず、それらについての判断を全く示していないのであるから、原判決は、「引用」部分においても、それ以外の部分においても、具体的な理由を全く欠いたものであると言え、原判決に、民訴法312条2項6号に掲げる絶対的上告理由としての理由の不備があることは疑い得ない(上告理由4)。
以上に加え、とりわけパワハラや不法行為の有無に関する原判決の審理判断の著しい特徴として、パワハラや不法行為の有無に関する判断において、原判決は、パワハラ行為の発生した状況や文脈及びパワハラ行為の程度、継続期間、頻度、反復性等の様態に関わる重要な具体的事実につき、一切審理判断していない。つまり、原判決の判断枠組みは、パワハラ行為の不法行為性を検討するにあたって考慮することが必要不可欠である、社会通念や業務上の常識をも包含するパワハラ行為発生の状況や文脈及びパワハラ行為の程度、継続期間、頻度、反復性等の様態に関わる重要な具体的事実の検討を全く欠いたまま、業務上の合理性及び必要性があるかどうか、社会通念に照らして許容されるかどうか等について結論を出すというものであり、かような誤った判断枠組みを用いてパワハラ及び不法行為の有無が問題になる本件各行為について判決結果を導く原判決には、理由の本質的部分が欠けていると考えざるを得ない。したがって、原判決には、判決主文を導き出すための理由の一部が欠けていると言わざるを得ず、民訴法312条2項6号に掲げる絶対的上告理由としての理由の不備があると言わざるを得ない(上告理由5)。
さらに、原判決が上告人の精神的苦痛及び精神的損害等につき一切審理判断していないことを鑑みれば、本件行為1~9の不法行為性につき判断するにあたって上告人の精神的苦痛を全く考慮しないことから、原判決が論理的に完結しているとは言えず、判決主文を導き出すための理由の一部が欠けていると言わざるを得ず、原判決に、民訴法312条2項6号に掲げる絶対的上告理由としての理由の不備があることは明白である(上告理由6)
また、第一審判決を「引用」するとしながら「補正」名のもとに第一審判決を大幅に書き換えた上で、上告人の請求を排斥した原判決の理由づけには論理的矛盾があり、したがって、原判決には理由の食違いがあると言え、民訴法312条2項6号に掲げる絶対的上告理由としての理由齟齬がある(上告理由7)。
1 原判決が第一審判決の「引用」に際して犯した夥しい判断遺脱の法令違反
原判決は、夥しい法令違反を犯した第一審判決の判決理由をほぼ引用するとし、判決に影響を及ぼす重要な事項に相当する上告人の具体的な主張や事実につき全く審理判断することなく、上告人の控訴を棄却した。第一審判決に具体的な主張や事実についての判断が見られるとしても、これらの判断には、上告人が控訴審弁論で主張したように(控訴理由書第2章参照)、判断遺脱、経験則違反、論理則違反、採証法則違反、弁論主義違反、自由心証主義違反、法令解釈適用を誤った違法等、判決結果に影響を及ぼす夥しい法令違反があるにもかかわらず、原判決は、第一審判決の当該法令違反につき全く審理判断していない。そうすると、原判決は、判決に影響を及ぼす重要な事項に相当する上告人の具体的な主張や事実につき全く審理判断していないということになり、判決理由を十分に示したことにならず、判決主文を導き出すための理由の一部が欠けていると言わざるを得ず、民訴法312条2項6号に掲げる絶対的上告理由としての理由の不備があると言わざるを得ない。
(1)第一審判決における前提事実の遺脱に関する上告人の主張についての判断遺脱
原判決は、前提事実につき、第一審判決追加部分を除いて、第一審判決を引用すると判示している(原判決第2・2、2頁)。この追加が憲法違反であることは上述の通りである。となれば、原判決は上告人が第一審判決につき控訴審弁論において主張した前提事実の遺脱につき全く審理判断していないということになる。具体的には、控訴理由書第2章第3・1(1)「「ハラスメントの防止に関する定め」に関する事実の遺脱」、すなわち、「パワハラ3要件及び6類型の遺脱」及び「「学校法人東洋大学ハラスメントの防止等に関する規程」第18条7項の遺脱」(控訴理由書51~52頁)、(2)「「本件訴訟に至る経緯」に関する事実の遺脱」(控訴理由書52頁)、(3)「控訴人の経歴の遺脱」(控訴理由書52~53頁)、(4)「控訴人のくも膜下出血既往症の遺脱」(控訴理由書53頁)につき原判決は全く審理判断していない。したがって、ここには、原判決による判決に影響を及ぼす判断遺脱の法令違反がある。
(2)第一審判決における争点変更の法令違反に関する上告人の主張についての判断遺脱
原判決は、争点についても、第一審判決を引用するとしている(原判決2頁)。引用とは、松本博之も指摘する通り、「控訴裁判所が引用部分の第一審判決の理由に従うことを自己の判決において明示的に確認していることを意味する」(松本博之『民事上告審ハンドブック』190頁)。しかし第一審における争点の違法な変更については、上告人が控訴審において主張し攻撃方法を提出したものである。第一審判決時点で争点変更に関する上告の主張は当然になされていないのであるから、争点につき第一審判決を引用することは、極めて不当な違法行為であるというほかはない。学術においてもこのような認識が確認される。例えば、松本博之は、上述の引用部分に続けて、次のように書く。「しかし、このことは控訴審において新たな請求が提起され、または新たな攻撃防御方法が提出された場合には妥当せず、第一審判決の理由を引用することはできない。なぜなら、これらは第一審段階では存在せず、第一審判決はこれについて判断することができないからである」(同書)。
上記に加えて、争点について第一審判決を引用するとする原判決は、上告人が控訴審弁論において主張した第一審判決における争点変更の法令違反(控訴理由書第1章第4、32~35頁)につき全く審理判断していない。したがって、原判決による判決に影響を及ぼす判断遺脱の法令違反があるというほかはない。
(3)第一審判決における本件行為1~9及びパワハラの長期にわたる継続性と大規模な組織性及び安全配慮義務違反に関する認定事実の誤りと遺脱に関する上告人の主張についての判断遺脱
原判決は、「第3当裁判所の判断」という部分で(原判決9頁)、「補正」部分を除けば、第一審判決「事実及び理由」欄の「第3当裁判所の判断」を引用するとしている。ところが、上告人は控訴審弁論において、第一審判決当該部分の本件行為1~9各行為についての「認定事実」欄につき、またパワハラの長期にわたる継続性と大規模な組織性及び安全配慮義務違反に関して、認定事実の誤りと遺脱を指摘している(控訴理由書第2章第3・2,53~69頁)。そうすると、原判決は、第一審判決における本件行為1~9及びパワハラの長期にわたる継続性と大規模な組織性及び安全配慮義務違反に関する認定事実の誤りと遺脱に関する上告人の控訴審における主張すべてにつき全く審理判断していないことになる。したがって、原判決が判決に影響を及ぼす判断遺脱の法令違反を犯していることは明白である。
(4)第一審判決における本件行為1~9及びパワハラの長期にわたる継続性と大規模な組織性及び安全配慮義務違反に関する夥しい法令違反に関する上告人の主張についての判断遺脱
ア 判断遺脱の法令違反
原判決は、「第3当裁判所の判断1及び2」という部分で(原判決9~13頁)、「補正」部分を除けば、第一審判決「事実及び理由」欄の「第3当裁判所の判断」を引用するとしている。ところが、上告人は原審弁論において、第一審判決当該部分の本件行為1~9各行為についての「検討」欄につき、またパワハラの長期にわたる継続性と大規模な組織性及び安全配慮義務違反に関して、判断遺脱、経験則違反、論理則違反、採証法則違反、弁論主義違反、自由心証主義違反、法令解釈適用を誤った違法等、第一審判決の犯した夥しい法令違反を指摘している(控訴理由書第2章第4「事実認定及び法令解釈適用の違法」、69~106頁)。そうすると、原判決は、第一審判決における本件行為1~9及びパワハラの長期にわたる継続性と大規模な組織性及び安全配慮義務違反に関する夥しい数の法令違反に関する上告人の原審における主張すべてにつき全く審理判断していないことになる。したがって、原判決が判決に影響を及ぼす判断遺脱の法令違反を犯していることは明白である。
イ その他の法令違反
(2)に前述の通り、引用とは、「控訴裁判所が引用部分の第一審判決の理由に従うことを自己の判決において明示的に確認していることを意味する」(松本博之『民事上告審ハンドブック』190頁)。そうなると、松本も指摘する通り、「第一審裁判所の手続違反に基づく判決を控訴裁判所が明示的に受け入れている場合、たとえば手続違反を主張する控訴を実質的な審理をしないで棄却した場合にも、控訴審において手続瑕疵が生じているといえる」(『民事上告審ハンドブック』170頁)。つまり、上告人が控訴理由書第2章第4「事実認定及び法令解釈適用の違法」(69~106頁)において、第一審判決当該部分の本件行為1~9各行為についての「検討」欄につき、またパワハラの長期にわたる継続性と大規模な組織性及び安全配慮義務違反に関して、主張した判断遺脱、経験則違反、論理則違反、採証法則違反、弁論主義違反、自由心証主義違反、法令解釈適用を誤った違法等、第一審判決の犯した夥しい法令違反を原判決もまた犯したことになるのである。したがって、原判決には、判決に影響を及ぼす上記すべての法令違反がある。
2 原判決「引用」部分以外における判決に影響を及ぼす重要な具体的事実についての判断遺脱の法令違反
(1)上告人の主張追加部分における具体的事実の遺脱
原判決は、一方で、第一審判決の判断遺脱につき何ら審理判断することなく、判断遺脱部分を補って別の判決を捏造したが、他方で、不正な追加部分においても、上告人の主張の結論部だけを選択し書き加えることによって、判決に影響を及ぼす重要な事実とそれらについての上告人の主張を遺脱する数多くの判断遺脱を犯している。
以下に、原判決による第一審判決(別紙)「パワーハラスメント行為一覧表」本件行為1~9(原告の主張)欄への追加部分のうち遺脱された重要事実とそれらについての上告人の主張を指摘する。
ア 本件行為1について
(ア)原判決による第一審「(原告の主張)」欄への追加部分
「履修者数の多寡は、中国語及びドイツ語の契約制講師採用の正当な理由にはなり得ないものであるし、大学全体の収容定員に応じ定める教員数の配分を事実上変更することは法令違反であり、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであることは明らかである。
また、被控訴人においては、フランス語の教員枠に対する対応が一貫していないのであって、控訴人を仲間外しにし、控訴人をおとしめる悪意があるのみであった。フランス語教員枠の政治学教員枠への転用は、控訴人に精神的苦痛を与えるとともに、控訴人を孤立させることを目的とするものであった。」(原判決3頁)
(イ)上記(ア)の追加部分のうち、「被控訴人においては、フランス語の教員枠に対する対応が一貫していないのであって、控訴人を仲間外しにし、控訴人をおとしめる悪意があるのみであった。」という部分は、前述の通り、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(1)「遺脱された主張3」の一部の若干の変更を加えた引用であるが、判決に影響を及ぼすことの明白な下線部の重要事実及びそれらに関する上告人の主張が原判決においては遺脱されている(下線は引用者による)。したがって、原判決には判断遺脱の法令違反がある。
「まず被控訴人東洋大学が、2008~9年に一人であったフランス語専任教員を*****を雇うことによって二人にし、***を重んずることによって控訴人を法学部フランス語運営から排除し、次いで2015~6年に二人いたフランス語専任教員を控訴人一人にすることによってフランス語劣遇措置がそのまま控訴人へのハラスメントになるような状況を作り、最後に2022~3年に法学部フランス語非常勤講師を3人増員することによって控訴人から授業を奪ったという事実がある。この過程を通して、法学部フランス語教員の増減はフランス語履修者数の増減と一切相関関係はない。つまり、被控訴人は、ある時は法学部フランス語教員枠二人を尊重しフランス語教員を雇い、ある時はフランス語教員枠を事実上減らしフランス語教員を採用しないようにしており、フランス語教員枠の被控訴人による扱いは全く首尾一貫していない。首尾一貫しているのは、フランス語教員を増やす時も増やさない時も控訴人を貶める悪意(故意あるいは過失)のみである。同様に被控訴人は、フランス語教員枠の政治学教員枠への転用に際してフランス語履修者減を理由とするが、他方でフランス語履修者の増減に関係なくフランス語教員を増やしている。そして、いずれの場合にも控訴人を無視し仲間外しし控訴人の尊厳を傷つける故意過失のみが一貫して確認される。(準備書面5、6頁~7頁、陳述書、6頁~7頁)」(控訴理由書38~39頁)
(ウ)上記(ア)の追加部分のうち、「フランス語教員枠の政治学教員枠への転用は、控訴人に精神的苦痛を与えるとともに、控訴人を孤立させることを目的とするものであった。」という部分は、前述の通り、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(1)「遺脱された主張4」の一部の若干の変更を加えた引用であるが、判決に影響を及ぼすことの明白な下線部の重要事実及びそれに関する上告人の主張が原判決においては遺脱されている(下線は引用者による)。したがって、原判決には判断遺脱の法令違反がある。
「フランス語教員枠の政治学教員枠への転用は、控訴人の意見を全く聞くことなく転用を決めた無視と仲間外しによって控訴人に精神的苦痛を与えると同時に、法学部フランス語専任教員だけを控訴人一人にすることによって、既に法学部内で仲間外しに遭っていた控訴人をさらに孤立させ、控訴人の発言力を奪いその立場を弱く不利なものとすると同時に、フランス語劣遇措置を容易にすることによってフランス語劣遇が法学部唯一のフランス語専任教員である控訴人へのハラスメントになることを目的とした悪意によるハラスメントである。(準備書面5、3頁、5頁、陳述書、6頁)」(控訴理由書39頁)
イ 本件行為2について
(ア)原判決による第一審「(原告の主張)」欄への追加部分
「原稿に問題があるのであれば、それを無視するのではなく、作成者に連絡をするのが常識であるから、これを無視することは、業務上必要かつ相当な範囲を超えているのであるが、**らは、控訴人を苦しめるため、悪意をもって、このような控訴人を無視するとの手段を選択した。また、控訴人に何らの相談もせずに控訴人の原稿を採用しなかったことは、控訴人の授業を妨害し、その就労に不利益を与えて就労環境に悪影響を及ぼすものである。控訴人は、被控訴人において徹底的に誹謗中傷されていたから、控訴人の原稿を無視するという常識に反する対応も許されてしまっていた。」(原判決3頁)
(イ)上記(ア)の追加部分のうち、「**らは、控訴人を苦しめるため、悪意をもって、このような控訴人を無視するとの手段を選択した」という部分は、前述の通り、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(2)「遺脱された主張2」の一部の若干の変更を加えた引用であるが、判決に影響を及ぼすことの明白な下線部の重要事実が原判決においては遺脱されている(下線は引用者による)。したがって、原判決には判断遺脱の法令違反がある。
「**学部長らは、原稿作成者の原稿を無視するという他の教職員に対しては絶対にしない通常の業務を逸脱した対応を、人間関係から切り離され孤立した状態にある控訴人に対して、控訴人に連絡する、字数を増やす等、可能ないくつかの選択肢のなかから控訴人を苦しめようという悪意をもって選択した。(準備書面5、10頁、陳述書、7頁)」(控訴理由書40頁)
(ウ)上記(ア)の追加部分のうち、「また、控訴人に何らの相談もせずに控訴人の原稿を採用しなかったことは、控訴人の授業を妨害し、その就労に不利益を与えて就労環境に悪影響を及ぼすものである。」という部分は、前述の通り、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(2)「遺脱された主張3」の一部の若干の変更を加えた引用であるが、判決に影響を及ぼすことの明白な下線部の重要事実が原判決においては遺脱されている(下線は引用者による)。したがって、原判決には判断遺脱の法令違反がある。
「控訴人に何らの相談もせず控訴人の原稿を採用しなかったことにより控訴人の授業計画が学生に正確に伝達されないと同時に、控訴人は伝達されたと勘違いして授業することになるため、控訴人の授業についての双方の理解の間に齟齬が生じ、原告の授業運営がスムーズに行かなくなる。したがって、被控訴人の行為は控訴人の授業を妨害することであり、控訴人の就労における不利益を与え、就労環境に悪影響を及ぼすものである。(準備書面5、10頁~11頁)」(控訴理由書40頁)
(エ)上記(ア)の追加部分のうち、「控訴人は、被控訴人において徹底的に誹謗中傷されていたから、控訴人の原稿を無視するという常識に反する対応も許されてしまっていた」という部分は、前述の通り、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(2)「遺脱された主張4」の一部の若干の変更を加えた引用であるが、判決に影響を及ぼすことの明白な下線部の重要事実が原判決においては遺脱されている(下線は引用者による)。したがって、原判決には判断遺脱の法令違反がある。
「控訴人の場合は、**教授の画策により徹底的に誹謗中傷され、法学部の中でほぼ人間関係から切り離された、味方のいない状態でいるので、原稿を無視するというような常識に反した失礼な対応も許される存在になっていた。(陳述書、7頁)」(控訴理由書40頁)
ウ 本件行為3について
(ア)原判決による第一審「(原告の主張)」欄への追加部分
「同36頁1 6行目末尾に「これは、控訴人が孤立し味方のいない弱い立場にあるからであって、業務上の必要性はないし、業務遂行上の手段として不適当なものでもあった。」を、同1 8行目の「である。」の次に「これは、複数の悪意あるフランス語劣後措置の一つであり、他のものと同様に、控訴人に対する悪意あるハラスメントであった。」を、同18行目の「本件行為3は」の次に「、パワハラの定義に照らし」を、同20行目の「原告に対する」の次に「悪意による」を、それぞれ加える。」(原判決3~4頁)
(イ)上記(ア)の追加部分のうち、「これは、控訴人が孤立し味方のいない弱い立場にあるからであって、業務上の必要性はないし、業務遂行上の手段として不適当なものでもあった」という部分は、前述の通り、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(3)「遺脱された主張1」の一部の若干の変更を加えた引用であるが、判決に影響を及ぼすことの明白な下線部の重要事実が原判決においては遺脱されている(下線は引用者による)。したがって、原判決には判断遺脱の法令違反がある。
「履修者数の点でフランス語と競合するドイツ語の宣伝だけを法学部HPに載せたことについて、そのような語学宣伝の場があることを法学部が私に教えなかったこと、フランス語とドイツ語間のこの不平等状態が2016年からほぼ5年間続いていた期間法学部の誰も私にそのような場があることを私に教えなかったことは、孤立し味方のいない弱い立場に立たされた私だけになされたことであり、業務上の必要性がなく、それが業務遂行上の手段として不適当な行為であり、しかも不平等状態の続いた期間が社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであることから業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであり、私に対する悪意なくしては考えられない。(準備書面5、12頁、陳述書、7頁)」(控訴理由書40~41頁)
(ウ)上記(ア)の追加部分のうち、「これは、複数の悪意あるフランス語劣後措置の一つであり、他のものと同様に、控訴人に対する悪意あるハラスメントであった」という部分は、前述の通り、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(3)「遺脱された主張2」の一部の若干の変更を加えた引用であるが、判決に影響を及ぼすことの明白な下線部の重要事実が原判決においては遺脱されている(下線は引用者による)。したがって、原判決には判断遺脱の法令違反がある。
「**教授が法学部を始め学内に控訴人について誹謗中傷をし、控訴人が孤立し法学部内で徹底した仲間外しに遭っている状況で、しかも**教授の悪意のもと他に複数の悪意あるフランス語劣遇措置がとられている中、このハラスメントだけが悪意ない偶然のものであったとは考えられない。」(控訴理由書41頁)
エ 本件行為4について
(ア)原判決による第一審「(原告の主張)」欄への追加部分
「このようなことは、控訴人以外の教員では起こり得ないのであって、被控訴人において、控訴人以外の語学教員には、平成23年の「教養演習開講方針」に従わなくていいことを伝え、控訴人のみがこれに従うようにしたからこそ生じたものにほかならない。被控訴人は、「教養演習開講について」との学部長文書をもって、過去のハラスメントを明文化して正当化するとともに、控訴人が過去に担当した教養演習より厳しい条件を課すことで、控訴人が教養演習を再開講することをあきらめさせようとしたものである。
これに対し、被控訴人は、控訴人に不利益を与えるため、ある時は6コマの授業が必要とし、ある時は5コマの授業でもよいとの恣意的な主張をするにすぎない。」(原判決4頁)
(イ)上記(ア)の追加部分のうち、「このようなことは、控訴人以外の教員では起こり得ない」という部分は、前述の通り、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(4)「遺脱された主張1」の一部の若干の変更を加えた引用であるが、判決に影響を及ぼすことの明白な下線部の重要事実が原判決においては遺脱されている(下線は引用者による)。したがって、原判決には判断遺脱の法令違反がある。
「法学部の大半の語学教員が教養演習を開講している中で控訴人だけが開講していないという異常な事態が10年間以上も誰にも批判もされずに放置され維持されているという状況自体が孤立し味方のいない私以外の教員には起こり得ない、通常の大学業務の範囲を超えるものである。このような状況は、偶然には維持され得ず、完全に排除され一人前の教員扱いしなくてもよいとされた私を通常の業務範囲を逸脱してでも苦しめようとする法学部教職員らの悪意によるものである。(準備書面5、15頁、陳述書、3頁)(控訴理由書41頁)
(ウ)上記(ア)の追加部分のうち、「被控訴人において、控訴人以外の語学教員には、平成23年の「教養演習開講方針」に従わなくていいことを伝え、控訴人のみがこれに従うようにしたからこそ生じたものにほかならない。」という部分は、前述の通り、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(4)「遺脱された主張2」の一部の若干の変更を加えた引用であるが、判決に影響を及ぼすことの明白な下線部の重要事実が原判決においては遺脱されている(下線は引用者による)。したがって、原判決には判断遺脱の法令違反がある。
「2011年の「教養演習開講方針」には、教養演習開講の必要条件として履修者10名以上語学科目6コマ+教養演習1コマ計7コマが定められているが、2011年以後10年以上にもわたって控訴人以外のほぼすべての語学教員らによる数多くの教養演習やセミナーがこの条件を満たさないまま開講されている。このような状況は、**法学部長らが、控訴人以外の語学教員には「教養演習開講方針」に従わなくていいことを伝え、それによって控訴人だけがこれに従うようにし向けたということがなければ起こり得ない。したがって、「教養演習開講方針」が控訴人の教養演習開講を妨げようという悪意によって作成されたものであり、上述の状況は、控訴人を差別し、控訴人だけを不利益に陥れようという悪意によって実現されたものである。(準備書面4、9頁~10頁、陳述書、3頁~4頁)」(控訴理由書42頁)
(エ)上記(ア)の追加部分のうち、「これに対し、被控訴人は、控訴人に不利益を与えるため、ある時は6コマの授業が必要とし、ある時は5コマの授業でもよいとの恣意的な主張をするにすぎない」という部分は、前述の通り、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(4)「遺脱された主張3」の一部の若干の変更を加えた引用であるが、判決に影響を及ぼすことの明白な下線部の重要事実が原判決においては遺脱されている(下線は引用者による)。したがって、原判決には判断遺脱の法令違反がある。
「被控訴人が第3準備書面で2023年度の控訴人の担当コマ数を4コマにしたことを不当に正当化するために5コマでよいと主張している事実から、被控訴人が控訴人に対して悪意をもってハラスメントを犯すために、控訴人を不利益に貶めたり苦しめたりする限りにおいて、ある時は6コマ必要と主張し、ある時は5コマでよいと主張しているだけであることが帰結する。(準備書面4、8頁、陳述書、4頁)」(控訴理由書42頁)
オ 本件行為5について
(ア)原判決による第一審「(原告の主張)」欄への追加部分
「同頁14行目の「なかった。」の次に「このようなことは、通常の大学業務の範囲内では起こり得ないものであり、偶然とは考え難い上、業務上の必要性はなく、業務遂行上の手段として不適当でもある。また、法学部が悪意をもって、控訴人の評価を不当におとしめるものでもある。」を加え、同14行目の「これは」を「以上のとおり」に改め、同1 6行目から1 7行目までにかけての「本件行為5は」の次に「、パワハラの定義に照らし」を、同1 9行目の「及び」の次に「悪意による」を、それぞれ加える。」(原判決4頁)
(イ)上記(ア)の追加部分のうち、「このようなことは、通常の大学業務の範囲内では起こり得ないものであり、偶然とは考え難い上、業務上の必要性はなく、業務遂行上の手段として不適当でもある。」という部分は、前述の通り、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(5)「遺脱された主張1」の一部の若干の変更を加えた引用であるが、判決に影響を及ぼすことの明白な下線部の重要事実が原判決においては遺脱されている(下線は引用者による)。したがって、原判決には判断遺脱の法令違反がある。
「法学部のほとんどすべての専任教員が「長」のつく何らかの役職を経験している中、控訴人にだけ20年以上も何らの役職にもつかせないということは、通常の大学業務の範囲内では起こり得ないものであり、控訴人のみに対するそのような劣遇に何ら業務上の必要性がなく、それが業務遂行上の手段として不適当な行為であり、しかも当該行為の継続期間が社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであることから業務上必要かつ相当な範囲を超えたものである。(準備書面5、17頁、陳述書、9頁)」(控訴理由書43頁)
(ウ)上記(ア)の追加部分のうち、「また、法学部が悪意をもって、控訴人の評価を不当におとしめるものでもある」という部分は、前述の通り、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(5)「遺脱された主張2」の一部の若干の変更を加えた引用であるが、判決に影響を及ぼすことの明白な下線部の重要事実が原判決においては遺脱されている(下線は引用者による)。したがって、原判決には判断遺脱の法令違反がある。
「ほとんどの法学部教員が何らかの役職を与えられるなか原告にのみ20年以上の間何らの役職をも与えなかった行為は、これを偶然のものであると考えることはできず、被控訴人の悪意によるものと考えるほかはない。(準備書面5、17頁~18頁、陳述書、9頁)」(控訴理由書43頁)
カ 本件行為6について
(ア)原判決による第一審「(原告の主張)」欄への追加部分
「同42頁24行目の末尾に「主査である控訴人の所見を副査の所見よりも下位に置き、審査結果報告書にも控訴人の所見を全く掲載せず、反映もさせないことは、業務上の必要性を欠き、業務遂行上不適当な行為であって、控訴人には何をしてもよいという法学部内の共通の了解の下、明白な悪意によりされたものである。」を加え、同頁2 5行目の「本件行為6は」の次に「、パワハラの定義に照らし」を、同43頁2行目の「及び」の次に「悪意による」を、それぞれ加える。」(原判決5頁)
(イ)上記(ア)の追加部分のうち、「主査である控訴人の所見を副査の所見よりも下位に置き、審査結果報告書にも控訴人の所見を全く掲載せず、反映もさせないことは、業務上の必要性を欠き、」という部分は、前述の通り、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(6)「遺脱された主張1」の一部の若干の変更を加えた引用であるが、判決に影響を及ぼすことの明白な下線部の重要事実が原判決においては遺脱されている(下線は引用者による)。したがって、原判決には判断遺脱の法令違反がある。
「非常勤講師採用審査にあたって、控訴人を主査にしたのであれば、主査に主要役割を副査に副次的役割を負わせ、副査の見解を審査結果報告書に反映させ掲載したのであれば、主査についてはより多く反映・掲載するのが通常の大学業務で行われることである。したがって、主査である控訴人の所見を副査のそれより下位に置いたり、審査結果報告書に全く掲載もせず反映もさせないことには、何ら業務上の必要性はなく、それが業務遂行上の手段として不適当な行為であることから、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものである。(準備書面5、24頁、陳述書、8頁)」(控訴理由書44頁)
(ウ)上記(ア)の追加部分のうち、「業務遂行上不適当な行為であって、控訴人には何をしてもよいという法学部内の共通の了解の下、明白な悪意によりされたものである」という部分は、前述の通り、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(6)「遺脱された主張2」の一部の若干の変更を加えた引用であるが、判決に影響を及ぼすことの明白な下線部の重要事実が原判決においては遺脱されている(下線は引用者による)。したがって、原判決には判断遺脱の法令違反がある。
「****学部長らは、副査の見解は踏まえながら主査である控訴人の見解は審査結果報告書に全く反映させないという控訴人以外の他の教員には決してなされない通常の業務を逸脱したことをした。これは、徹底した仲間外しによって法学部内にあるいは大学全体に孤立し味方のいない控訴人にだけは何をやっても大丈夫という共通の了解が出来上がっており、その共通の了解を前提として通常の業務範囲を超えてでも私の精神を傷つけるようとしてなされたことであり、明白に悪意によるものである。(準備書面5、23頁、陳述書、8頁)」(控訴理由書44頁)
キ 本件行為7について
(ア)原判決による第一審「(原告の主張)」欄への追加部分1
「同44頁1 6行目末尾に改行して、次のとおり加える。「 また、法学部では、教授会資料に掲載される推薦入試出向教員一覧の一番上にほかと切り離した形でほかの教員の氏名より大きな活字で控訴人の氏名を印刷した。これは、控訴人が法学部内の人間関係から隔離されていることを法学部教員らに象徴的に示すとともに、控訴人にもそれをはっきりと示して精神的苦痛を与えるためにされたものである。」」(原判決5頁)
(イ)上記(ア)の追加部分は、前述の通り、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(7)「遺脱された主張3」の一部の若干の変更を加えた引用であるが、判決に影響を及ぼすことの明白な下線部の重要事実及びそれらに関する上告人の主張が原判決においては遺脱されている(下線は引用者による)。したがって、原判決には判断遺脱の法令違反がある。
「2007年から少なくとも2014年まで(あるいは2015年まで)の8年間(あるいは9年間)にわたって、被控訴人東洋大学法学部は、教授会資料に載る10月・11月推薦入試出向教員一覧の一番上に他から切り離した形でしかも他の教員の氏名より大きな活字で控訴人の氏名を印刷した。ちなみに控訴人の氏名は一覧表などに載る時はいつも一番下や最後に書かれるので、一番上に書かれたのはこの時だけである。
留学生日本語試験採点の日は法学部での試験監督出向は控訴人だけであり、被控訴人東洋大学法学部がこれを10年間にわたってさせたのは明らかに法学部内での控訴人の人間関係からの切り離しを狙ったものである 。そして、控訴人が法学部内で人間関係から隔離され仲間外しされていることを新任教員も含めた法学部教員たちに象徴的に示すために、そして控訴人に対しても自身が仲間外しされていることをはっきり示し、これによって控訴人に精神的苦痛を与え原告の精神をさいなむために、教授会資料に挿入される、出向日ごとに入試業務担当教員を分類・区分した10月・11月推薦入試出向教員一覧表において、例えば10月19日であれば、一番上に置かれた10月19日の欄に一人だけ書かれた控訴人の氏名をことさら大きな活字で印刷し、その下の別の日にち欄に印刷された多数の法学部教員の氏名との対照を際立たせることによって、一覧表の上でも控訴人が隔離され差別されているということを示したのである。」(控訴理由書45~46頁)
(ウ)原判決による第一審「(原告の主張)」欄への追加部分2
「同頁1 8行目の「ことは」の次に「、偶然とは考え難い上、業務上の必要性はなく、業務遂行上の手段として不適当なものでもあって」を、同1 9行目の
「であり」の次に「、パワハラの定義に照らし」を、それぞれ加え、同22行目の「、不法行為」を「及び悪意による不法行為」に改める。」(原判決5頁)
(エ)上記(ウ)の追加部分は、前述の通り、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(7)「遺脱された主張1・2」の一部の若干の変更を加えた引用であるが、判決に影響を及ぼすことの明白な下線部の重要事実及びそれらに関する上告人の主張が原判決においては遺脱されている(下線は引用者による)。したがって、原判決には判断遺脱の法令違反がある。
「ほぼ10年連続で留学生日本語試験採点の仕事を東洋大学で控訴人のみに強要することに何ら業務上の必要性がなく、それが業務遂行上の手段として不適当な行為であり、10年連続という期間が社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであることから、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものである。」
「東洋大学でただ一人控訴人のみに、ほぼ10年連続で他の入試業務をほとんどさせず日本人であれば誰でもできる留学生日本語試験採点を強要する行為は、偶然にはなされ得ず、控訴人への悪意によるものであると考えるほかはない。」(控訴理由書45頁)
ク 本件行為8について
(ア)原判決による第一審「(原告の主張)」欄への追加部分
「**及び**の行為は、極めて異常であって、業務上の必要性を欠き、業務遂行上の手段として不適当でもあった。また、控訴人を仲間外しとする悪意を認めることができるとともに、それが常態化しており、末端の教務課職員までもが自らの職分を超えて控訴人の人格を傷付けようとしたものである。さらに、**の控訴人に対する態度は、極めて敵対的で傲慢であることも、悪意をもって原稿の改ざんがされたことの証左である。」(原判決5頁)
(イ)上記(ア)の追加部分のうち、「**及び**の行為は、極めて異常であって、業務上の必要性を欠き、業務遂行上の手段として不適当でもあった。」という部分は、前述の通り、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(8)「遺脱された主張1」の一部の若干の変更を加えた引用であるが、判決に影響を及ぼすことの明白な下線部の重要事実及びそれに関する上告人の主張が原判決においては遺脱されている(下線は引用者による)。したがって、原判決には判断遺脱の法令違反がある。
「被控訴人法学部教務課職員が、控訴人に何ら相談もなく控訴人の原稿を修正した行為、及び、目の前にいる控訴人にわざわざ朱の入った原稿を見えるようにしておきながら、控訴人に全く相談することなく控訴人の原稿の修正点についての検討を続行しようとした行為は、いずれも控訴人も交えて検討するのが常識であり、大学業務において通常のことであることから、社会通念からして極めて異常であり、原告を無視して原告の研究計画書に手を入れ、それについての検討を原告を交えずにすることに何ら業務上の必要性がなく、それが業務遂行上の手段として不適当な行為であることから業務上必要かつ相当な範囲を超えたものである。(準備書面5、27頁~28頁、陳述書、8頁)」(控訴理由書46頁)
(ウ)上記(ア)の追加部分のうち、「また、控訴人を仲間外しとする悪意を認めることができるとともに、それが常態化しており、」という部分は、前述の通り、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(8)「遺脱された主張2」の一部の若干の変更を加えた引用であるが、判決に影響を及ぼすことの明白な下線部の重要事実が原判決においては遺脱されている(下線は引用者による)。したがって、原判決には判断遺脱の法令違反がある。
「被控訴人法学部教務課職員が、控訴人に何ら相談もなく控訴人の原稿を修正した行為及び目の前にいる控訴人に全く相談することなく控訴人の原稿の修正点についての検討を続行しようとした行為のいずれにおいても、控訴人に相談するというごく自然な選択肢を被控訴人法学部教務課職員が敢えて採らなかったという事実に控訴人を仲間外ししようという悪意が認められる。同時に、控訴人を仲間外しすることが法学部内で常態化していたことも確認される。(準備書面5、27頁、陳述書、8頁)」(控訴理由書46~47頁)
(エ)上記(ア)の追加部分のうち、「末端の教務課職員までもが自らの職分を超えて控訴人の人格を傷付けようとしたものである。」という部分は、前述の通り、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(8)「遺脱された主張3」の一部の若干の変更を加えた引用であるが、判決に影響を及ぼすことの明白な下線部の重要事実及びそれに関する上告人の主張が原判決においては遺脱されている(下線は引用者による)。したがって、原判決には判断遺脱の法令違反がある。
「教員の専門的学問につき何らの見識をも有さない大学職員が教員の研究計画書に教員に無断で朱を入れた上、それにつき当該教員の意見を聞くことなしに検討を続けるなどということが起こったということは、控訴人に対する徹底した組織的な誹謗中傷と仲間外しの結果、大学職員の職分を超えしたがって通常の大学業務の範囲を逸脱したそのような非常識な行為が味方のいない控訴人に対してだけは許されるという共通認識が醸成されており、末端の教務課職員までがその共通認識を前提として自らの職分を超え通常の業務範囲を逸脱してでも控訴人の人格を傷つけようという悪意をもってハラスメント行為に及んだことを意味する。(陳述書、8頁、控訴人本人調書、23頁)」(控訴理由書47頁)
(オ)上記(ア)の追加部分のうち、「**の控訴人に対する態度は、極めて敵対的で傲慢であることも、悪意をもって原稿の改ざんがされたことの証左である」という部分は、前述の通り、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(8)「遺脱された主張4」の一部の若干の変更を加えた引用であるが、判決に影響を及ぼすことの明白な下線部の重要事実及びそれに関する上告人の主張が原判決においては遺脱されている(下線は引用者による)。したがって、原判決には判断遺脱の法令違反がある。
「法学部教務課では、**と****が対応した。****の態度は控訴人に対し極めて敵対的かつ傲慢なもので、通常であれば「~して頂けますか?」というところを「~してもらえますか?」と言い放つという、若い職員の年配の教授に対する態度としては普通は考えられぬものである。このような態度は、被控訴人及び東洋大学法学部が常日頃から控訴人を一方的に自分らより下位に位置づけ、控訴人をさげすんでいることの証左である。打ち合わせの最後に当時の法学部教務課長である****が挨拶に来た。その際、**は変ににやにやしながら、控訴人をまじまじと見つめるという控訴人を小馬鹿にした態度を取った。法学部教務課の控訴人に敵対的な雰囲気は、当の改竄が悪意あるハラスメントであることを証すものである。(準備書面4,12頁)」(控訴理由書47頁)
ケ 本件行為9について
(ア)原判決による第一審「(原告の主張)」欄への追加部分
「同48頁21行目末尾に改行して、次のとおり加える。
「 フランス語とほかの言語との間で予算の格差を設け、悪意をもってこれを維持し、更に拡大することに業務上の必要性はなく、業務遂行上の手段として不適当でもあって、明白なハラスメントである。法学部において、控訴人には何をしてもよいという共通の了解の下、控訴人に不利益を与えるものでもある。また、被控訴人が控訴人に対して海外研修予算をつけることが可能であることを教示せず、立案や予算要求書提出を勧めることもしなかったことは、極めて異常であり、悪意のあるハラスメントであるというほかない。」」(原判決6頁)
(イ)上記(ア)の追加部分のうち、「フランス語とほかの言語との間で予算の格差を設け、悪意をもってこれを維持し、更に拡大することに業務上の必要性はなく、業務遂行上の手段として不適当でもあって、明白なハラスメントである」という部分は、前述の通り、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(9)「遺脱された主張1」の一部の若干の変更を加えた引用であるが、判決に影響を及ぼすことの明白な下線部の重要事実及びそれに関する上告人の主張が原判決においては遺脱されている(下線は引用者による)。したがって、原判決には判断遺脱の法令違反がある。
「フランス語予算と他言語予算との間に数10万から100万、200万に至る莫大な格差が10年間も維持されている場合、通常の大学業務の範囲内であれば、10年間の間にこの極端な不平等状態を是正しようという試みが法学部の方からなされているはずである。そのような試みが全くなされないままこれだけ大きな予算格差が10年間も維持された事実は、通常の大学業務の範囲を超えたものであり、
10年以上もの間フランス語のみに予算をつけず、フランス語と他言語との間の予算格差を維持することに何ら業務上の必要性がなく、それが業務遂行上の手段として不適当な行為であり、10年以上という期間が社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであることから、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものである。(準備書面5、29頁~30頁、陳述書、5頁)」(控訴理由書48頁)
(ウ)上記(ア)の追加部分のうち、「法学部において、控訴人には何をしてもよいという共通の了解の下、控訴人に不利益を与えるものでもある」という部分は、前述の通り、次に引用する控訴理由書第2章第2・1「遺脱された主張」(9)「遺脱された主張4」の一部の若干の変更を加えた引用であるが、判決に影響を及ぼすことの明白な下線部の重要事実が原判決においては遺脱されている(下線は引用者による)。したがって、原判決には判断遺脱の法令違反がある。
「これだけ大きな予算格差が10年間も維持された事実は、**教授らによる徹底した誹謗中傷と仲間外しにより、人間関係から切り離され味方がいないために何をしてもよい存在であるという共通の了解が形作られた控訴人をこの了解に基づいて通常の業務範囲を逸脱してでも貶め、不利益に陥らせようとする悪意なくしては考えられない。(陳述書、5頁)」(控訴理由書49頁)
(2)原審における上告人の主張部分の認定判断における具体的事実の遺脱
原判決は、「第2・3当審における控訴人の主張(補足の主張)」(原判決6~9頁)という部分で、第一審の訴訟手続の法令違反、本件行為1~9、そして安全配慮義務違反につき、原審における上告人の主張の結論部分だけを選択しこれを書き加えることによって、判決に影響を及ぼす重要な具体的事実とそれらについての上告人の主張を遺脱する数多くの判断遺脱を犯している。
ア 第一審の訴訟手続の法令違反について
(ア)原判決が摘示した原審における上告人の主張
「原審の裁判官らは、控訴人が代理人を選任せずに訴訟を追行していたことに乗じ、被控訴人に加担をして、尋問箇所について控訴人を欺き、違法な主尋問をし、一方的に争点を変更した。また、被控訴人側の人証に控訴人が反対尋問をする機会を設けないなど、原審の訴訟手続には、複数の法令違反があった。」
(イ)原判決による判断遺脱の法令違反
原判決による上告人の上記主張の摘示において、第一審で大須賀寛之裁判長が上告人本人尋問主尋問個所につき上告人を欺いた違法行為、第一審上告人本人尋問の主尋問における法令違反、第一審裁判官が判決で争点を変更した違法行為に関する判決に影響を及ぼす重要な具体的事実のすべて及びそれらに関する上告人の主張のすべてにつき(控訴理由書第1章第2~第4、6~35頁)、原判決は一切認定判断していない。したがって、当該摘示において、原判決は判断遺脱の法令違反を犯している。
イ 本件行為1について
(ア)原判決が摘示した原審における上告人の主張
「本件行為1は、職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、業務上の合理性及び必要性が全くなく、社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであって、法学部内において、控訴人に関わる重要な問題について控訴人を無視することにより、控訴人の人格及び名誉感情を侵害することに主眼を置いた不当な目的を有するものである。また、控訴人を標的として、フランス語教員人事を口実とする約15年にわたるフランス語教員の増減の過程の一契機でもあって、控訴人に対し、著しい継続的精神的圧力を加え、大きな精神的負担を感じさせるものである。その継続性からも、社会的相当性を欠いており、不法行為に当たる。」(原判決6~7頁)
(イ)原判決による判断遺脱の法令違反
上記主張は、原判決が、原審における上告人の以下の主張の一部に手を加えて引用したものである。
「上記(イ)~(カ)から、本件行為1は、職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、業務上の合理性及び必要性の全くないままに、また社会通念に照らして許容される範囲を超えて、法学部内で控訴人を、フランス語教員枠の転用という控訴人に関わる重要問題に関して、無視することにより、控訴人の人格及び名誉感情を侵害することに主眼をおいた不当な目的を有するものであり、控訴人を標的とし、フランス語教員人事を口実とした、平成21年以来15年の長きにわたるフランス語教員増減過程の一契機を成すという意味でも控訴人に甚だしい継続的精神的圧力を加え、大きな精神的負担を感じさせるものであり、当該背景事情の継続性からしても、社会相当性を全く欠いており、不法行為を構成するというほかはない。」(控訴理由書第2章第4・1(5)イ、75頁)
原判決の摘示においては、「上記(イ)~(カ)から」という部分が不当に削除されており、当該部分に記載された判決に影響を及ぼす重要な具体的事実およびそれらに関する上告人の主張につき(控訴理由書第2章第4・1(5)イ、73~75頁)、原判決は一切審理判断していない。したがって、当該摘示において、原判決には判断遺脱の法令違反がある。
ウ 本件行為2について
(ア)原判決が摘示した原審における上告人の主張
「本件行為2は、職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、業務上の合理性及び必要性が全くなく、社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであって、控訴人の個人的尊厳及び名誉感情を侵害することにより、控訴人に一定—の見識を備えた一人前の法学部教員として認められていないという屈辱感を感じさせることを通じて控訴人に精神的圧力を加えることを主眼とする不当な目的によるものであり、人格権侵害の不法行為に当たる。」(原判決7頁)
(イ)原判決による判断遺脱の法令違反
上記主張は、原判決が、原審における上告人の以下の主張の一部に手を加えて引用したものである。
「前記(2)イに明記された諸事情を鑑みるに、本件行為2は、職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、業務上の何らの合理性及び必要性をも欠き、社会通念に照らして許容される範囲を超え、控訴人の個人的尊厳及び名誉感情を侵害することにより、控訴人に一定の見識を備えた一人前の法学部教員として認められていないという屈辱感を感じさせることを通して控訴人に精神的圧力を加えることを主眼とするという不当な目的によるものであり、人格権侵害の不法行為を構成すると言うべきである。」(控訴理由書第2章第4・2(5)、79~80頁)
原判決の摘示においては、「前記(2)イに明記された諸事情を鑑みるに」という部分が不当に削除されており、当該部分に記載された判決に影響を及ぼす重要な具体的事実およびそれらに関する上告人の主張につき(控訴理由書第2章第4・2(2)イ、76~77頁)、原判決は一切審理判断していない。したがって、当該摘示において、原判決には判断遺脱の法令違反がある。
エ 本件行為3について
(ア)原判決が摘示した原審における上告人の主張
「本件行為3は、職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、業務上の合理性及び必要性が全くなく、社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであって、控訴人が法学部専任教員として当然に享受することができるはずの情報を控訴人に与えず、控訴人を大学の専任教員として通常に尊重しないことにより、控訴人の人格又は個人的尊厳及び名誉感情を侵害し、控訴人に精神的圧力を加えるという不当な目的によるものであり、人格権侵害の不法行為に当たる。」(原判決7頁)
(イ)原判決による判断遺脱の法令違反
上記主張は、原判決が、原審における上告人の以下の主張の一部に手を加えて引用したものである。
「上記(ア)~(カ)より、本件行為3は、職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、社会通念に照らして許容される範囲を超え、業務上の何らの合理性及び必要性をも欠き、仲間外しされていない状態であれば控訴人が法学部専任教員として当然享受してよいはずの情報を控訴人に与えず、控訴人を大学専任教員として通常に尊重しないことにより、控訴人の人格ないし個人的尊厳及び名誉感情を侵害し、控訴人に精神的圧力を加えるという不当な目的によるものであり、人格権侵害の不法行為を構成すると言うべきである。」(控訴理由書第2章第4・3(1)(キ)、82頁)
原判決の摘示においては、「上記(ア)~(カ)より」という部分が不当に削除されており、当該部分に記載された判決に影響を及ぼす重要な具体的事実およびそれらに関する上告人の主張につき(控訴理由書第2章第4・3(1)イ(ア)~(カ)、80~82頁)、原判決は一切審理判断していない。したがって、当該摘示において、原判決には判断遺脱の法令違反がある。
オ 本件行為4について
(ア)原判決が摘示した原審における上告人の主張
「本件行為4は、業務上の合理性及び必要性が全くなく、控訴人の人格及び名誉を侵害し、控訴人に精神的圧力を加えることによって、控訴人に精神的苦しみを与えることを主眼とした不当な目的によるものであり、社会的相当性を欠くものであるから、不法行為に当たる。」(原判決7頁)
(イ)原判決による判断遺脱の法令違反
上記主張は、原判決が、原審における上告人の以下の主張の一部に手を加えて引用したものである。
「上記(ア)(イ)から、平成19年に、履修者10名以上語学科目6コマ+教養演習1コマ計7コマという条件を守っていないことを理由として、控訴人の教養演習を潰した**、**、**らの行為は(被控訴人第1準備書面、8~9頁)、何ら業務上の合理性及び必要性を有しておらず、控訴人の人格及び名誉を侵害し、控訴人に精神的圧力を加えることによって、控訴人に精神的苦しみを与えることを主眼とした不当な目的によるものであると言うべきであり、社会相当性を欠いたものであることから、不法行為を構成する。」(控訴理由書第2章第4・4(3)イ(ウ)、88頁)
原判決の摘示においては、「上記(ア)(イ)から、平成19年に、履修者10名以上語学科目6コマ+教養演習1コマ計7コマという条件を守っていないことを理由として、控訴人の教養演習を潰した**、**、**らの行為は(被控訴人第1準備書面、8~9頁)」という部分が不当に削除されており、当該部分に記載された判決に影響を及ぼす重要な具体的事実およびそれらに関する上告人の主張につき(控訴理由書第2章第4・4(3)イ(ア)(イ)、87~88頁)、原判決は一切審理判断していない。また、控訴理由書第2章第4・4(2)イ(ウ)の次に引用する部分に明記された判決に影響を及ぼす具体的事実とそれに関する上告人の主張につき、原判決は一切審理判断していない。「12年の長きにわたり、控訴人に教養演習開講に関する情報を与えず、控訴人だけが教養演習を開講していない状況を維持し続ける行為は、明らかに社会通念の許容範囲を超えており、業務上の何らの合理性も必要性も有さぬものであり、法学部成員に対して当然認められるべき権利を控訴人にだけ拒むことにより、組織の成員としての控訴人の人格と名誉を侵害し、控訴人に対して継続的な圧力を加えることを主眼とした不当な目的によるものであることから、不法行為を構成するというべきである。」(控訴理由書86頁)したがって、当該摘示において、原判決には判断遺脱の法令違反があるというほかはない。
カ 本件行為5について
(ア)原判決が摘示した原審における上告人の主張
「本件行為5は、社会通念に照らし、組織の在り方に関する通常人の常識からすれば合理性を欠き、社会的相当性も欠くものであって、控訴人を仲間から外し、差別するものである。本件行為5は、通常の業務の範囲内や偶然では起こり得ないものであって、業務上の合理性及び必要性も全くなく、控訴人の人格及び名誉感情を傷付けると同時に、控訴人を法学部内において軽視されるべき地位に20年以上も置き続けることによって、控訴人の孤立を激化させ、控訴人に継続的な圧力を長期にわたり加え続けることによって、精神的負担及び精神的苦痛を与え続けることを主眼とした不当な目的によるものであり、不法行為に当たる。」(原判決8頁)
(イ)原判決による判断遺脱の法令違反
上記主張は、原判決が、原審における上告人の以下の主張の一部に手を加えて引用したものである。
「法学部のほとんどすべての専任教員が「長」のつく何らかの役職を経験している中、職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、控訴人にだけ20年以上も何らの役職にもつかせないという行為は、社会通念に照らし、組織のあり方に関する通常人の常識からすれば、合理性を欠き、控訴人に対する仲間外しや差別を結論せざるを得ないものであり、許容される範囲を大きく超えるものであると言うべきであり、社会通念上許されない社会的相当性を欠いたものであるというほかない。」(控訴理由書第2章第4・5(3)イ(ア)、91頁)
「当該行為は、通常業務の範囲内では起こり得ないものであり、何ら業務上の合理性及び必要性を有さないものである。しかも当該行為の継続期間が社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであり、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであることは明白である。」(控訴理由書第2章第4・5(3)イ(イ)、91頁)
「当該行為は、その継続期間の長さからしても偶然のものとはみなされ得ず、控訴人の人格及び名誉感情を傷つけると同時に、控訴人を法学部内において軽視されるべき位置に20年以上の長きにわたって置き続けることによって控訴人の孤立状態を激化させ、継続的な圧力を長期間にわたり控訴人に加え続けることにより、控訴人に精神的負担及び精神的苦痛を与え続けることを主眼とした不当な目的によるものである。」(控訴理由書第2章第4・5(3)イ(ウ)、91頁、下線は引用者による)
原判決の摘示においては、上告人の上記主張のうち2か所の下線部分が不当に削除されており、当該部分に記載された判決に影響を及ぼす重要な具体的事実およびそれらに関する上告人の主張につき、原判決は一切審理判断していない。したがって、当該摘示において、原判決には判断遺脱の法令違反があると言わざるを得ない。
キ 本件行為6について
(ア)原判決が摘示した原審における上告人の主張
「本件行為6は、職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、主査である控訴人の所見を副査の所見より下位に置き、審査結果報告書に全く掲載、反映をさせないというものであって、業務上の合理性及び必要性が全くなく、社会通念に照らして許容される範囲を超えるものである。本件行為6は、控訴人のフランス文学者としての経歴や名誉を無視し、控訴人の人格及び名誉を侵害することを通じて、控訴人に精神的圧力を加えることを主眼とする不当な目的によるものであって、不法行為に当たる。」(原判決8頁)
(イ)原判決による判断遺脱の法令違反
上記主張は、原判決が、原審における上告人の以下の主張の一部に手を加えて引用したものである。
「上記(イ)からして、職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、主査である控訴人の所見を副査のそれより下位に置いたり、審査結果報告書に全く掲載もせず反映もさせないという行為は、明らかに社会通念に反しており、また、何ら業務上の合理性も必要性も有さず、控訴人に対して、わざわざそのような社会通念に反し、通常業務を逸脱した行為を選択する以上、控訴人のフランス文学者としての経歴と名誉を無視し、控訴人の人格及び名誉を侵害することを通して、控訴人に精神的圧力を加えることを主眼とした不当な目的による行為であると言わざるを得ない。」(控訴理由書第2章第4・6(1)イ(ウ)、93頁、下線は引用者による)
原判決の摘示においては、「上記(イ)からして」という部分が不当に削除されており、当該部分に記載された判決に影響を及ぼす重要な上告人の主張につき(控訴理由書第2章第4・6(1)イ(イ)、92頁)、原判決は一切審理判断していない。したがって、当該摘示において、原判決には判断遺脱の法令違反がある。これに加えて、原判決は、上告人の主張の下線部分における上告人による事実認定の推認過程を不当に無視し、これによって上告人の主張につき誤った認定判断をしている。原判決は用いるべき経験則を用いなかったと言えるのであり、ここに原判決による経験則違反の違法がある。
ク 本件行為7について
(ア)原判決が摘示した原審における上告人の主張
「本件行為7は、職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、業務上の合理性及び必要性が全くなく、社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであって、留学生の日本語試験採点の業務に1 0年間の長きにわたって控訴人を縛りつけることによって、控訴人に屈辱感を味合わせ、控訴人の人格や名誉を侵害して大きな精神的苦痛を感じさせることを主眼とする不当な目的によるものであるから、不法行為に当たる。」(原判決8頁)
(イ)原判決による判断遺脱の法令違反
上記主張は、原判決が、原審における上告人の以下の主張の一部に手を加えて引用したものである。
「前記第3、2(7)ア、イ、ウに明示された状況で、職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、ほぼ10年連続で留学生日試験採点の仕事を東洋大学で控訴人のみに強要する行為は、10年連続という期間が社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであることに加え、何ら業務上の合理性及び必要性がなく、控訴人を人間関係から切り離しつつ控訴人を10年間という長きにわたって当該業務のみに縛り付けることによって、控訴人に屈辱感を味合わせ、控訴人の人格や名誉を侵害し、控訴人に継続的圧力を加え続けることによって、控訴人に大きな精神的苦痛を感じさせることを主眼とした不当な目的によるものと考えるほかはない。」(控訴理由書第2章第4・7(1)イ(イ)、95頁、下線は引用者による)
原判決の摘示においては、「前記第3、2(7)ア、イ、ウに明示された状況で」という部分が不当に削除されており、当該部分に記載された判決に影響を及ぼす重要な具体的事実およびそれらに関する上告人の主張につき(控訴理由書第2章第3、2(7)ア、イ、ウ、63~64頁)、原判決は一切審理判断していない。これに加えて、原判決の摘示においては、上告人の上記主張のうち2か所の下線部分が不当に削除されており、当該部分に記載された判決に影響を及ぼす重要な具体的事実およびそれらに関する上告人の主張につき、原判決は一切審理判断していない。したがって、当該摘示において、原判決には判断遺脱の法令違反がある。
また、原判決は、最初の下線部に認められる、留学生日本語試験の採点を「控訴人のみに強要」した事実を無視する判断遺脱を犯した上、一方で、「ほぼ10年連続で留学生日試験採点の仕事を東洋大学で控訴人のみに強要する行為は」という上告人の主張部分における主語を「本件行為7」にすり替え、他方で、2番目の下線部に認められる「10年連続という期間」という上告人の主張部分における主語を「本件行為7」にすり替えてしまっており、これにより上告人の主張を歪め、本来の上告人の主張と異なったものに変造した上で、これを上告人の主張として提出するといるのであるから、原判決が上告人の主張につき誤った認定判断をしていることは明白である。
ケ 本件行為8について
(ア)原判決が摘示した原審における上告人の主張
「本件行為8は、社会通念及び組織運営の常識に照らし、控訴人を交えて検討すべきであるにもかかわらず、教員の専攻につき何らの見識も有さない法学部教務課職員が職務上の地位・権限を逸脱・濫用してしたものであって、許容される範囲を超えるものであるから、不法行為に当たる。」(原判決9頁)
(イ)原判決による判断遺脱の法令違反
上記主張は、原判決が、原審における上告人の以下の主張の一部に手を加えて引用したものである。
「教員の専門的学問につき何らの見識をも有さない被控訴人法学部教務課職員が、職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、フランス文学専門の研究者であり、教授の地位にある控訴人に何ら相談もなく控訴人の原稿を修正した行為、及び目の前にいる控訴人にわざわざ朱の入った原稿を見えるようにしておきながら、控訴人に全く相談することなく控訴人の原稿の修正点についての検討を続行しようとした行為は、いずれも控訴人も交えて検討するのが社会通念からして、組織運営の常識として、相当であることから、社会通念に照らして極めて異常であり、通常人の許容する範囲を超えている。」
「上記行為は、控訴人も交えて検討するのが大学業務において通常のことであることから、通常の業務範囲を超えており、何ら業務上の合理性及び必要性を有するものではない。」(控訴理由書第2章第4・8(1)イ(ウ)(エ)、97頁、下線は引用者による)
原判決の摘示においては、上告人の上記主張のうち下線部分が不当に削除されており、当該部分に記載された判決に影響を及ぼす重要な具体的事実およびそれらに関する上告人の主張につき、原判決は一切審理判断していない。
これに加えて、原判決は、以下に引用する判決に影響を及ぼす重要な具体的事実およびそれに関する上告人の主張につき全く審理判断していない。
「当該行為のいずれにおいても、控訴人に相談するという、社会通念からしても、通常業務のあり方からしても、相当である選択肢を被控訴人法学部教務課職員が敢えて採らず、わざわざ社会通念からしても通常業務のあり方からしても相当でない当該行為を選択したという事実から、当該行為が、控訴人を無視し、控訴人の教授としての名誉を踏みにじることで、控訴人が法学部内で長期にわたって仲間外しされた極めて弱い立場に置かれていることを強調することによって控訴人の人格と名誉感情を侵害し、控訴人に精神的圧力を加えることを通して、精神的苦痛を与えることを主眼とした不当な目的によるものである事実が推認される。また、法学部教務課職員が社会通念及び通常の業務範囲の許容し得る範囲を大きく超えて、当該行為に及ぶことが可能であり、当該行為を可能にする状況が法学部にあったという事実から、控訴人を仲間外しし、孤立化させ、控訴人に有形無形の継続的圧力を加えることが法学部内で常態化していたことも確認される。」(控訴理由書第2章第4・8(1)イ(オ)、97~98頁)
したがって、当該摘示において、原判決には判断遺脱の法令違反がある。
コ 本件行為9について
(ア)原判決が摘示した原審における上告人の主張
「職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、業務上の合理性及び必要性が全くなく、社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであって、控訴人を長期にわたり仲間から外し、差別するものである。本件行為9は、控訴人の人格及び名誉を侵害し、控訴人に継続的な精神的圧力をかけることを主眼とする不当な目的によるものであるから、不法行為に当たる。」(原判決9頁)
(イ)原判決による判断遺脱の法令違反
上記主張は、原判決が、原審における上告人の以下の主張の一部に手を加えて引用したものである。
「職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、フランス語予算と他言語予算との間に数10万から100万、200万に至る莫大な格差を10年間も維持するという行為は、社会通念からして、通常の組織であれば、たとえ控訴人が必要資料等を提出していなくても、教授会その他の会議において、あるいは個人的に、フランス語担当専任教員である控訴人に格差を是正する提案をすることが相当であるところ、そのような提案が10年間にわたって一切なかったのであるから、社会通念に照らして通常人の許容し得る範囲を大きく超えるものであり、社会相当性を欠いているというほかはない。」
「当該行為は、明らかに通常業務の範囲を大きく超えており、何ら業務上の合理性及び必要性を有するものではない。」
「当該行為は、控訴人を同じ組織に属する法学部成員の一人として他の成員たちが認め、控訴人の法学部成員としての権利を認め、控訴人の人格と名誉を尊重しているのなら、発生し得ないものであることから、控訴人を法学部内で長期間にわたって仲間外しし、人間関係から切り離し、控訴人の人格と名誉を侵害し、控訴人に継続的な精神的圧力をかけることを主眼とした不当な目的によるものであると言うべきである。」(控訴理由書第2章第4・9(1)イ(イ)~(エ)、99~100頁、下線は引用者による)
原判決の摘示においては、上告人の上記主張のうち2か所の下線部分が不当に削除されており、当該部分に記載された判決に影響を及ぼす重要な具体的事実およびそれらに関する上告人の主張につき、原判決は一切審理判断していない。
これに加えて、原判決は、以下に引用する判決に影響を及ぼす重要な具体的事実およびそれに関する上告人の主張につき全く審理判断していない。
「「予算を要求する者が計画書や予算要求書、アンケート等を提出」すべきことが、教授会や語学会議その他の会議で周知されたこともなく、10年間の間にそれが控訴人に伝えられたことも一切なかったという事実は、仲間外しや差別等のパワハラがなく通常に機能している組織では起こり得ないことであることから、社会通念の許容する範囲及び通常の業務範囲を超えており、社会相当性を欠いたものである。」(控訴理由書第2章第4・9(1)イ(オ)、100頁)
「被控訴人は、10年以上も続く予算格差を是正する試みを全くせず、そればかりか、海外研修に専任教員の付き添いを急遽義務付けてフランス語海外研修実現を困難にしたり、予算格差を是正するためにフランス語予算を増やして欲しいという控訴人の度重なる訴えを拒否あるいは無視し、「2022年度法学部予算執行要領」によって教材費によるDVD購入を禁じるなど、悪意をもって予算格差を維持あるいは拡大することを図った。(甲56)」(控訴理由書第2章第4・9(2)イ(イ)、101頁)
したがって、当該摘示において、原判決には判断遺脱の法令違反がある。
サ 安全配慮義務違反について
(ア)原判決が摘示した原審における上告人の主張
「令和3年4月の人事異動によって、**がハラスメント防止対策委員となったが、調査・苦情処理委員会がハラスメント防止対策委員から独立していないことが判明した。そこで、控訴人は、**が調査・苦情処理委員会に関わっている状態では公正な運営ができないことは明らかであるとして、人事部長に対し、ヒアリングの日程を決める必要はない旨述べた。これらの事実によれば、被控訴人が本件規程を踏まえた対応をしていなかったことは明らかであり、安全配慮義務に違反した。」(原判決9頁)
(イ)原判決による判断遺脱の法令違反
上記上告人の主張は、原審において初めてなされたものではない。したがって、原判決の上記摘示には認定判断の誤りがある。
当該主張は既に第一審弁論においてなされたものであり、上告人は原審弁論において、第一審判決における以下3点の判決の結果に影響を及ぼす事実の遺脱を指摘している。
「令和3年4月の人事異動で、控訴人にハラスメントを繰り返している加害者である当時法学部長の****教授がハラスメント防止委員となる。(甲85、甲86、甲87の1、2)」
「令和3年9月のハラスメント調査・苦情処理委員会第一回事情聴取で、****弁護士が、「学校法人東洋大学ハラスメントの防止等に関する規定」第18条第7項によれば独立が保証されなくてはならないはずのハラスメント調査・苦情処理委員会が当時法学部長であった****が委員となっているハラスメント防止委員会に「紐付け」であることを明かす。(甲88)」
「令和3年10月、****が ハラスメント調査苦情処理委員会に関わっている状態でハラスメント調査苦情処理委員会の公正な運営が不可能であることは明らかであるという理由により、控訴人が、これ以上ヒアリングの日程は決めないでけっこうであると**人事部長に告げる。(甲89の1,2)」(控訴理由書第2章第3・1(2)「「本件訴訟に至る経緯」に関する事実の遺脱」ア~ウ、52頁)
原判決が摘示した上記(ア)の主張は、原判決が、原審における上告人の以下の主張の一部に手を加えて引用したものである。
「令和3年4月の人事異動で、控訴人にハラスメントを繰り返している加害者である当時法学部長の****教授がハラスメント防止対策委員となり、しかも、令和3年9月のハラスメント調査・苦情処理委員会第一回事情聴取において、上記規定に反し、ハラスメント調査・苦情処理委員会が**が委員を務めるハラスメント防止対策委員から独立していない事実が判明したため、令和3年10月、****がハラスメント調査苦情処理委員会に関わっている状態でハラスメント調査苦情処理委員会の公正な運営が不可能であることは明らかであるという理由により、控訴人が、これ以上ヒアリングの日程は決めないでけっこうであると**人事部長に告げた、という事実がある。(甲85、甲86、甲87の1、2、甲88、甲89の1、2)」(控訴理由書第2章第4・11「安全配慮義務違反について」(2)イ(イ)、105~106頁、下線は引用者による)
原判決の摘示においては、上告人の上記主張のうち2か所の下線部分が不当に削除されており、当該部分に記載された判決に影響を及ぼす重要な具体的事実につき、原判決は一切審理判断していない。つまり、ハラスメント防止対策委員となった**が控訴人にハラスメントを繰り返している加害者である当時法学部長であった事実、及び令和3年9月のハラスメント調査・苦情処理委員会第一回事情聴取で、****弁護士が、「学校法人東洋大学ハラスメントの防止等に関する規定」第18条第7項によれば独立が保証されなくてはならないはずのハラスメント調査・苦情処理委員会が当時法学部長であった****が委員となっているハラスメント防止委員会に「紐付け」であることを明かした事実につき、原判決は一切審理判断していないのである。したがって、原判決に判断遺脱の法令違反があることは明白である。
(3)パワハラ・不法行為の有無等に関する原判決の判断における具体的事実の遺脱
ア 原判決の判示
原判決は、「第3当裁判所の判断」、2「当審における控訴人の主張等に対する判断」欄において、次のように判示する。
「(1)控訴人は、上記のとおり、原審の訴訟手続には、複数の法令違反があったとの主張をする。
しかし、本件記録を精査してもなお、原審の訴訟手続につき、控訴人主張の法令違反の事実を認めることはできない。控訴人の主張は、独自の理解に基づき原審の訴訟手続を論難するものにすぎず、採用することができない。
(2)また、控訴人は、上記のとおり、本件各行為につき、業務上の合理性及び必要性が全くなく、社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであるなどとして、悪意による不法行為に当たる等との主張をする。
![]() しかし、本件各行為の行われた経緯は補正の上引用した原判決が認定をしたとおりであり、そのほか本件全証拠によっても、本件各行為につき業務上の合理性及び必要性を欠き、社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであると認めることはできない。本件各行為については、当該各行為があったとは認めることができず、行為があったと認めることができるものについても、不法行為の主張としては主張自体失当であり、又は控訴人の人格権を違法に侵害するものとは認めることはできないものであるから、被控訴人又は被控訴人の教職員による控訴人に対する不法行為があったものということはできず、また、被控訴人による安全配慮義務違反の事実を認めることもできないことは、いずれも補正の上引用した原判決が認定、説示をしたとおりである。控訴人の主張は、実質、原審における主張を繰り返し、又は独自の理解を述べるものにすぎないのであって、補正の上引用した原判決の認定、説示に照らし、採用することができない。
しかし、本件各行為の行われた経緯は補正の上引用した原判決が認定をしたとおりであり、そのほか本件全証拠によっても、本件各行為につき業務上の合理性及び必要性を欠き、社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであると認めることはできない。本件各行為については、当該各行為があったとは認めることができず、行為があったと認めることができるものについても、不法行為の主張としては主張自体失当であり、又は控訴人の人格権を違法に侵害するものとは認めることはできないものであるから、被控訴人又は被控訴人の教職員による控訴人に対する不法行為があったものということはできず、また、被控訴人による安全配慮義務違反の事実を認めることもできないことは、いずれも補正の上引用した原判決が認定、説示をしたとおりである。控訴人の主張は、実質、原審における主張を繰り返し、又は独自の理解を述べるものにすぎないのであって、補正の上引用した原判決の認定、説示に照らし、採用することができない。
このほか控訴人が主張をする諸事情を考慮してもなお、当裁判所の上記判断は左右されない。」(原判決12頁)
イ 上記判示における法令違反
パワハラや不法行為の有無に関する上記判示において、原判決は、判決に影響を及ぼす上告人の具体的主張や具体的事実につき一切審理判断することなく、上告人の主張を排斥しているのであるから、上記判示が判断遺脱の法令違反を犯していることは疑い得ない。
以下、ウにおいて第一審の訴訟手続の法令違反について、エにおいて安全配慮義務違反について、それぞれ詳述し、本件行為1~9及びパワハラの長期にわたる継続性と大規模な組織性については、以下4において詳述する。
ウ 第一審の訴訟手続の法令違反について
(ア)原判決の判示
「控訴人は、上記のとおり、原審の訴訟手続には、複数の法令違反があったとの主張をする。
しかし、本件記録を精査してもなお、原審の訴訟手続につき、控訴人主張の法令違反の事実を認めることはできない。控訴人の主張は、独自の理解に基づき原審の訴訟手続を論難するものにすぎず、採用することができない。」(原判決12頁)
(イ)上記判示における法令違反
(ア)原判決の上記判示において、第一審で大須賀寛之裁判長が上告人本人尋問主尋問個所につき上告人を欺いた違法行為、第一審上告人本人尋問の主尋問における夥しい法令違反、第一審裁判官が判決で争点を変更した違法行為に関する判決に影響を及ぼす重要な具体的事実のすべてにつき、及びそれらに関して法令違反及び憲法違反を主張する上告人の主張のすべてにつき(控訴理由書第1章第2~第4、6~35頁)、原判決は一切審理判断せず、具体的な理由を一切挙げぬまま、上告人の主張を排斥している。したがって、当該判示において、原判決は判断遺脱の違法及び法令解釈適用を誤った違法を犯している。
(イ)原判決は、第一審で大須賀寛之裁判長が上告人本人尋問主尋問個所につき上告人を欺いた違法行為につき、第一審第3回弁論準備手続において、大須賀寛之裁判長が控訴人に陳述書にアンダーラインを引くように指示し、そのアンダーライン部分を控訴人本人尋問で質問すると確約した事実を証す上告人のメモ(甲81)、実際にアンダーラインを引いてある陳述書(甲80)などの証拠、第一審上告人本人尋問の主尋問における夥しい法令違反につき、第一審第2回口頭弁論におけるすべての質問が記載された調書、第一審裁判官が判決で争点を変更した違法行為につき、第一審弁論準備手続終結の際に読み上げられた争点を記載した上告人のメモ(甲82)、第一審第2回口頭弁論で読み上げられた争点を記載した上告人の妻のメモ(甲83)などの証拠につき全く検討せずに、上告人の請求を排斥しているのであるから、原判決には採証法則に反する法令違反がある。
エ 安全配慮義務違反について
(ア)原判決の判示
上記アに引用した原判決の判示には、「被控訴人による安全配慮義務違反の事実を認めることもできない」とある。
(イ)上記判示における法令違反
前記2(2)サ(イ)に明記した通り、原判決の上記判示は、原審における上告人の主張に関して判断遺脱の違法を犯した誤った認定判断に基づくものであり、全く失当であるというほかはない。すなわち、前述の通り、ハラスメント防止対策委員となった****が控訴人にハラスメントを繰り返している加害者である当時法学部長であった事実、及び令和3年9月のハラスメント調査・苦情処理委員会第一回事情聴取で、****弁護士が、「学校法人東洋大学ハラスメントの防止等に関する規定」第18条第7項によれば独立が保証されなくてはならないはずのハラスメント調査・苦情処理委員会が当時法学部長であった****が委員となっているハラスメント防止委員会に「紐付け」であることを明かした事実につき、原判決は一切審理判断していないのである。
パワハラ加害者を上告人のハラスメント申立て直後にハラスメント防止委員とすれば、ハラスメント防止委員会が、上告人に対するパワハラを解決すべき正常に機能しないこと、したがって被上告人東洋大学が上告人に対するパワハラを解決することによって安全配慮義務を果たすことを怠った事実は、経験則からして容易に推認される。また、ハラスメント調査・苦情処理委員会が****が委員となっているハラスメント防止委員会に「紐付け」である事実から、東洋大学が「学校法人東洋大学ハラスメントの防止等に関する規定」第18条第7項違反という学内規則違反を犯しつつハラスメント調査・苦情処理委員会が正当に機能しないようにすることにより、上告人に対するパワハラへの正当な対応を怠り、上告人に対する安全配慮義務を果たすことを怠った事実も経験則からして容易に推認されるところである。したがって、認定すべき重要事実を認定せず、用いるべき経験則を用いずに、しかも何ら具体的な事実や上告人の具体的な主張につき審理判断することなく、被上告人による安全配慮義務違反の事実を認めることができないとして、上告人の請求を排斥した原判決の上記判示には、判決に影響を及ぼす判断遺脱の法令違反、経験則違反の法令違反、及び法令解釈適用を誤った違法がある。
以上に加え、原判決は、調査・苦情処理委員会の独立と公正を定める「学校法人東洋大学ハラスメントの防止等に関する規定」第18条第7項(甲84)、東洋大学が、法学部長****を新たにハラスメント防止対策委員とした事実を証すメール(甲85)、控訴人が、法学部長****を新たにハラスメント防止対策委員としたことにつき、ハラスメント相談室に抗議し、**をハラスメント防止対策委員会から外すように要請したメール(甲86)、控訴人が、法学部長****を新たにハラスメント防止対策委員としたことにつき、人事部長***に抗議し、**をハラスメント防止対策委員会から外すように要請した事実を証す電話音声記録(甲87の1)、被控訴人弁護士の****が、上告人が事情聴取をビデオ録画することの可否をハラスメント調査・苦情委員会に相談すると主張し、ハラスメント調査・苦情委員会が**のいるハラスメント防止対策委員会に「紐づけ」であると言明した事実を証す録画ビデオ(甲88)などの判決に影響を及ぼす重要な証拠につき全く検討することなく、被上告人による安全配慮義務違反の事実を認めることもできないなどと言い、上告人の請求を排斥するのであるから、原判決は、採用すべき証拠を採用していないと言え、原判決には、採証法則に反する法令違反がある。
3 小括
上記1及び2から明らかなように、原判決は、「引用」部分においても、それ以外の部分においても、重要な具体的事実やそれら具体的事実に関する上告人の主張につき全く認定判断及び審理判断しないということに存する夥しい数の判断遺脱の法令違反を犯していることから、具体的な理由を全く欠いたものであると言え、判決主文を導き出すための理由の一部が欠けていると言わざるを得ず、原判決に、民訴法312条2項6号に掲げる絶対的上告理由としての理由の不備があることは疑い得ない(上告理由4)。
4 パワハラ行為の発生した状況や文脈及びパワハラ行為の程度、継続期間、頻度、反復性等の様態に関わる具体的事実についての判断遺脱と理由不備
とりわけパワハラや不法行為の有無に関する原判決の審理判断の著しい特徴として、パワハラや不法行為の有無に関する判断において、原判決は、パワハラ行為の発生した状況や文脈及びパワハラ行為の程度、継続期間、頻度、反復性等の様態に関わる重要な具体的事実につき、一切審理判断していない。つまり、原判決の判断枠組みは、パワハラ行為の不法行為性を検討するにあたって考慮することが必要不可欠である、パワハラ行為の発生した状況や文脈及びパワハラ行為の程度、継続期間、頻度、反復性等の様態に関わる重要な具体的事実の検討を全く欠いたまま、業務上の合理性及び必要性があるかどうか、社会通念に照らして許容されるかどうか等について結論を出すというものであり、かような判断枠組みを用いてパワハラ及び不法行為の有無が問題になる本件各行為について判決結果を導く原判決には、理由の本質的部分が欠けていると考えざるを得ない。
(1)本件行為1~9
ア 本件行為1
(ア)原判決の判示
原判決は、前記2(3)アに引用した判示(原判決12頁)において、「しかし、本件各行為の行われた経緯は補正の上引用した原判決が認定をしたとおりであり、そのほか本件全証拠によっても、本件各行為につき業務上の合理性及び必要性を欠き、社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであると認めることはできない」と述べ、「被控訴人又は被控訴人の教職員による控訴人に対する不法行為があったものということはでき」ないと結論付ける。
(イ)上記判示における法令違反
まず、「補正」という名のもとでの判断遺脱部分の追加が法令違反であり憲法違反であること、第一審判決を不当に「引用」することにより、本件行為1~9に関して第一審判決が犯した複数の法令違反につき原判決が判断遺脱の違法を犯していることは前述の通りである。次に、原判決は、「本件各行為につき業務上の合理性及び必要性を欠き、社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであると認めることはできない」と判示するが、どのような具体的事実を根拠にそのように断言するのか、原判決が重要な具体的事実を全く検討しないまま結論を出している以上、全く不明である。このような不正な判示に至ったのは、前述した通り、原判決が原審における上告人の主張部分の認定判断において、重要な具体的事実及びそれに関する上告人の主張につき全く認定判断しない判断遺脱の違法を犯したからである(前記2(2))。本件行為1~9について、具体的に何が業務上の合理性及び必要性であり、何が社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであるかを検討すべきであるのに、原判決はそのような検討を一切行なっていないのであるから、原判決の上記判示は具体性を欠いた全く無意味なものであり、全く理由を欠いたものとなっているのである。
前記2(2)イ(イ)に、本件行為1に関する原審における上告人の主張についての認定判断において「上記(イ)~(カ)から」という部分(控訴理由書第2章第4・1(5)イ、73~75頁)が不当に削除されていることを指摘した。以下に当該部分を控訴理由書から引用する。
「(イ)平成21年の*****の法学部フランス語専任教員としての採用、平成27年の***枠の政治学教員枠への転用、令和5年のフランス語担当非常勤講師の新規採用、そして令和6年の*****のフランス語担当専任教員(助教)としての採用(甲101,甲102)のすべてのフランス語教員人事を通して、フランス語教員の増減はフランス語履修者数の増減と全く相関関係のないことから、本件行為1がフランス語履修者の減少によるものではないこと、したがって、本件行為1に業務上の合理性及び必要性が全くないことは明白である。」(控訴理由書73頁)
本件行為1の不法行為性につき判断する際にまず検討すべき問題点は、***教員枠の政治学教員枠への転用の根拠として、被上告人が第一審弁論で主張した通り、法学部のフランス語履修者減があるのかどうかという点である。もし、当該転用の理由がフランス語履修者減であるのなら、本件行為1は業務上の合理性及び必要性を有するものであることになる。ところが、控訴理由書の上記引用から明らかであるように、とりわけ令和6年に被上告人が、フランス語履修者増のないところ法学部フランス語専任教員を雇用し、それに加えて非常勤講師3名を雇う大幅なフランス語教員増を敢行し上告人の担当授業をすべて奪った事実も鑑みるに、「フランス語教員の増減はフランス語履修者数の増減と全く相関関係のないことから、本件行為1がフランス語履修者の減少によるものではないこと、したがって、本件行為1に業務上の合理性及び必要性が全くないことは明白である」。
控訴理由書の上記引用部分に続く部分は以下の通りである。
「(ウ)本件行為1に業務上の合理性及び必要性がなく、通常の業務範囲内の合理的な動機・目的が全く見当たらないことから、本件行為1は、法学部で唯一のフランス語専任教員でありフランス語について、及びフランス語教員人事についてそれ相応の見識を有する控訴人に、職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、フランス教員にとっての重大問題であるフランス語教員人事につき全く相談しないことにより、控訴人を無視し、控訴人の見識を不当に否定することを通して、控訴人の名誉感情及び個人的な尊厳を侵害すると同時に、他の語学担当専任教員が複数であるところ、フランス語担当専任教員だけを控訴人一人にして控訴人を差別し孤立させ無力化し、フランス語劣遇に対する抵抗力をなくさしむることにより、フランス語劣遇を通して控訴人に圧力をかけることを容易にし、ただでさえ法学部内で孤立し精神的に隔離された状況にある控訴人に有形無形の圧力を加え、精神的負担を与えること自体に主眼をおく不当な目的によるものであると考えるほかはない。」(控訴理由書73頁)
上記引用を要約すると、本件行為1に業務上の合理性及び必要性がなく、通常の業務範囲内の合理的な動機・目的が全く見当たらない事実から、経験則により、本件行為1が上告人に圧力を加え精神的負担を与えること自体に主眼をおく不当な目的によるものである事実が容易に推認されるということである。
以上で、本件行為1に何ら業務上の合理性及び必要性がなく、上告人に圧力を加え精神的負担を与えるという不当な目的を有するものであることが証明された。次に、本件行為1が社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであるか否かについて確認するために、控訴理由書の上記引用部分に続く部分を以下に引用する。
「(エ)法学部で唯一のフランス語担当専任教員である控訴人に全く相談せず、全く無視して、フランス語教員枠を転用するというごときフランス語教員にとって重大な決定をするという行為は、通常業務の範囲内で起こることではなく、したがって何ら業務上の合理性及び必要性を有するものではなく、社会通念に照らしても、組織運営の常識からして、控訴人の人格及び名誉を尊重する通常の組織内で起こるべき事態ではないことから、社会通念上の許容範囲を大きく超えるものであり、社会相当性を欠いたものである。
(オ)本件行為1は、大学設置基準第13条に違反する法令違反でもあり、その意味でも、通常業務の範囲を超えており、何ら業務上の合理性及び必要性を有するものではなく、社会通念に照らしても、通常人の許容し得る範囲を大きく超えた社会相当性を欠いたものである。
(カ)本件パワハラの総体は、平成14年に始まり、平成20年の****法学部教授の法学部長就任とともに激化し、現在まで継続されているものである。平成14年、平成16年、平成27年に東洋大学法学部教授による控訴人に対する極めて侮辱的なセクシャルハラスメント発言があったことから(訴状、16~17頁)、また令和3年以降の控訴人が「付随的ハラスメント」とした複数のパワハラ行為があったことから(準備書書面5,陳述書)、被控訴人法学部において控訴人の人格及び名誉の侵害が極めて長期間にわたって継続していた事実が容易に推認される。フランス語教員人事に限っても、控訴人の人格及び名誉感情の侵害は、平成20年以来現在に至るまで継続されているものであり、法学部唯一のフランス語専任教員である期間の長い控訴人を継続的な精神的圧力による負担を感じざるを得ない状態に長期間にわたって置き続けるものであり、社会的通念に照らして許容し得る範囲を超えているとしか言いようがない。本件行為1もまた、これを孤立させて考えるのではなく、東洋大学法学部によるフランス語教員人事を口実とした控訴人の個人的尊厳及び名誉感情を侵害することを目的とする長期間にわたる過程の一契機として目されるべきものであり、法学部内で長期間にわたって継続的な精神的圧力を感じざるを得ない状況に置かれ続けている控訴人にさらなる精神的苦痛を感じさせることを目的としたものと考えるべきである。」(控訴理由書74~75)
上記の控訴理由書の記述から、本件行為1が社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであるであるか否かについての上告人の主張は3点に要約される。すなわち、1.法学部で唯一のフランス語担当専任教員である控訴人に全く相談せず、全く無視して、フランス語教員枠を転用するというごときフランス語教員にとって重大な決定をするという行為は、成員の人格及び名誉を尊重する通常の組織内で起こるべき事態ではないことから、社会通念上の許容範囲を大きく超えるものであり、社会相当性を欠いたものであるということ、2.本件行為1のごとく法令違反である行為は、通常業務の範囲を超えており、社会通念に照らしても、通常人の許容し得る範囲を大きく超えた社会相当性を欠いたものであるということ、3.フランス語教員人事における上告人の人格及び名誉感情の侵害は、平成20年以来現在に至るまで継続されているものであり、法学部唯一のフランス語専任教員である期間の長い控訴人を継続的な精神的圧力による負担を感じざるを得ない状態に長期間にわたって置き続けるものであり、社会的通念に照らして許容し得る範囲を超えているということ、以上3点である。
以上から、本件行為1が何ら業務上の合理性及び必要性もなく、上告人の人格と名誉を侵害することにより上告人に圧力を加え精神的負担を与えるという不当な目的を有するものであり、また社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであることは明白である。このような行為が職務上の地位・権限を逸脱・濫用したものであることは言うまでもない。したがって、原判決の判示とは全く逆に、本件行為1が被上告人法学部による上告人に対する不法行為を構成することは疑い得ない。
上記から明らかであるように、本件行為1に関する原審における上告人の主張についての認定判断において「上記(イ)~(カ)から」という部分を原判決が不当に削除せず、控訴理由書第2章第4・1(5)イ(イ)~(カ)(73~75頁)につき正当に審理判断していれば、本件行為1が不法行為ではないなどという不正な結論に達するはずはなかったのである。したがって、重要な具体的事実とそれらから経験則による推認を経て不法行為の存在を推認する上告人の主張につき全く認定判断及び審理判断することなく、不法行為はないなどとし、上告人の主張を排斥した原判決の判示には、判決結果に影響を及ぼす判断遺脱の法令違反、それに加え、用いるべき経験則を用いていないことから、経験則違反の法令違反、及び法令解釈適用を誤った違法がある。
(ウ)原判決による第一審「当裁判所の判断」欄の修正部分
前述の通り、第一審判決の極めて不当な書き換えによって法令違反を犯している第一審「当裁判所の判断」欄の原判決による修正部分を以下に再び引用する。
「また、控訴人は、本件行為1が大学設置基準に違反するものであって、職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、業務上の合理性及び必要性が全くなく、社会通念に照らして許容される範囲を超える等との主張をするが、上記アにおいて認定をした諸事情に照らし、本件行為1が職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、業務上の合理性及び必要性を欠くとも、社会通念に照らして許容される範囲を超えるとも認めることはできない。」(原判決10頁)
(エ)上記判示における法令違反
前述の通り、本件行為1は、大学設置基準第13条に違反する法令違反である。法令違反である行為が、通常業務の範囲を超えており、何ら業務上の合理性及び必要性を有するものではなく、社会通念に照らして通常人の許容し得る範囲を大きく超えた社会相当性を欠いたものであることは自明である。上記判示に従うならば、法令違反を構成する行為が大学の通常業務の範囲内のものであり、業務上の合理性及び必要性を有するものであり、社会通念に照らして通常人の許容し得る範囲内のものであることになるが、これは極めて不合理である。上記判示は極めて不合理なものというほかはない。原判決の上記判示は、第2、1(1)カにおいて指摘した複数の法令違反に加えて、用いるべき経験則を用いることなく、上告人の主張を排斥したのであるから、判決結果に影響を及ぼす経験則違反の法令違反を犯している。
イ 本件行為2
(ア)原判決の判示
原判決は、前記2(3)アに引用した判示(原判決12頁)において、「しかし、本件各行為の行われた経緯は補正の上引用した原判決が認定をしたとおりであり、そのほか本件全証拠によっても、本件各行為につき業務上の合理性及び必要性を欠き、社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであると認めることはできない」と述べ、「被控訴人又は被控訴人の教職員による控訴人に対する不法行為があったものということはでき」ないと結論付ける。
(イ)上記判示における法令違反
前記2(2)ウ(イ)に、本件行為2に関する原審における上告人の主張についての認定判断において「前記(2)イに明記された諸事情を鑑みるに」という部分(控訴理由書第2章第4・2(2)イ、76~77頁)が不当に削除されていることを指摘した。以下に当該部分を控訴理由書から引用する。
「 イ 判示の違法性
(ア)原審は、第2、1(2)ア及びイにおける控訴人の主張を不当に無視し、これについて全く検討していない。したがって、判決に影響を及ぼすことが明らかな上記2点の主張を全く検討せずに控訴人の主張を排斥する当該判示の審理判断には、判断遺脱、審理不尽、理由不備の違法があると言わざるを得ない。
(イ)原稿に問題がある場合、原稿作成者にその旨連絡するというのが、社会通念に照らして、組織運営の常識として、唯一妥当な対応である。
(ウ)原稿に問題がある場合に、原稿作成者に全く連絡せず別のテクストを掲載するという行為は、通常、組織内で相手を一人前の人間ないし組織の構成員として認め、相手の人格を尊重している場合には発生し得ない。このような行為は、本件行為2の場合、控訴人を一定の見識を備えた一人前の大学教員として認めず、控訴人の人格的尊厳や名誉感情を尊重していないから、起こる行為である。したがって、当該行為は、控訴人を一定の見識を備えた一人前の大学教員として認めず、控訴人の人格的尊厳や名誉感情を侵害するものであり、社会通念上容認されるべきではない、社会相当性を欠いた行為である。
(エ)原稿に問題がある場合に、原稿作成者に全く連絡せず別のテクストを掲載するという行為は、通常業務の範囲内で起こることではなく、業務上何らの合理性も必要性も有さないものである。」(控訴理由書第2章第4・2(2)イ、76~77頁)
本件行為2の不法行為性につき判断する際にまず検討すべき問題点は、被上告人が主張するように上告人の提出原稿に問題があるということを事実として仮定した場合に、その仮定された事実から経験則によってどのような事実が認定されるか、という点である。そこで、上記引用(イ)にあるように、提出原稿に問題がある場合、原稿作成者にその旨連絡するというのが、社会通念に照らして、組織運営の常識として、唯一妥当な対応であるという事実が認定される。そこから、上記引用(ウ)にあるように、原稿に問題がある場合に、原稿作成者に全く連絡せず別のテクストを掲載するという行為は、通常、組織内で相手を一人前の人間ないし組織の構成員として認め、相手の人格を尊重している場合には発生し得ない、という事実が帰結する。したがって、本件行為2のごとき行為が発生した場合には、原稿提出者を一定の見識を備えた一人前の大学教員として認めず、控訴人の人格的尊厳や名誉感情を尊重していないという事実が容易に推認される。その結果、本件行為2が、上告人を一定の見識を備えた一人前の大学教員として認めず、上告人の人格的尊厳や名誉感情を侵害するものであり、社会通念上容認されるべきではない、社会相当性を欠いた行為であるという事実が認定されるのである。また、原稿に問題がある場合に、原稿作成者に全く連絡せず別のテクストを掲載するという行為が業務上何らの合理性も必要性も有さないものであることも疑い得ない。
次に、上記引用部分に続く部分を引用する。
「(オ)**と**は、原稿作成者の原稿を無視し原稿作成者に全く連絡せず別のテクストを掲載するという、通常の業務を逸脱しており、社会通念上も許容し得る範囲を超えた行為を、控訴人に対して、控訴人に連絡する、字数を増やす等、可能ないくつかの選択肢のなかから選択した。
(カ)選択は常に意図的なものであり、上記行為は、控訴人の人格的尊厳や名誉感情を侵害するものであるから、**と**が原稿作成者である控訴人に全く連絡しないまま別のテクストを掲載するという選択肢を他の複数の選択肢の中から敢えて選択した行為は、控訴人の人格的尊厳や名誉感情を侵害しようという不当な動機に駆り立てられた悪意あるものというべきである。
(キ)したがって、判決に影響を及ぼすことが明らかな、弁論における控訴人の主張を全く検討せずに控訴人の主張を排斥する当該判示の審理判断には、判断遺脱、審理不尽、理由不備の違法に加え、経験則違反の違法があると言わざるを得ない。」
(控訴理由書第2章第4・2(2)イ、77頁)
上記引用を要約すると、選択は常に意図的なものであるから、いくつかの可能な選択肢の中から、**と**は敢えて意図的に原稿作成者である上告人に全く連絡しないまま別のテクストを掲載するという選択肢を選んだことは確かな事実である。この事実から、経験則によって、本件行為2が上告人の人格的尊厳や名誉感情を侵害しようという不当な動機に駆り立てられた悪意あるものであるという事実が容易に推認されるのである。
以上から、本件行為2が何ら業務上の合理性及び必要性もなく、上告人の人格と名誉を侵害することにより上告人に圧力を加え精神的負担を与えるという不当な目的を有するものであり、また社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであることは明白である。このような行為が職務上の地位・権限を逸脱・濫用したものであることは言うまでもない。したがって、原判決の判示とは全く逆に、本件行為2が被上告人法学部による上告人に対する不法行為を構成することは疑い得ない。
上記から明らかであるように、本件行為2に関する原審における上告人の主張についての認定判断において「前記(2)イに明記された諸事情を鑑みるに」という部分を原判決が不当に削除せず、控訴理由書第2章第4・2(2)イ(76~77頁)につき正当に審理判断していれば、本件行為2が不法行為ではないなどという不正な結論に達するはずはなかったのである。したがって、重要な具体的事実とそれらから経験則による推認を経て不法行為の存在を推認する上告人の主張につき全く認定判断及び審理判断することなく、不法行為はないなどとし、上告人の主張を排斥した原判決の判示には、判決結果に影響を及ぼす判断遺脱の法令違反、それに加え、用いるべき経験則を用いていないことから、経験則違反の法令違反、及び法令解釈適用を誤った法令違反がある。
ウ 本件行為3
(ア)原判決の判示
原判決は、前記2(3)アに引用した判示(原判決12頁)において、「しかし、本件各行為の行われた経緯は補正の上引用した原判決が認定をしたとおりであり、そのほか本件全証拠によっても、本件各行為につき業務上の合理性及び必要性を欠き、社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであると認めることはできない」と述べ、「被控訴人又は被控訴人の教職員による控訴人に対する不法行為があったものということはでき」ないと結論付ける。
(イ)上記判示における法令違反
前記2(2)エ(イ)に、本件行為2に関する原審における上告人の主張についての認定判断において「上記(ア)~(カ)より」という部分(控訴理由書第2章第4・3(1)イ(ア)~(カ)、80~82頁)が不当に削除されていることを指摘した。以下に当該部分を控訴理由書から引用する。
「 イ 判示の違法性
(ア)原審は、前記第2、1(3)アに明記された控訴人の主張及び前記第3、2(3)ア、イに明記された諸事実を不当に無視し、これらを検討することなく、上記のごとく判示している。したがって、判決に影響を及ぼすことが明らかな上記主張及び上記2点の事実を全く検討せずに控訴人の主張を排斥する当該判示の審理判断には、判断遺脱、審理不尽、理由不備の違法があると言わざるを得ない。
(イ)法学部ウェブサイトに語学宣伝の場を作るのであれば、教授会や語学会議等で周知すること、あるいは少なくとも、そのような場があることを法学部教職員が控訴人に個人的に教えることが、社会通念に照らして、組織運営の常識として、当然あるべき事態である。
(ウ)フランス語とドイツ語間の不平等状態が平成28年からほぼ5年間も続いていたのであるから、その間に、法学部ウェブサイトにおける語学宣伝の場の存在につき、教授会や語学会議等で周知したり、法学部教職員が控訴人に個人的に知らせることは、社会通念に照らして、組織運営の常識として、当然発生すべき事態である。
(エ)上記(イ)(ウ)のごとき事態は一切発生しなかった。法学部ウェブサイトにおける語学宣伝の場立ち上げの際も、その後の5年間にも、会議の場であれ、個人的にであれ、法学部ウェブサイトにおける語学宣伝の場の存在につき、法学部教職員が控訴人に情報を与えることは、一切なかった。この事実から、通常、語学教員であれば知っているべきであるところ、控訴人に関してだけは、法学部教職員全員が、控訴人が語学宣伝の場の存在につき知らないままでいる事態に平気でいる、つまり、知らないことが当然であると考えている、という事実が推認される。この新たに推認された事実からまた、法学部語学教員で控訴人だけが語学宣伝の場の存在につき知る権利が当然にない、と考えているという事実が推認される。さらに、この事実から、そして上記(イ)(ウ)からして、法学部教職員の誰もがもっているべきである、自身の専門分野や担当科目についての社会通念からして当然与えられるべき情報を与えられる権利を控訴人がもっていないと法学部教職員全員が考えているという事実が推認される。最後に、この事実から、法学部教職員が、法学部教職員が当然もっているべき権利を控訴人にだけは認めていないのであるから、控訴人の人格と名誉を尊重していないという事実、すなわち、法学部教職員が、控訴人の個人的尊厳と名誉感情を侵害しているという事実が推認されるのである。また、ここに法学部教職員による控訴人への仲間外しによる人間関係からの切り離しも容易に結論付けられる。
(オ)法学部ウェブサイトにおける語学宣伝の場立ち上げの際も、その後の5年間にも、会議の場であれ、個人的にであれ、法学部ウェブサイトにおける語学宣伝の場の存在につき、法学部教職員が控訴人に情報を与えることが、通常業務も範囲内で起こることであることから、本件行為3は、業務上の何らの合理性も必要性も有さないものである。
(カ)**始め法学部教職員が、敢えて社会通念を無視し、通常の業務を逸脱してまで、業務上の何らの合理性も必要性も有さない本件行為3を選択したのは、控訴人の個人的尊厳と名誉感情を損傷することによって控訴人に精神的圧迫を加えると同時に、フランス語履修者に比してドイツ語履修者のみを増やして控訴人を不利益に貶めようという不当な目的によるものと考えるほかはない。」(控訴理由書、80~82頁)
上記引用部分に確認される、具体的事実を踏まえての推認による事実認定から成る上告人の主張から、本件行為3が何ら業務上の合理性及び必要性もなく、上告人の人格と名誉を侵害することにより上告人に圧力を加え精神的負担を与えるという不当な目的を有するものであり、また社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであることは明白である。このような行為が職務上の地位・権限を逸脱・濫用したものであることは言うまでもない。したがって、原判決の判示とは全く逆に、本件行為3が被上告人法学部による上告人に対する不法行為を構成することは疑い得ない。
上記から明らかであるように、本件行為3に関する原審における上告人の主張についての認定判断において「上記(ア)~(カ)より」という部分を原判決が不当に削除せず、控訴理由書第2章第4・3(1)イ(ア)~(カ)(80~82頁)につき正当に審理判断していれば、本件行為3が不法行為ではないなどという不正な結論に達するはずはなかったのである。したがって、重要な具体的事実とそれらから経験則による推認を経て不法行為の存在を推認する上告人の主張につき全く認定判断及び審理判断することなく、不法行為はないなどとし、上告人の主張を排斥した原判決の判示には、判決結果に影響を及ぼす判断遺脱の法令違反、それに加え、用いるべき経験則を用いていないことから、経験則違反の法令違反、及び法令解釈適用を誤った法令違反がある。
エ 本件行為4
(ア)原判決の判示
原判決は、前記2(3)アに引用した判示(原判決12頁)において、「しかし、本件各行為の行われた経緯は補正の上引用した原判決が認定をしたとおりであり、そのほか本件全証拠によっても、本件各行為につき業務上の合理性及び必要性を欠き、社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであると認めることはできない」と述べ、「被控訴人又は被控訴人の教職員による控訴人に対する不法行為があったものということはでき」ないと結論付ける。
(イ)上記判示における法令違反
前記2(2)オ(イ)に、本件行為4に関する原審における上告人の主張についての認定判断において、「上記(ア)(イ)から、平成19年に、履修者10名以上語学科目6コマ+教養演習1コマ計7コマという条件を守っていないことを理由として、控訴人の教養演習を潰した**、**、**らの行為は(被控訴人第1準備書面、8~9頁)」という部分、及び控訴理由書第2章第4・4(2)イ(ウ)が不当に削除されていることを指摘した。以下に当該部分を控訴理由書から引用する。
「 イ 判示の違法性
(ア)平成23年の「教養演習開講方針」には、教養演習開講の必要条件として履修者10名以上語学科目6コマ+教養演習1コマ計7コマが定められているが、平成23年以後10年以上にもわたって控訴人以外のほぼすべての語学教員らによる数多くの教養演習やセミナーがこの条件を満たさないまま開講されている。(甲28,甲91の1~19、甲92)上記の事実から、また語学教員らが勝手に法学部で定められた開講方針を破って教養演習を開講することは考えられず、またそうしようと思っても開講が許されるはずもないことは自明であることから、**法学部長ら法学部の実力者が、控訴人以外の語学教員には「教養演習開講方針」に従わなくてよいことを伝え、それによって控訴人だけがこれに従うようにし向けたという事実が推認される。この事実から、また、被控訴人が弁論において(第3準備書面)令和5年度の控訴人の担当コマ数を4コマにしたことを不当に正当化するために5コマでよいと主張している事実から、6コマという開講条件そのものが虚偽であり不正なものであるという事実が推認されることをも鑑みて、「教養演習開講方針」が控訴人の教養演習開講を妨げようという不当な目的によって作成された不正な文書であるという事実が推認されるとともに、法学部の実力者に大半の語学教員が同調した仲間外しが存在する事実も推認されるのである。
(イ)教養演習開講にあたって、控訴人が平成18年及び平成19年に開講していた時より厳しい条件を課す虚偽の開講方針を作ることにより、控訴人が再び教養演習を開講することをあきらめるように仕向け、控訴人以外の語学教員には開講方針が虚偽のものであることを伝えて、開講を促す行為は、組織の一成員だけを仲間外しし、差別することであるから、社会通念に照らし、通常人が許容し得る範囲を超えており、何らの業務上の合理性及び必要性をも有さないものであることは明白である上、職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、法学部専任教員として本来享受することのできるはずの権利を控訴人にだけは策略をもって拒否することによって、差別された控訴人の人格と名誉を侵害することを通して、控訴人に精神的圧力をかけることを主眼とした不当な目的によるものであることから、不法行為上も違法であるというべきである。」(控訴理由書第2章第4・4(3)イ(ア)(イ)、87~88頁)
「(ウ)もし法学部が控訴人を仲間外ししていない通常の健全な組織であり、法学部の成員としての控訴人の人格と名誉を普通に尊重しているのであれば、たとえ控訴人から開講の申し出がなかったとしても、12年間にわたり語学教員のなかで控訴人だけが教養演習を一度も開講していないという異常な事態に目をつぶることはできず、教授会その他の会議、あるいは個人的にでも控訴人に対して、教養演習は開講方針を遵守しなくても開講できる旨を伝え、控訴人に開講を促す等の配慮をすることが社会通念からして相当であったところ、法学部教職員から控訴人へのそのような情報伝達および働きかけは一切なかった。12年の長きにわたり、控訴人に教養演習開講に関する情報を与えず、控訴人だけが教養演習を開講していない状況を維持し続ける行為は、明らかに社会通念の許容範囲を超えており、業務上の何らの合理性も必要性も有さぬものであり、法学部成員に対して当然認められるべき権利を控訴人にだけ拒むことにより、組織の成員としての控訴人の人格と名誉を侵害し、控訴人に対して継続的な圧力を加えることを主眼とした不当な目的によるものであることから、不法行為を構成するというべきである。(控訴理由書第2章第4・4(2)イ(ウ)、86頁)
上記引用部分から、本件行為4が何ら業務上の合理性及び必要性もなく、上告人の人格と名誉を侵害することにより上告人に圧力を加え精神的負担を与えるという不当な目的を有するものであり、また社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであることは明白である。このような行為が職務上の地位・権限を逸脱・濫用したものであることは言うまでもない。したがって、原判決の判示とは全く逆に、本件行為4が被上告人法学部による上告人に対する不法行為を構成することは疑い得ない。
上記から明らかであるように、本件行為4に関する原審における上告人の主張についての認定判断において、控訴理由書第2章第4・4(3)イ(ア)(イ)及び第2章第4・4(2)イ(ウ)を原判決が不当に削除せず、これにつき正当に審理判断していれば、本件行為4が不法行為ではないなどという不正な結論に達するはずはなかったのである。したがって、重要な具体的事実とそれらから経験則による推認を経て不法行為の存在を推認する上告人の主張につき全く認定判断及び審理判断することなく、不法行為はないなどとし、上告人の主張を排斥した原判決の判示には、判決結果に影響を及ぼす判断遺脱の法令違反、それに加え、用いるべき経験則を用いていないことから、経験則違反の法令違反、及び法令解釈適用を誤った法令違反がある。
上記に加え、原判決は、2018年度、20年度、21年度、22年度の4年間で、多くの法学部語学専任教員が、教養演習1コマ+語学科目6コマ計7コマで履修者数10人以上を教養演習開講の条件として定めた教養演習開講方針に違反する形で教養演習を開講している事実を証明する甲91の1~19を始め、甲28、甲92等、重要な証拠につき全く検討していない。採用すべき証拠を採用しないまま、被上告人による不法行為はないなどとして、上告人の主張を排斥する原判決の上記判示には、判決結果に影響を及ぼす採証法則に反する法令違反がある。
(ウ)原判決による第一審「当裁判所の判断」欄の追加部分
第一審「当裁判所の判断」欄の原判決による不当な追加部分を以下に再び引用する。
「このメールで言及されている「教養演習開購方針」は、①授業形態は、いわゆる「ゼミナール」として開講されるものであるため、学生が研究・発表・討議を行うことを主眼とした演習授業とする、②教養演習の担当を希望する場合には、法学部時間割編成方針の「一般教養科目担当教員の担当コマ数については、6コマを基本とする」に基づき、従来の担当6コマに追加する形で担当をする、③履修人数については、法学部時間割編成方針の「演習科目は、原則として最低10名の履修者を確保するものとする」に基づき、10名の履修者確保を開講の目途とし、希望者が1 0名に満たない場合には、開講しないことがあり得るというものである」(原判決、10頁)
(エ)上記判示における法令違反
上記判示は、乙3号証のほぼ忠実な引用から成る。「教養演習開購方針」を上記のごとく、あたかも信頼に足る文書であるかのように援用する原判決の上記判示は、控訴理由書第2章第4・4(3)イ(ア)(イ)(87~88頁)に明記された、平成23年以後10年以上にもわたって上告人以外のほぼすべての語学教員らによる数多くの教養演習やセミナーがこの条件を満たさないまま開講されている事実、法学部の実力者が、上告人以外の語学教員には「教養演習開講方針」に従わなくてよいことを伝え、それによって控訴人だけがこれに従うようにし向けたという事実、「教養演習開講方針」が上告人の教養演習開講を妨げようという不当な目的によって作成された不正な文書であるという事実等、及びそれらに関わる上告人の主張のすべてにつき全く審理判断していいない点において、判決結果に影響を及ぼす判断遺脱の法令違反を犯しているというほかはない。また、控訴理由書第2章第4・4(3)イ(ア)(イ)に記載された諸事実にもかかわらず、「教養演習開講方針」を信頼に足る文書とみなしている点において、経験則の適用を誤っていると言え、原判決の上記判示には、判決結果に影響を及ぼす経験則違反の法令違反がある。さらに、多くの法学部語学専任教員が、教養演習1コマ+語学科目6コマ計7コマで履修者数10人以上を教養演習開講の条件として定めた教養演習開講方針に違反する形で教養演習を開講している事実を証明する甲91の1~19を始め、甲28、甲92等、重要な証拠を全く無視している点において、原判決には判決結果に影響を及ぼす採証法則に反する法令違反がある。
(オ)原判決による第一審「当裁判所の判断」欄の追加部分
「また、控訴人は、「教養演習開講について」との学部長文書をもって、過去のハラスメントを明文化して正当化するとともに、控訴人が過去に担当した教養演習より厳しい条件を課すことで、控訴人が教養演習を再開講することをあきらめさせようとしたとの主張をする。
しかし、「教養演習開講方針」の内容等上記アにおいて認定をした諸事情に照らし、教養演習の開購に関する文書が過去のハラスメントを明文化して正当化し、控訴人が過去に担当した教養演習より厳しい条件を課すことで、控訴人が教養演習を再開講することをあきらめさせようとしたものであるということはできず、ほかにこれを認めるに足りる証拠もない。この点に関する控訴人の主張も、採用することができない。」(原判決10~11頁)
(カ)上記判示における法令違反
前記(イ)より、原判決の上記判示は、原審弁論における上告人の主張(控訴理由書第2章第4・4(3)イ(ア)(イ)、87~88頁)につき全く審理判断せず、また教養演習1コマ+語学科目6コマ計7コマで履修者数10人以上を教養演習開講の条件として定めた教養演習開講方針に違反する形で教養演習を開講している事実を証明する甲91の1~19を始め、甲28、甲92等、重要な証拠を全く無視したまま「これを認めるに足りる証拠もない」などと述べ、上告人を主張を排斥しているのであるから、原判決には判決結果に影響を及ぼす判断遺脱の法令違反及び採証法則に反する法令違反がある。
オ 本件行為5
(ア)原判決の判示
原判決は、前記2(3)アに引用した判示(原判決12頁)において、「しかし、本件各行為の行われた経緯は補正の上引用した原判決が認定をしたとおりであり、そのほか本件全証拠によっても、本件各行為につき業務上の合理性及び必要性を欠き、社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであると認めることはできない」と述べ、「被控訴人又は被控訴人の教職員による控訴人に対する不法行為があったものということはでき」ないと結論付ける。
(イ)上記判示における法令違反
前記2(2)カ(イ)に、本件行為5に関する原審における上告人の主張についての認定判断において、上告人の主張の一部(控訴理由書第2章第4・5(3)イ、91頁)が不当に削除されていることを指摘した。以下に当該部分を控訴理由書から引用する。2か所の下線部が不当な削除部分である。
「 イ 判示の違法性
(ア)法学部のほとんどすべての専任教員が「長」のつく何らかの役職を経験している中、職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、控訴人にだけ20年以上も何らの役職にもつかせないという行為は、社会通念に照らし、組織のあり方に関する通常人の常識からすれば、合理性を欠き、控訴人に対する仲間外しや差別を結論せざるを得ないものであり、許容される範囲を大きく超えるものであると言うべきであり、社会通念上許されない社会的相当性を欠いたものであるというほかない。
(イ)当該行為は、通常業務の範囲内では起こり得ないものであり、何ら業務上の合理性及び必要性を有さないものである。しかも当該行為の継続期間が社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであり、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであることは明白である。
(ウ)当該行為は、その継続期間の長さからしても偶然のものとはみなされ得ず、控訴人の人格及び名誉感情を傷つけると同時に、控訴人を法学部内において軽視されるべき位置に20年以上の長きにわたって置き続けることによって控訴人の孤立状態を激化させ、継続的な圧力を長期間にわたり控訴人に加え続けることにより、控訴人に精神的負担及び精神的苦痛を与え続けることを主眼とした不当な目的によるものである。」(控訴理由書第2章第4・5(3)イ(ア)~(ウ)、91頁、下線は引用者による)
本件行為5の不法行為性につき適切に判断するためには、法学部のほとんどすべての専任教員が「長」のつく何らかの役職を経験しているところ、控訴人にだけ20年以上も何らの役職にもつかせていないという事実である。上記引用にある通り、本件行為5の長期にわたる継続性を証すこの事実を考慮に入れると、社会通念に照らして許容される範囲を超える社会的相当性を欠いたものであるであること、そして業務上の合理性及び必要性を全く有さぬものであることは明白である。
以上から、本件行為5が何ら業務上の合理性及び必要性もなく、上告人の人格と名誉を侵害することにより上告人に圧力を加え精神的負担を与えるという不当な目的を有するものであり、また社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであることは明白である。このような行為が職務上の地位・権限を逸脱・濫用したものであることは言うまでもない。したがって、原判決の判示とは全く逆に、本件行為5が被上告人法学部による上告人に対する不法行為を構成することは疑い得ない。
上記から明らかであるように、本件行為5に関する原審における上告人の主張についての認定判断において上告人の主張の重要部分を原判決が不当に削除せず、控訴理由書第2章第4・5(3)イ(ア)~(ウ)(91頁)につき正当に審理判断していれば、本件行為5が不法行為ではないなどという不正な結論に達するはずはなかったのである。したがって、本件行為5の長期にわたる継続性を証す重要な具体的事実とそれらから経験則による推認を経て不法行為の存在を推認する上告人の主張につき全く認定判断及び審理判断することなく、不法行為はないなどとし、上告人の主張を排斥した原判決の判示には、判決結果に影響を及ぼす判断遺脱の法令違反、それに加え、用いるべき経験則を用いていないことから、経験則違反の法令違反、及び法令解釈適用を誤った違法がある。
カ 本件行為6
(ア)原判決の判示
原判決は、前記2(3)アに引用した判示(原判決12頁)において、「しかし、本件各行為の行われた経緯は補正の上引用した原判決が認定をしたとおりであり、そのほか本件全証拠によっても、本件各行為につき業務上の合理性及び必要性を欠き、社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであると認めることはできない」と述べ、「被控訴人又は被控訴人の教職員による控訴人に対する不法行為があったものということはでき」ないと結論付ける。
(イ)上記判示における法令違反
前記2(2)キ(イ)に、本件行為6に関する原審における上告人の主張についての認定判断において「上記(イ)からして」という部分(控訴理由書第2章第4・6(1)イ(イ)、92~93頁)及び上告人の主張の一部(控訴理由書第2章第4・6(1)イ(ウ)、93頁)が不当に削除されていることを指摘した。以下に当該部分を控訴理由書から引用する。2か所の下線部が不当な削除部分である。
「(イ)非常勤講師採用審査にあたって、控訴人を主査にしたのであれば、主査に主要役割を副査に副次的役割を負わせ、副査の見解を審査結果報告書に反映させ掲載したのであれば、主査についてはより多く反映・掲載するのが、社会通念に照らして組織で通常起こるべきことであり、また、通常業務の範囲内で起こることである。(控訴理由書92~93頁)
(ウ)上記(イ)からして、職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、主査である控訴人の所見を副査のそれより下位に置いたり、審査結果報告書に全く掲載もせず反映もさせないという行為は、明らかに社会通念に反しており、また、何ら業務上の合理性も必要性も有さず、控訴人に対して、わざわざそのような社会通念に反し、通常業務を逸脱した行為を選択する以上、控訴人のフランス文学者としての経歴と名誉を無視し、控訴人の人格及び名誉を侵害することを通して、控訴人に精神的圧力を加えることを主眼とした不当な目的による行為であると言わざるを得ない。」(控訴理由書93頁)
以上から、本件行為6が何ら業務上の合理性及び必要性もなく、上告人の人格と名誉を侵害することにより上告人に圧力を加え精神的負担を与えるという不当な目的を有するものであり、また社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであることは明白である。このような行為が職務上の地位・権限を逸脱・濫用したものであることは言うまでもない。したがって、原判決の判示とは全く逆に、本件行為6が被上告人法学部による上告人に対する不法行為を構成することは疑い得ない。
上記から明らかであるように、本件行為6に関する原審における上告人の主張についての認定判断において「上記(イ)からして」という部分及び上告人の主張の一部を原判決が不当に削除せず、(控訴理由書第2章第4・6(1)イ(イ)(ウ)、92~93頁)につき正当に審理判断していれば、本件行為6が不法行為ではないなどという不正な結論に達するはずはなかったのである。したがって、重要な具体的事実とそれらから経験則による推認を経て不法行為の存在を推認する上告人の主張につき全く認定判断及び審理判断することなく、不法行為はないなどとし、上告人の主張を排斥した原判決の判示には、判決結果に影響を及ぼす判断遺脱の法令違反、それに加え、用いるべき経験則を用いていないことから、経験則違反の法令違反、及び法令解釈適用を誤った法令違反がある。
キ 本件行為7
(ア)原判決の判示
原判決は、前記2(3)アに引用した判示(原判決12頁)において、「しかし、本件各行為の行われた経緯は補正の上引用した原判決が認定をしたとおりであり、そのほか本件全証拠によっても、本件各行為につき業務上の合理性及び必要性を欠き、社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであると認めることはできない」と述べ、「被控訴人又は被控訴人の教職員による控訴人に対する不法行為があったものということはでき」ないと結論付ける。
(イ)上記判示における法令違反
前記2(2)ク(イ)に、本件行為7に関する原審における上告人の主張についての認定判断において「前記第3、2(7)ア、イ、ウに明示された状況で」という部分(控訴理由書第2章第3・2(7)ア、イ、ウ、63~64頁)及び上告人の主張の一部(控訴理由書第2章第4・7(1)イ(イ)、95頁)が不当に削除されていることを指摘した。以下に当該部分を控訴理由書から引用する。
「ア 遺脱された事実1
被控訴人東洋大学は、東洋大学でただ一人控訴人のみに、ほぼ10年連続で他の入試業務をほとんどさせず、日本人であれば誰でもできる留学生日本語試験採点を強要した。ほぼ10年連続で当該業務を担当したのは東洋大学で控訴人ただ一人であり、平成19年以降、現在に至るまで、法学部で当該業務を担当したのは、控訴人ただ一人である。言い換えれば、法学部で控訴人以外に当該業務を担当した教員は一人もいない。(控訴人本人調書、7~8頁、甲53)
イ 遺脱された事実2
ほぼ10年間にわたって、控訴人の担当した留学生日本語試験採点の日の法学部での試験監督出向は控訴人だけであり、法学部の他のほとんどすべての教員は別の日の面接試験担当となっていた。(控訴人準備書面5,25頁、甲53、控訴人本人調書、8頁)
ウ 遺脱された事実3
2007年から少なくとも2014年まで(あるいは2015年まで)の8年間(あるいは9年間)にわたって、被控訴人東洋大学法学部は、教授会資料に載る10月・11月推薦入試出向教員一覧の一番上に他から切り離した形でしかも他の教員の氏名より大きな活字で控訴人の氏名を印刷した。ちなみに控訴人の氏名は一覧表などに載る時はいつも一番下や最後に書かれるので、一番上に書かれたのはこの時だけであった。教授会資料に挿入される、出向日ごとに入試業務担当教員を分類・区分した10月・11月推薦入試出向教員一覧表において、例えば10月19日であれば、一番上に置かれた10月19日の欄に一人だけ書かれた控訴人の氏名がことさら大きな活字で印刷され、その下の別の日にち欄に印刷された多数の法学部教員の氏名との対照が際立つようにされていた。(控訴人準備書面5,25頁、甲53、控訴人本人調書、8頁)」(控訴理由書第2章第3・2(7)ア、イ、ウ、63~64頁)
「前記第3、2(7)ア、イ、ウに明示された状況で、職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、ほぼ10年連続で留学生日本語試験採点の仕事を東洋大学で控訴人のみに強要する行為は、10年連続という期間が社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであることに加え、何ら業務上の合理性及び必要性がなく、控訴人を人間関係から切り離しつつ控訴人を10年間という長きにわたって当該業務のみに縛り付けることによって、控訴人に屈辱感を味合わせ、控訴人の人格や名誉を侵害し、控訴人に継続的圧力を加え続けることによって、控訴人に大きな精神的苦痛を感じさせることを主眼とした不当な目的によるものと考えるほかはない。」(控訴理由書第2章第4・7(1)イ(イ)、95頁、下線部が不当な削除部分である)
本件行為7の不法行為性につき適切に判断するためには、本件行為7がほぼ10年続いたという事実ののみならず、留学生日本語試験採点をほぼ10年連続で担当したのが東洋大学で上告人ただ一人であるという事実、及び法学部で当該業務を担当したのが上告人ただ一人である事実につき審理判断することが不可欠である。第一審判決と同様、原判決も上記2点の事実につき一切認定判断及び審理判断していない点で全く失当であるというほかはない。
上記引用部分から、本件行為7が何ら業務上の合理性及び必要性もなく、上告人の人格と名誉を侵害することにより上告人に圧力を加え精神的負担を与えるという不当な目的を有するものであり、また社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであることは明白である。このような行為が職務上の地位・権限を逸脱・濫用したものであることは言うまでもない。したがって、原判決の判示とは全く逆に、本件行為7が被上告人法学部による上告人に対する不法行為を構成することは疑い得ない。
上記から明らかであるように、本件行為7に関する原審における上告人の主張についての認定判断において「前記第3、2(7)ア、イ、ウに明示された状況で」という部分及び上告人の主張の一部を原判決が不当に削除せず、控訴理由書第2章第3・2(7)ア、イ、ウ(63~64頁)及び控訴理由書第2章第4・7(1)イ(イ)(95頁)につき正当に審理判断していれば、本件行為7が不法行為ではないなどという不正な結論に達するはずはなかったのである。したがって、重要な具体的事実とそれらから経験則による推認を経て不法行為の存在を推認する上告人の主張につき全く認定判断及び審理判断することなく、不法行為はないなどとし、上告人の主張を排斥した原判決の判示には、判決結果に影響を及ぼす判断遺脱の法令違反、それに加え、用いるべき経験則を用いていないことから、経験則違反の法令違反、及び法令解釈適用を誤った法令違反がある。
(ウ)原判決による第一審「当裁判所の判断」欄の追加部分
第一審「当裁判所の判断」欄の原判決による不当な追加部分を以下に再び引用する。
「また、控訴人は、控訴人が法学部内の人間関係から隔離されていることを法学部教員らに象徴的に示すとともに、控訴人にもそれをはっきりと示して精神的苦痛を与えるために、法学部では、教授会資料に掲載される推薦入試出向教員一覧の一番上にほかと切り離した形でほかの教員の氏名より大きな活字で控訴人の氏名を印刷したとの主張をする。
しかし、仮に控訴人指摘の事情を考慮したとしても、控訴人が主張をする意図を推認することはできず、控訴人の人格権等の権利を侵害するものと認めることもできないから、この点に関する控訴人の主張も採用することができない。」(原判決11頁)
(エ)上記判示における法令違反
留学生日本語試験採点をほぼ10年連続で担当したのが東洋大学で上告人ただ一人であるという事実、法学部で当該業務を担当したのが上告人ただ一人である事実を鑑み、本件行為1~9及び第一審において上告人が「付随的ハラスメント」と呼んだ明白なパワハラや令和6年に控訴人に授業を全く担当させなかった明白なパワハラ行為の存在を考え合わせれば、上告人が被上告人法学部において永年の間、仲間外しによる人間関係からの切り離しを被り、それにより精神的苦痛を感じていたことは明白であり、この状況で、上記行為が発生したのであるから、留学生日本語試験採点業務における上告人の置かれた孤立状態からして、上記行為が、この孤立状態を強調することにより上告人にさらなる精神的苦痛を与えると同時に法学部における上告人の立場をより悪化させ、上告人の人格を侵害させると同時に上告人を不利益に陥れる不当な目的をもったものであることは、十分に推認可能である。したがって、上告人の主張を排斥する原判決の上記判示には、経験則違反の法令違反、採証法則に反する法令違反及び法令解釈・適用を誤った違法がある。
ク 本件行為8
(ア)原判決の判示
原判決は、前記2(3)アに引用した判示(原判決12頁)において、「しかし、本件各行為の行われた経緯は補正の上引用した原判決が認定をしたとおりであり、そのほか本件全証拠によっても、本件各行為につき業務上の合理性及び必要性を欠き、社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであると認めることはできない」と述べ、「被控訴人又は被控訴人の教職員による控訴人に対する不法行為があったものということはでき」ないと結論付ける。
(イ)上記判示における法令違反
前記2(2)ケ(イ)に、本件行為8に関する原審における上告人の主張についての認定判断において、上告人の主張の一部が不当に削除されていることに加え、以下に引用する判決に影響を及ぼす重要な具体的事実およびそれに関する上告人の主張が不当に遺脱されていることを指摘した。以下に当該部分を控訴理由書から引用する。下線部が不当な削除部分である。
「(ウ)教員の専門的学問につき何らの見識をも有さない被控訴人法学部教務課職員が、職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、フランス文学専門の研究者であり、教授の地位にある控訴人に何ら相談もなく控訴人の原稿を修正した行為、及び目の前にいる控訴人にわざわざ朱の入った原稿を見えるようにしておきながら、控訴人に全く相談することなく控訴人の原稿の修正点についての検討を続行しようとした行為は、いずれも控訴人も交えて検討するのが社会通念からして、組織運営の常識として、相当であることから、社会通念に照らして極めて異常であり、通常人の許容する範囲を超えている。
(エ)上記行為は、控訴人も交えて検討するのが大学業務において通常のことであることから、通常の業務範囲を超えており、何ら業務上の合理性及び必要性を有するものではない。
(オ)当該行為のいずれにおいても、控訴人に相談するという、社会通念からしても、通常業務のあり方からしても、相当である選択肢を被控訴人法学部教務課職員が敢えて採らず、わざわざ社会通念からしても通常業務のあり方からしても相当でない当該行為を選択したという事実から、当該行為が、控訴人を無視し、控訴人の教授としての名誉を踏みにじることで、控訴人が法学部内で長期にわたって仲間外しされた極めて弱い立場に置かれていることを強調することによって控訴人の人格と名誉感情を侵害し、控訴人に精神的圧力を加えることを通して、精神的苦痛を与えることを主眼とした不当な目的によるものである事実が推認される。また、法学部教務課職員が社会通念及び通常の業務範囲の許容し得る範囲を大きく超えて、当該行為に及ぶことが可能であり、当該行為を可能にする状況が法学部にあったという事実から、控訴人を仲間外しし、孤立化させ、控訴人に有形無形の継続的圧力を加えることが法学部内で常態化していたことも確認される。」(控訴理由書第2章第4・8(1)イ(ウ)~(オ)、97~98頁、下線は引用者による)
以上から、本件行為8が何ら業務上の合理性及び必要性もなく、上告人の人格と名誉を侵害することにより上告人に圧力を加え精神的負担を与えるという不当な目的を有するものであり、また社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであることは明白である。このような行為が職務上の地位・権限を逸脱・濫用したものであることは言うまでもない。したがって、原判決の判示とは全く逆に、本件行為8が被上告人法学部による上告人に対する不法行為を構成することは疑い得ない。
上記から明らかであるように、本件行為8に関する原審における上告人の主張についての認定判断において上告人の主張の一部を原判決が不当に削除せず、控訴理由書第2章第4・8(1)イ(ウ)~(オ)(97~98頁)に確認される具体的事実に関する推認による事実認定から成る上告人の主張つき正当に審理判断していれば、本件行為8が不法行為ではないなどという不正な結論に達するはずはなかったのである。したがって、重要な具体的事実とそれらから経験則による推認を経て不法行為の存在を推認する上告人の主張につき全く認定判断及び審理判断することなく、不法行為はないなどとし、上告人の主張を排斥した原判決の判示には、判決結果に影響を及ぼす判断遺脱の法令違反、それに加え、用いるべき経験則を用いていないことから、経験則違反の法令違反、及び法令解釈適用を誤った法令違反がある。
ケ 本件行為9
(ア)原判決の判示
原判決は、前記2(3)アに引用した判示(原判決12頁)において、「しかし、本件各行為の行われた経緯は補正の上引用した原判決が認定をしたとおりであり、そのほか本件全証拠によっても、本件各行為につき業務上の合理性及び必要性を欠き、社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであると認めることはできない」と述べ、「被控訴人又は被控訴人の教職員による控訴人に対する不法行為があったものということはでき」ないと結論付ける。
(イ)上記判示における法令違反
前記2(2)コ(イ)に、本件行為9に関する原審における上告人の主張についての認定判断において、上告人の主張の一部が不当に削除されていることに加え、以下に引用する判決に影響を及ぼす重要な具体的事実およびそれに関する上告人の主張が不当に遺脱されていることを指摘した。以下に当該部分を控訴理由書から引用する。下線部が不当な削除部分である。
「(イ)職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、 フランス語予算と他言語予算との間に数10万から100万、200万に至る莫大な格差を10年間も維持するという行為は、社会通念からして、通常の組織であれば、たとえ控訴人が必要資料等を提出していなくても、教授会その他の会議において、あるいは個人的に、フランス語担当専任教員である控訴人に格差を是正する提案をすることが相当であるところ、そのような提案が10年間にわたって一切なかったのであるから、社会通念に照らして通常人の許容し得る範囲を大きく超えるものであり、社会相当性を欠いているというほかはない。
(ウ)当該行為は、明らかに通常業務の範囲を大きく超えており、何ら業務上の合理性及び必要性を有するものではない。
(エ)当該行為は、控訴人を同じ組織に属する法学部成員の一人として他の成員たちが認め、控訴人の法学部成員としての権利を認め、控訴人の人格と名誉を尊重しているのなら、発生し得ないものであることから、控訴人を法学部内で長期間にわたって仲間外しし、人間関係から切り離し、控訴人の人格と名誉を侵害し、控訴人に継続的な精神的圧力をかけることを主眼とした不当な目的によるものであると言うべきである。
(オ)「予算を要求する者が計画書や予算要求書、アンケート等を提出」すべきことが、教授会や語学会議その他の会議で周知されたこともなく、10年間の間にそれが控訴人に伝えられたことも一切なかったという事実は、仲間外しや差別等のパワハラがなく通常に機能している組織では起こり得ないことであることから、社会通念の許容する範囲及び通常の業務範囲を超えており、社会相当性を欠いたものである。
(カ)上記(イ)~(オ)から、本件行為9は、明白に不法行為を構成するものである。」(控訴理由書第2章第4・9(1)イ(イ)~(カ)、99~100頁)
「エ 遺脱された事実3
東洋大学法学部は2022年4月に、授業用図書等教材購入費でDVDを購入することができないよう規則を定めた。2022年4月法学部定例教授会にて「2022年度法学部予算執行要領」が可決された。この要領の8頁(教授会資料37頁)に「授業・講座等運営費は、授業で使用する図書購入のみが対象です」と書かれている。(甲56)」(控訴理由書第2章第3・2(9)エ、67頁)
「(イ)被控訴人は、10年以上も続く予算格差を是正する試みを全くせず、そればかりか、海外研修に専任教員の付き添いを急遽義務付けてフランス語海外研修実現を困難にしたり、予算格差を是正するためにフランス語予算を増やして欲しいという控訴人の度重なる訴えを拒否あるいは無視し、「2022年度法学部予算執行要領」によって教材費によるDVD購入を禁じるなど、悪意をもって予算格差を維持あるいは拡大することを図った。(甲56)」(控訴理由書第2章第4・9(2)イ(イ)、101頁)
上記引用部分から、本件行為9が何ら業務上の合理性及び必要性もなく、上告人の人格と名誉を侵害することにより上告人に圧力を加え精神的負担を与えるという不当な目的を有するものであり、また社会通念に照らして許容される範囲を超えるものであることは明白である。このような行為が職務上の地位・権限を逸脱・濫用したものであることは言うまでもない。したがって、原判決の判示とは全く逆に、本件行為9が被上告人法学部による上告人に対する不法行為を構成することは疑い得ない。
上記から明らかであるように、本件行為9に関する原審における上告人の主張についての認定判断において、上告人の主張の一部及び判決に影響を及ぼす重要な具体的事実およびそれに関する上告人の主張を原判決が不当に削除せず、控訴理由書第2章第4・9(1)イ(イ)~(カ)(99~100頁)、第3・2(9)エ(67頁)、及び第4・9(2)イ(イ)(99~100頁)につき正当に審理判断していれば、本件行為9が不法行為ではないなどという不正な結論に達するはずはなかったのである。したがって、重要な具体的事実とそれらから経験則による推認を経て不法行為の存在を推認する上告人の主張につき全く認定判断及び審理判断することなく、不法行為はないなどとし、上告人の主張を排斥した原判決の判示には、判決結果に影響を及ぼす判断遺脱の法令違反、それに加え、用いるべき経験則を用いていないことから、経験則違反の法令違反、及び法令解釈適用を誤った法令違反がある。
上記に加え、教材費によるDVD購入を禁じる「2022年度法学部予算執行要領」によって被上告人法学部が予算格差を維持あるいは拡大することを図ったことを証明する重要な証拠である甲56を全く無視したまま「本件全証拠によっても」などと述べ、上告人を主張を排斥しているのであるから、原判決の上記判示には判決結果に影響を及ぼす判断遺脱の法令違反に加え、採証法則に反する法令違反がある。
コ 小括
上記ア~ケから明白であるように、上告人が具体的事実を踏まえた推認過程を経て、本件行為1~9は不法行為であるという結論を出しているにもかかわらず、原判決の当該判示は、具体的事実を踏まえた上告人の主張はもとより、そもそも何ら本件行為1~9の発生した状況及び当該行為の諸様態等に関わる具体的事実を踏まえた推認をしないまま、不法行為はないとの結論を不当に出しているのである。どのような過程を経て判決結果に至ったのかが全く示されていない点で、原判決には理由不備があるというほかはない。原判決自体にこのような致命的な欠陥があるにもかかわらず、上告人の主張につき「独自の理解を述べるものにすぎない」などと言いなす原判決の審理態度は、公正、良心、品位を欠いたものであるというほかはない。
(2)原判決の判断枠組みと理由不備
上記(1)から明白であるように、原判決は、本件行為1~9が、どのような状況や文脈で、どのような社会通念や業務上の常識との関りを維持しつつなされた様態をもつ行為であるのかにつき、全く考慮せず、検討もしていない。社会通念や業務上の常識をも含んだ本件各行為発生の状況や文脈及び本件各行為の程度、継続期間、頻度、反復性等の様態に関する上告人の提示した具体的事実とそれらに関わる上告人の主張とが、原判決にあっては、ほとんどすべて切り捨てられている。しかし、社会通念や業務上の常識をも含んだ本件各行為発生の状況や文脈及び本件各行為の程度、継続期間、頻度、反復性等の様態につき検討せずに、本件各行為につき適切に判断できるわけがないのである。
原判決は、本件行為1~9を、行為の発生を取り巻く様々な状況や文脈から行為を切り離し、行為を孤立させて考えている。しかも、いわば、抽象空間に置かれた本件行為1~9について上告人が抽象的な主張をしているかのように、上告人の主張から、社会通念や業務上の常識をも含んだ本件各行為発生の状況や文脈及び本件各行為の程度、継続期間、頻度、反復性等の様態に関する重要部分を捨象してしまっている。このように原判決は、社会通念や業務上の常識をも含んだ本件各行為発生の状況や文脈及び本件各行為の程度、継続期間、頻度、反復性等の様態から切り離された本件行為1~9と、重要部分を欠いて歪められた上告人の主張を前提として判決結果を導き出した。このような判決には理由の一部が欠けているとしか言いようがない。これを言い換えると、原判決の判断枠組みは、パワハラ行為の不法行為性を検討するにあたって考慮することが必要不可欠である、社会通念や業務上の常識をも含んだパワハラ行為発生の状況や文脈及びパワハラ行為の程度、継続期間、頻度、反復性等の様態に関わる重要な具体的事実、及び後述する通り、上告人の精神的苦痛についての検討を全く欠いたまま、業務上の合理性及び必要性があるかどうか、社会通念に照らして許容されるかどうか等について結論を出すというものであり、かような誤った判断枠組みを用いてパワハラ及び不法行為の有無が問題になる本件各行為について判決結果を導く原判決には、理由の本質的部分が欠けていると考えざるを得ない。
パワハラ行為の不法行為性についての判断基準を示すものとしてしばしば援用される「ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル事件」原審判決には、「パワーハラスメントを行った者とされた者の人間関係、当該行為の動機・目的、 時間・場所、態様等を総合考慮の上」とあり、判例上からも、パワハラ行為発生に際しての諸状況や文脈及びパワハラ行為の諸様態を考慮することは、パワハラ行為の不法行為性について判断する際の常識となっている。「パワーハラスメントを行った者とされた者の人間関係、当該行為の動機・目的、 時間・場所、態様等を総合考慮の上、「企業組織もしくは職務上の指揮命令関係にある上司等が、職務を遂行する過程において、部下に対して、職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、社会通念に照らし客観的な見地からみて、通常人が許容し得る範囲を著しく超えるような有形・無形の圧力を加える行為」をしたと評価される場合に限り、被害者の人格権を侵害するものとして民法709条所定の不法行為を構成するものと解するのが相当である」。(東京地判平24・3・9労判1050号68頁)
パワハラ及びセクハラ等のハラスメント行為に関する最高裁判例を例にとっても、問題となるハラスメント行為の継続期間、頻度、反復性などの諸様態が不法行為の有無の判断基準となっていることが明白であることはいかに引用する3点の最高裁判例からも明らかである。「本件各行為は、5年を超えて繰り返され、約80件に上るものである。その対象となった消防職員も、約30人と多数であるばかりか、上告人の消防職員全体の人数の半数近くを占める。そして、その内容は、現に刑事罰を科されたものを含む暴行、暴言、極めて卑わいな言動、プライバシーを侵害した上に相手を不安に陥れる言動等、多岐にわたる。こうした長期間にわたる悪質で社会常識を欠く一連の行為に表れた被上告人の粗野な性格につき、公務員である消防職員として要求される一般的な適格性を欠くとみることが不合理であるとはいえない。また、本件各行為の頻度等も考慮すると、 上記性格を簡単に矯正することはできず、指導の機会を設けるなどしても改善の余 地がないとみることにも不合理な点は見当たらない。」(最大判令和4年9月13日集民269号21頁)「このように,同一部署内において勤務していた従業員Aらに対し,被上告人らが職場において1年余にわたり繰り返した上記の発言等の内容は,いずれも女性従業員に対して強い不快感や嫌悪感ないし屈辱感等を与えるもので,職場における女性従業員に対する言動として極めて不適切なものであって,その執務環境を著しく害するものであったというべきであり, 当該従業員らの就業意欲の低下や能力発揮の阻害を招来するものといえる。」「被上告人らは,上記の研修を受けていただけでなく,上告人の管理職として上記のような上告人の方針や取組を十分に理解し, セクハラの防止のために部下職員を指導すべき立場にあったにもかかわらず,派遣 労働者等の立場にある女性従業員らに対し,職場内において1年余にわたり上記のような多数回のセクハラ行為等を繰り返したものであって,その職責や立場に照らしても著しく不適切なものといわなければならない。」「従業員Aらが上告人に対して被害の申告に及ぶまで1年余にわたり被上告人らが本件各行為を継続していたことや,本件各行為の多くが第三者のいない状況で行われており,従業員Aらから被害の申告を受ける前の時点において,上告人が被上告人らのセクハラ行為及びこれによる従業員Aらの被害の事実を具体的に認識して警告や注意等を行い得る機会があったとはうかがわれないことからすれば,被上告人らが懲戒を受ける前の経緯について被上告人らに有利にしんしゃくし得る事情があるとはいえない。」(最大判平成27年2月26日集民249号109頁)「加えて、上記各働き掛けが第1処分の停職期間中にされたものであり、被上告人が上記非違行為について何ら反省していないことがうかがわれることにも照らせば、被上告人が業務に復帰した後に、上記非違行為と同種の行為が反復される危険性があると評価することも不合理であるとはいえない。」(最大判令和4年6月14日集民268号23頁)(下線はすべて引用者による)最高裁判例の上記引用より、本件行為1~9の不法行為性を判断するにあたって本件各行為発生の状況や文脈及び本件各行為の程度、継続期間、頻度、反復性等の様態をほぼ全く考慮に入れない原判決が最高裁判例に相反する判断を示していることは明らかである。
このように、社会通念や業務上の常識をも含んだ本件各行為発生の状況や文脈及び本件各行為の程度、継続期間、頻度、反復性等の様態に関わる具体的諸事実及びそれらに関する上告人の主張につき検討し判断することないまま、本件行為が社会通念の許容範囲を超えること及び業務上の合理性や必要性がないことを否定し、ひいては本件行為1~9の不法行為性を否定する原判決には、明らかに理由の一部が欠けており、理由不備の絶対的上告理由があると言えるのである。具体的判断を欠いた判決が理由不備の違法を犯していることになることは次の最高裁判例からも明らかである。「そして、 右特例法一一条二項によれば、同一項の規定による裁判には、処分が違法であること及び請求を棄却する理由を明示しなけれはならないものである。しかるに、原判決は、単に一般的に農地買収は公共の福祉のためになされるものであるから正に同法条を適用すべき場合に該当するものと解するを相当とする旨説示しただけで、具体的に本件について処分は違法であるが、処分を取り消し、又は変更することが公共の福祉に適合しない理由について何等首肯するに足りる理由を示していないのである。従つて、原判決は、この点において失当たるを免れない。」(最大判昭和29年7月19日民集8巻7号1387頁)
確かに、前述の通り、原判決は夥しい事実の遺脱を行っており、判断遺脱の違法を犯している。その場合、たとえ事実が遺脱されていても、判決自体がその理由において論理的に完結していれば理由不備とならないという説もある。次の最高裁判例は、そのような方向性をもったものとして知られる。
「右によれば、原判決には、判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断を遺 脱した違法があるといわなければならない。
五 しかしながら、【要旨】原判決の右違法は、民訴法三一二条二項六号により 上告の理由の一事由とされている「判決に理由を付さないこと」(理由不備)に当 たるものではない。すなわち、いわゆる上告理由としての理由不備とは、主文を導 き出すための理由の全部又は一部が欠けていることをいうものであるところ、原判 決自体はその理由において論理的に完結しており、主文を導き出すための理由の全 部又は一部が欠けているとはいえないからである。
したがって、原判決に所論の指摘する判断の遺脱があることは、上告の理由とし ての理由不備に当たるものではないから、論旨を直ちに採用することはできない。 しかし、右判断の遺脱によって、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法 令の違反があるものというべきであるから(民訴法三二五条二項参照)、本件につ いては、原判決を職権で破棄し、更に審理を尽くさせるために事件を原裁判所に差し戻すのが相当である。」(最判平成11年6月29日裁判集民193号411頁)
しかし、上記判例は、学術においては厳しく批判されており(松本博之『民事上告審ハンドブック』186~187頁)、また、上記判例自体も、判決理由が論理的に完結してさえいれば重要事実を適示しなくても自動的に理由不備にはならないということを意味しているのではないことは言うまでもない。なぜなら、そうなれば、判決理由自体に論理的整合性があれば、裁判所は重要事実を遺脱しても理由不備とならないということになり、それが極めて不正かつ不合理なことであるのは自明であるからだ。それに加えて、社会通念や業務上の常識をも含んだ本件各行為発生の状況や文脈及び本件各行為の程度、継続期間、頻度、反復性等の様態に関わる具体的諸事実及びそれらに関する上告人の主張につき検討し判断することないまま、本件行為1~9が社会通念の許容範囲を超えること及び業務上の合理性や必要性がないことを否定し、ひいては本件行為1~9の不法行為性を否定する原判決には、社会通念や業務上の必要性及び合理性の本件行為1~9各々に関しての具体的な現れ方について、そして本件各行為の具体的発生様態について、大きな欠落があり、この欠落により原判決が本件行為1~9につき論理的に正当な判断を下すことは事実上不可能であるという事情があるのであるから、原判決が論理的に完結しているとは言えず、したがって主文を導き出すための理由の全部又は一部が欠けていることは明白である。
前述の通り、発生時の状況や様々な発現様態から切り離された行為は、状況や文脈のうちにあり多様な様態を帯びた本来の行為とは全く別のものである。本来の行為とは異なる発生時の状況や様々な発現様態から切り離された行為につき検討し結論を出す原判決は、本来の行為につき判断したとは言えないのであるから、その判決理由も本来の行為についてのものではあり得ないことから、原判決に理由の一部が欠けていることは疑い得ない。とりわけ、原判決は、本件行為1~9が社会通念の許容範囲を超えること及び業務上の合理性や必要性がないことを否定するのであるが、本件行為1~9の各々に、業務上のいかなる常識に照らして業務上の必要性及び合理性があるのか、どのような領域に関するいかなる社会通念に照らして本件行為1~9が許容され得るものであるのか、につき原判決は全く審理判断していないのであるから、原判決による本件行為1~9が社会通念の許容範囲を超えておらず、業務上の合理性や必要性を有するものであるという結論は、推論過程に大きな論理的欠落を抱えたまま出した結論であると言え、原判決に論理的整合性を認めることは到底できないのである。
(3)小括
上記4(1)(2)より、原判決には、判決主文を導き出すための理由の一部が欠けていると言わざるを得ず、原判決に、民訴法312条2項6号に掲げる絶対的上告理由としての理由の不備があることは明白である(上告理由5)。
5 上告人の被った精神的苦痛についての判断遺脱と理由不備(上告理由6)
被上告人東洋大学による控訴人へのパワハラは、本件行為1~9に限定されるものではなく、時期的には、平成14年に始まり、平成20年に激化したものであり、規模の観点からすると、法学部のみならず東洋大学全学の関わる大規模な組織性を有するものである。永年の間、大学組織全体で仲間外しされ続けることにより孤立し、数多くのパワハラ行為の被害を被った上告人の精神的苦痛及び精神的損害は甚大なものであると言わざるを得ない。原審弁論において、上告人は、本件行為1~9に限定されない、長期にわたる継続性と大規模な組織性を有する総体としての本件パワハラが上告人に甚大な精神的圧力及び精神的不利益を与えて来たことを主張している。「本件各行為の不法行為性についてはもとより、総体としての本件パワハラの、社会通念に照らして通常人の許容し得る範囲を大きく超え、常軌を逸しているとすら言える長期にわたる継続性と大規模な組織性は、控訴人の人格と名誉の侵害による極めて大きな精神的圧力を控訴人に20年以上の長きにわたって加え続けるものといえ、本件各行為による精神的不利益の程度が、総体としての本件パワハラの長期にわたる継続性と大規模な組織性によってさらに増幅されることから、損害額500万円が相当である」(控訴理由書第2章第4、10(3)イ(イ)、104頁)。
原審弁論における上告人の上記主張につき全く審理判断せず、上告人の請求を排斥する原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱の違法がある。また、本件行為1~9につきパワハラの有無及び不法行為の有無を判断するにあたって、被害者である上告人の被った精神的苦痛及び精神的損害等につき一切審理判断しないという原判決の審理態度は不合理であるというほかはない。以下に引用する最高裁判例に照らしても、パワハラ及びセクハラ等に関して不法行為の有無を判断する際に、屈辱感等、被害者の精神的苦痛について検討することが当然なされるべきことであることは言うまでもない。「このように,同一部署内において勤務していた従業員Aらに対し,被上告人らが職場において1年余にわたり繰り返した上記の発言等の内容は,いずれも女性従業員に対して強い不快感や嫌悪感ないし屈辱感等を与えるもので,職場における女性従業員に対する言動として極めて不適切なものであって,その執務環境を著しく害するものであったというべきであり, 当該従業員らの就業意欲の低下や能力発揮の阻害を招来するものといえる。」(最大判平成27年2月26日集民249号109頁)
上記より、原判決の判決理由全体において、原判決が上告人の精神的苦痛及び精神的損害等につき一切審理判断していないことを鑑みれば、本件行為1~9の不法行為性につき判断するにあたって上告人の精神的苦痛を全く考慮しないことから、原判決が論理的に完結しているとは言えず、判決主文を導き出すための理由の一部が欠けていると言わざるを得ず、原判決に、民訴法312条2項6号に掲げる絶対的上告理由としての理由の不備があることは明白である(上告理由6)
6 原判決の理由齟齬(上告理由7)
前記第1で主張した通り、原判決は、「補正」の名のもとに第一審判決の夥しい判断遺脱部分を補ったり、違法部分を全面的に書き換えたりしつつ第一審判決を別の判決に変造しながら、第一審判決を「引用」すると述べている。ところが、引用とは、松本博之も指摘する通り、「控訴裁判所が引用部分の第一審判決の理由に従うことを自己の判決において明示的に確認していることを意味する」(松本博之『民事上告審ハンドブック』190頁)。そうすると、第一審判決を別の判決へと書き換えると同時に当該判決を「引用」するということは、二つの矛盾する行為から構成されていることになり、不可能であることになるので、原判決の理由づけには論理的矛盾があることになる。したがって、原判決には理由の食違いがあると言え、民訴法312条2項6号に掲げる絶対的上告理由としての理由齟齬がある(上告理由6)。
第4 結語
以上の通り、原判決には、憲法32条、憲法14条1項及び憲法76条3項に違反する憲法違反の上告理由(上告理由1,2,3)に加え、民訴法312条2項6号に掲げる絶対的上告理由としての理由の不備(上告理由4、5、6)及び理由齟齬(上告理由7)があるため、原判決は速やかに破棄されるべきである。
以 上